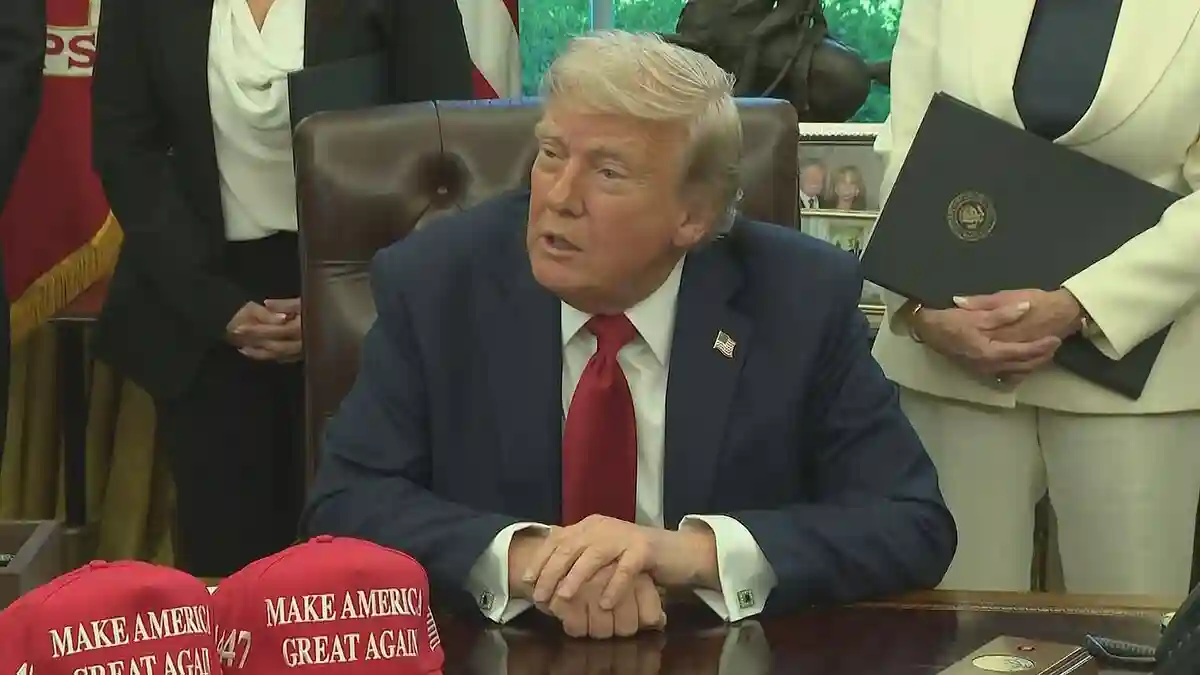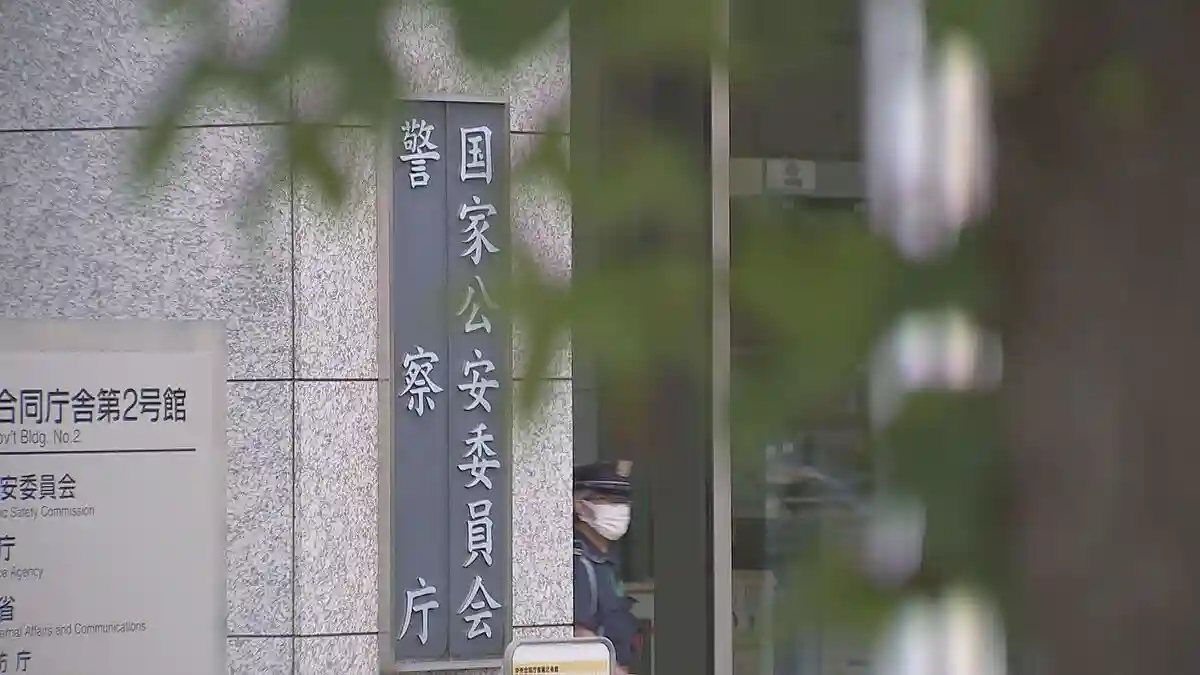「モームリ」が繁盛 五月病という言葉はもはや過去の遺物なのか、4月早々、退職を希望する新入社員が数多くいることが話題になっている。 本人に代わって退職の手続きその他を請け負う企業「退職代行モームリ」は連日「速報」としてその日の退職代行実績をX上で報告している。それによると、4月1日以降の新卒者で退職代行を依頼してきた人数は5人(1日)、8人(2日)、20人(3日)、13人(4日)、42人(7日)と推移。入社してすぐに「辞めたい」と考える社員が少なくないことが分かる。 【写真を見る】「退職代行」を利用して辞めた人の“退職理由”がエグい 人数もさることながら興味深いのはその理由。そのへんも同社はX上で一部公開している。いくつか引用してみると……、 「■社長が入社式の最中に新卒社員ともめて、みんなの前で怒鳴ったことに加え、廊下に出して『なめてんのか』と説教。(女性・事務関連) ■入職前の研修がありマナーやコミュニケーションなどの5時間ほどの研修で講師の方の脅しのような言葉、看護学生と社会人は違うとの言葉があり自信を無くしてしまった。(男性・医療関連) ■実際の業務を想像するだけで、すごく吐き気と鬱のような状態となり、働ける状態にないため。(男性・教育関連) ■思っていた接客業務と違い、やりがいを感じる機会がないと感じた。(女性・飲食業)」(4月1日の投稿より) 「■求人票に記載されていた出社時間と実際の出社時間が違った。(男性・不動産業) ■求人票には基本給16万+各種手当と記載があったが、実際の基本給は最低賃金を下回っていた。 養老孟司さんが語る「仕事の本質」とは ■入社後に休日出勤の必要があると説明を受けた。入社前はそのような説明は一切受けていなかった。(女性・教育関連) ■入社前に聞いていた出勤日数、休日日数と入社後に受けたそれらの説明の内容が違った。(女性・製造業) ■エージェント経由で入社したが、エージェントから受けていた説明と入社後に受けた説明が違った。(男性・建築業)」(4月2日の投稿より) 自分に合った仕事 これらを見て、「逃げて当然」と思う方もいることだろう。入社前の説明と入社後のそれのギャップがあまりに大きければ、だまされたと思うのは当然のこと。給与などの基本的な条件面でウソが多ければ、他も信用できないと思われても仕方はない。 生きていくうえで壁にぶつからない人はいない。それをどう乗り越えるか。どう上手にかわすか。「子どもは大人の予備軍ではない」「嫌なことをやってわかることがある」「人の気持ちは論理だけでは変わらない」「居心地の良い場所を見つけることが大切」「生きる意味を過剰に考えすぎてはいけない」——自身の幼年期から今日までを振り返りつつ、誰にとっても厄介な「人生の壁」を越える知恵を正面から語る 『人生の壁』養老孟司/著 一方で、理由によっては「我慢が足りない」「判断が早すぎるのでは」と感じる方もいるに違いない。 日々、やらなければならないこと、目の前にあることを片付けていくうちに、到達したのが偉業だった あまりにブラックな企業に入ってしまったケースは論外として、「すぐに辞める若者」について懸念されるのは、「辞め癖」のようなものがついてしまわないか、という点だ。 募集時の説明にある程度美辞麗句が含まれているのは、大人にとっては常識ともいえる。問題はその盛り具合だろう。「理想の職場ではない」ことで退職を考えてしまうと、いつまでも青い鳥を追い求めることになりかねない。 「自分に合った仕事」に就きたいと考えるのは普通のことで、これから社会人になる若者なら余計にそうだろう。 しかし、その考え方にとらわれることに問題がある、と指摘するのは養老孟司さんだ。『バカの壁』などで知られる養老さんは、新著『人生の壁』の中で、仕事に関して次のように述べている。 「仕事の本質は、目の前の穴を埋めることです。穴が空いていたら、困る人がいるだろう。だから埋める。その延長線上に偉業があるかもしれないし、ないかもしれない。 ここを理解していない人がとても多いのです。仕事というのはあらかじめ存在しているものだというのは勘ちがいです。そういう勘ちがいをする人はともすれば、上司や会社に『私の仕事を定義してください』などと求めることになる。そんなことは事前に完全に定められるものではないというのが理解できていないのです。 まず存在しているのは『穴』のほうです。需要と言ってもいいでしょう。自分のやりたいことが先にあるのではなく、求められることが先にある」 これは養老さんの持論ともいえる仕事論だ。ともすれば人は「自分に合った仕事」を追い求める。もちろんそういうものと出会えればいいだろうが、そんな都合の良いものが転がっているとは限らない。それよりもやってほしいと思われること、やるべきだと感じること、すなわち「穴」を埋めていくことを心がけたほうがいいのではないか、という考え方である。 偉業は「穴埋め」の先にある 上の文章にある「偉業」の実例として同書ではアフガニスタンの復興に尽力した中村哲さんを取り上げている。それが「穴」とどう関係しているか。 「たとえばアフガニスタンの復興に人生を捧げた中村哲さんは、もともとは虫が好きで蝶を求めてアフガニスタンに行ったことで、現地と縁ができました。その後、医者として同国に赴任し、調べていくうちに、問題は個々の患者ではなく、インフラなど現地の環境にあると気づく。そして見捨てられた農地をよみがえらせるためには、水を引かなければと考えて、実行に移すわけです。 結果として、中村さんがやったことは立派な偉業です。しかし彼自身は、偉業を成し遂げようとしていたわけではないし、ましてや後世に名を残そうなどと考えていたわけでもないはずです。本人が日々、やらなければならないこと、目の前にあることを片付けていくうちに、到達したのがそこだったということです」 世間が先にある もちろん養老さんは、若者に対して「自分に合った仕事を探すな」「とにかく周りの言うことを聞いて我慢しろ」などと言っているわけではない。心身にダメージを与えるようなブラックな職場からは逃げることも進めている。一方で、会社、あるいは社会全体に強い不満を抱えがちな人に、こんな視点を持つことも勧めている。 「何歳になっても子どものような人、成熟しない人は困ったものです。大学で働くようになってからは、そういうタイプの人への対処もしなければなりませんでした。簡単に言えば、尻ぬぐいをする必要があったのです。 こういう人の最大の問題点は、世の中を受け入れていないということです。当人たちは世の中が自分を受け入れてくれないことに不満を感じているかもしれません。 実際に、その通りなのですが、実は同時に自分もまた世の中を受け入れていないことがわかっていない。 『世間』にはさまざまな決まりがある。ゲームのルールは先に決まっているという点も理解しなければならない。ところが、世間のルールを自分が決められないことに納得できない人が一定数います。 『俺に相談なく勝手に決めやがって』 何をどう思おうが、どれだけ不満を抱こうが、自分よりも「世間」は先に存在している。この大前提は理解しておく必要があります」 自分よりも世間が先にある——この言葉の受け止め方も人それぞれだろうし、世代によってもかなり異なるのかもしれない。 養老孟司(ようろうたけし) 1937(昭和12)年、神奈川県鎌倉市生まれ。解剖学者。東京大学医学部卒。東京大学名誉教授。89年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。2003年の『バカの壁』は460万部を超えるベストセラーとなった。ほか著書に『唯脳論』『ヒトの壁』など多数。 デイリー新潮編集部