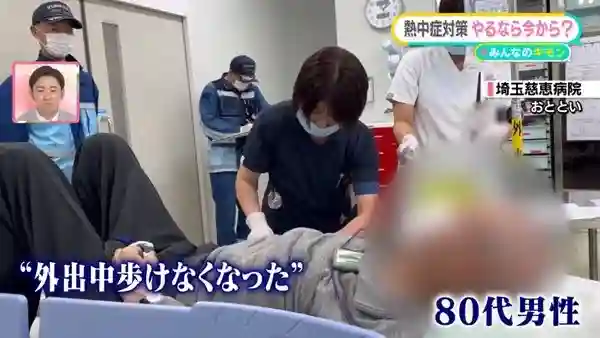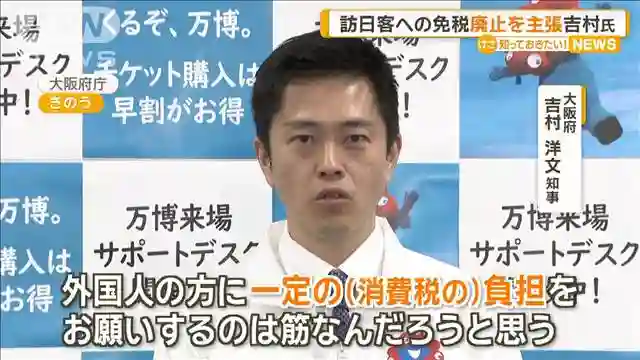フリーアナウンサー、VERYモデルとして活躍する青木裕子さん(instagram: yukoaoki_official )は、11歳と9歳の2人の男の子の母。2024年4月には、青木さんがお子さんたちと一緒に実践してきた「体験学習」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、書籍 『3歳からの子育て歳時記』 が発売されました。 子育ての正解ってある? 教育ママじゃダメ? 子どもにとって“本当にいいこと”って? などなど、青木さんが子育てをする上で日々感じているアレコレを、「子どもの教育」をテーマにしつつ徒然なるままに語っていただいている本連載。今回は連載特別編の2回目として、オンラインの読書教育サービス「ヨンデミー」代表取締役・笹沼颯太さんを、青木さんが取材。本を読む子、読まない子は何が違う? 子どもに読書好きになってもらうために、親ができることはある? そんな疑問をお聞きしました。 以下、青木さんによる寄稿です。 ●笹沼 颯太(ささぬま・そうた) 筑波大学附属駒場中・高等学校卒業後、東京大学に進学。東京大学経済学部在学中の2020年にYondemyを設立。著書に 『 東大発!1万人の子どもが変わった ハマるおうち読書 』 (ディスカヴァー・トゥエンティワン)がある。 子どもが読書にハマるオンライン習い事 「ヨンデミー」 を開発・運営し、"読書を習う"という新しい文化を創る挑戦をしている。ヨンデミーは、「読書は、一生モノの習い事」をテーマに、AIのヨンデミー先生によるサポートとゲーム感覚で楽しめるアプリの仕掛けによって子どもが読書にハマる、読書教育のオンライン習い事。 「子どもに読書好きになってほしい」 「“自分はこうだったから”という思い込みで子育てをするのはなるべくやめよう。もっと広い視野を持つことを心がけよう」そんな思いから、親である私がいろいろな方のお話を聞いて学びを得ようという連載特別企画。ありがたいことに2回目だ。今回は子どもが読書にハマるオンラインの教育サービス「ヨンデミー」代表の笹沼颯太さんにお話をうかがえることになった。 「子どもに読書好きになってほしい」というのは多くの親が抱く願いだろう。もちろん私もそう思っている。そもそも、私は幼いころから読書が好きだった。本は私の友達で、先生で、時に逃げ場だった。だから、子どもたちにも豊かな読書体験をしてほしいし、読みなさいと強制されるのではなくて、楽しいと思って読書をしてほしい。 「一番本を読んでいたのは小学生のころですね。2年生の終わりか3年生くらいに『北極のムーシカミーシカ』という本に出会って、そこからワーッと。朝学校に行ったら図書室に行って、昼休みにも図書室に行って、毎日3,4冊は読んでいました」という笹沼さんもやはり根っからの読書好きだ。読書好きは作り上げられるものではない、とつくづく思う。では、読む子は読むし、読まない子は読まない、が結論なのだろうか。 本を好きな理由は“たまたま” 「ヨンデミーを立ち上げるときに、本が好きな人達に、なんで本が好きなのかを聞いてみたら、みんな“たまたま”と答えるわけです。“たまたま”両親が本好きだったとか、“たまたま”趣味を共有できる友達がいたとか。だから、“たまたま”が起こりやすい環境を作ったら、“たまたま”が起こるんじゃないかというのが僕らのコンセプトなんです」(笹沼さん) なるほど。読む子、読まない子ではなくて、“たまたま”が起きた子、起きていない子と考えると、“たまたま”を起こすことで読書好きになる可能性はあるということか(“たまたま”言い過ぎてすみません)。 確かに自分のことを振り返ってみると、私の両親も読書好きだった。それに単行本だけではなくて、文藝春秋とか新聞とか身の回りに活字がたくさんあって、暇つぶしにそれらの難しい漢字の読み方を予想していた記憶がある。そうそう、トイレには父の詰碁(つめご=囲碁の練習問題)の本だけじゃなくて、ポケットジョークとか星新一のショートショートとかが置いてあったなあ。大きな声では言えないけれど、私もトイレでそれらを拝借したことがあった……。電車に乗れば大人は新聞か単行本を開いていたし、やることがなければ吊り広告を一生懸命読んだ。読むということが今の子どもたちに比べてずっと身近だったし、“たまたま”が起こりやすい環境だったのだろう。ここまで考えて、ハッとした。 〈私は読書好きだった→子どもにも読書好きになってほしい〉というのも、〈強制されなくても好きになった→子どもたちもいつか読書好きになるだろう〉というのも、“自分はこうだったから”という思い込みで子育てをしていることに他ならないのではないか。なるべくやめようと思っているはずなのにまたやっていたのか。 では、思い込みから解放されて改めて今の子どもたちと読書を考えたときに私たちが意識するべきことは一体どんなことだろう。 読書は子どもの武器になる 「大前提として、僕たちは全員が本を読まなきゃいけない、本を読んでさえいればいいとは思っていないんです。本を読まなくても成功している人間はいますよね。その上で、魅力的なコンテンツが増えた現代では、これまで自然と本に向かうことができていた子も向かわなくなってしまっている。本来たくさんいるはずの、本を読むことと相性がいい、読書がきっと武器になる子が、本から離れているのを回復したいという思いなんです。 実際、ヨンデミー入会時点で、本が好きという子と好きじゃない子は半々です。読み聞かせをしている日本の家庭は9割以上、週3以上の読み聞かせをしている家庭だって6割以上です。それなのに、子どもが本を読まなくなっているのは、例えばYouTubeのほうが100倍面白いからなんですよね。だから読書もYouTubeと同じかそれ以上に面白いと思ってもらいたいんです」(笹沼さん) 私は、次男が小学校中学年になって、読書が学習に与える影響というのを痛感した。読書好きな長男に比べて、あまり本を読まなかった次男は、国語では「文章題を解くスピードが遅いなあ」とか算数や社会では「問題文が理解できていないのでは」と感じることが多かったのだ。もちろん個人差があるから、その原因を読書だけに求めることはできない。でも、もしも本当は読むことができるのに読んでいなかったことで、武器が一つ減っているのなら親としては環境を整える努力をしたいと思う。 実際、笹沼さんのもとには、読書をするようになった子どもたちが「学びを楽しめるようになった」「宿題に前向きになった」「教科書が配られた日に読んでしまった」と変化したという声が届くという。読書を面白いと思って、面白いから読むようになって、それが学びにつながっていくというのは、『3歳からの子育て歳時記』でご提案している体験教育とも重なる。 「ヨンデミーがかかげているのは読書教育です。読書習慣がつくのは入り口で、読書を通じて成長を目指すのが読書教育なんです。その時に2本柱になるのが言葉と思考。ただ読むのではなく考えて読むことで、言葉と思考力を身に着けていくことにつながると考えています。そして、読書を武器にして、読書を特技にして成長していってほしいんです」(笹沼さん) ちなみに、「受験のために読書をするとはとらえてほしくないのですが……」と前置きした上で、笹沼さんがこっそり教えてくれたのだけれど、笹沼さんご自身は中学受験期も大学受験期も塾通いは非常に限定的で、読書で東大に入ったと言っても過言ではないと思っているそう。読書によって教育機会の差を超えうるとのこと。「もともとの能力が高いのでは……」とすぐに卑屈な考え方をしてしまう私だけど、でもちょっと信じて息子たちに読書を勧めてみるのも悪くないなと思う。だって、読書は楽しいことなのだから。 子どものために親ができること 最後に、笹沼さんのお話から、子どもたちの読書習慣を作るために家庭で取り組めそうなことを4点まとめてみる。 ・お家図書館をつくる 笹沼さん曰く、図書館で借りた本など新しい本が常に10冊以上家にある状態を作ることが、子どもたちと本が出会う機会を増やすことに一番効果があるそう。その際、用意した本を読む読まないにはこだわらないのが大切なんだとか。 ・本を読んでいない時間こそが読書習慣を作る つまり本を読んでいない時間にどれくらい本のことを考える機会があるかということ。身の回りに本があるということもそうだし、本について会話をすることが読書のきっかけづくりになる。読んだ本について感想を言い合うコミュニケーションも大事にしたい。 ・読書は「楽しく」「たくさん」「幅広く」。これを逆の順にしてはいけない。 まずは読書が楽しいと感じられることが第一歩。楽しくなったらたくさん読んで、たくさん読めるようになったら幅を広げる。この場合の幅は、縦と横。すなわち難易度とジャンル。楽しくないのに、たくさん読むように言っても、たくさん読んでいないのに難しい本を渡してもうまくはいかない。当たり前のようだけど、納得した。特に、親が子どもに読書を進めるときは、縦の方向、上向きの方向の幅ばかりを意識してしまうけれど、常に幅広く、そして横にも広げていくことが大切とのこと。 ・難しい本に挑戦させたいときは読みたいと思う理由を作る 本は読めるのに、幅が広がらない子は、苦労してまで読む理由がないと感じていることが多い。特に難しい本は、最初の5ページが肝。ビブリオバトル(おすすめの本を紹介し合うゲーム感覚の書評合戦)のように本を読みたいと思わせるきっかけを作ったり、冒頭に出てくる難解な語彙を予めわかるようしたりすると効果的。5ページを超えると、すっと読めることが多い。 全て完璧にはできなくても意識することはできそうだと思う。体験と同じように「やらなくちゃ」ではなくて、「一緒に楽しもう」という気持ちで取り組めたら、親子共に前向きでいられそうだ。 変化していく時代に、「自分たちの中でも葛藤がある。10年後20年後にどんな教育が良かったと思うのか、正解がないから難しい」と笹沼さんがおっしゃっていたように、子育てに絶対なんて存在しない。でも楽しいことが増えると考えたら、そしてそれが“武器”になるのなら。新しい楽しいことの中で埋もれてしまいがちな昔ながらの楽しいことを発掘してみてもいいんじゃないか。だからやっぱり私は息子たちに読書好きになってほしい。私がそうだったからじゃなくて、彼ら自身の人生のために、そんなことを強く感じた対談でした。 2児の母・青木裕子が考える…「本を読まなかった次男」が夏休みに「本好き」になった理由