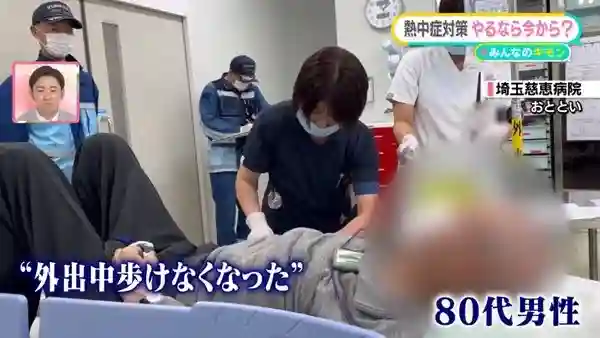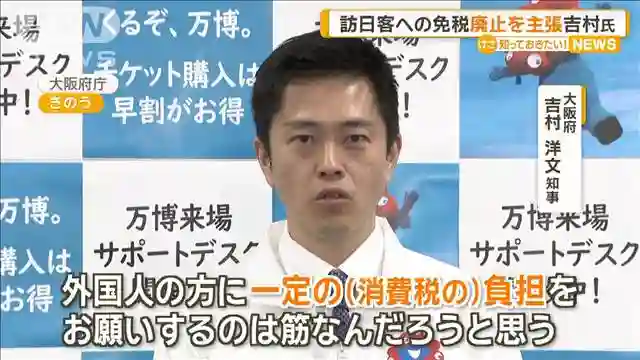作家・クリエイターとして幅広く活躍する、いとうせいこうさんの新刊『「国境なき医師団」をそれでも見に行く 戦争とバングラデシュ編』が刊行されました。 2016年以来、「国境なき医師団」とともに世界各地の困難な現場を訪ねてきた著者は、昨年6月、バングラデシュにあるロヒンギャ難民キャンプに入ります。ミャンマーの迫害を逃れた難民約100万人が暮らすメガ・キャンプで出会ったのは、貧困と感染症と暴力の連鎖、そして世界で起きている「戦争」の甚大な影響でした。 世界が絶望に覆われていく現在、いとうさんが「それでも」困難な場所を訪ねつづける理由とは? 本書の「まえがき」からお届けします。 希望なき世界で踏みとどまる それでも、とはどういうことだろうか。 『「国境なき医師団」をそれでも見に行く』とは? 今回の取材中に編集者からメールで問い合わせを受け、自分自身で連載の名前を即決しておいて、なぜ俺は今になって引っかかっているのか。晴れて原稿が本になるというのに。 俺はこれまで七ヵ国での「国境なき医師団」(Médecins Sans Frontières、略称MSF)の活動を次々と見てきた。 そのことはこれから始まる本文の冒頭にも書いてある。 そして今回見たのはバングラデシュにあるロヒンギャ難民キャンプであった。 帰国後、複雑に過ぎる事態をきちんと整理したくて、MSF東京の海外メンバーに集まってもらって問題点を再び話し合ったし、多忙な歴史学者である藤原辰史さんにも時間をいただいて、今ある世界の過酷さの根源は何か教えを乞うた。奥深い言葉が与えられた。 難民がなぜ生まれ、追われるのか、ミャンマーでもガザ地区でもそこにどんな歴史の歪みが反映されるのか。 それでも俺はいまだに混乱したままでいる。 しかし、だから俺は「それでも」と言いたかったのだろうか。「またまた」とか「もっともっと」といった軽妙なフレーズではまったく対応できない事態の奥暗さを、今回俺が感じ続けたのは確かではあるのだけれど。 MSFメンバーからよく出てくる「私たちがいなくていい世界にするために、私たちが今ここにいる」という絶妙な言葉がある。それが自分の「それでも」への疑念に関係あると気づいたのは、ずいぶん考えてからだった。 そんな言葉を掲げる彼らが実際そこにいて欲しいと望まれ続けてしまうこと、あるいはついに彼ら自身が紛争地で攻撃の対象とされている異常さは、できればその事実に目をふさぎ耳をふさぎたいほどで、俺は本当はもう耐えきれないのだ。ガザでヨルダン川西岸地区でミャンマーでウクライナで起きていることに。 だがそこにMSFが踏みとどまっている、あるいは危険の度が過ぎるがゆえに冷静にギリギリのラインまで退避してひたすら前方をにらんでいる、ないしは一歩ずつ目的地へにじり寄っている。その様子を知る度、俺は自分の目や耳をふさいでいる手のひらをほんのわずかでも動かしたくなる。 「私たちがいなくていい世界にするために、私たちが今ここにいる」というフレーズが、単に病気や怪我への対応ばかりでなく、矛盾だらけの地そのものでの誰にも譲れない存在の重要性を示しているとわかるからだ。彼らはこの希望なき世界で、信じることのできない希望のためになお“踏みとどまっている”、あるいは“退避してひたすら前方をにらんでいる”、または“一歩ずつ目的地へにじり寄っている”。 つまり、それでも彼らはいる。 彼らは挫折をもろに引き受けながら、しかしそこを去らない。次々駆けつける。それでも世界がどうすべきかを提言し続ける。 ユーモアのひとつも言ってみせながら歯を食いしばり直す彼らのあとを、俺は怯えた子犬みたいについて回り、そこで何を見たのか書く以外することがない。情けないが俺にはそれしかない。 結果、世界がまったく変わらないのだとしても、何をおそれることがあろう。 なぜなら彼らが、今この時にもそこにじっと“踏みとどまっている”、あるいは“退避してひたすら前方をにらんでいる”、または“一歩ずつ目的地へにじり寄っている”からだ。 現在、世界はきつい。 希望は日々少なくなる。 しかしそれでも、いやだからこそ「私たちが今ここにいる」必要がある。 そして俺も『「国境なき医師団」をそれでも見に行く』のだ。 いとうせいこうの「国境なき医師団」をそれでも見にいく〜戦争とバングラデシュ編(1)