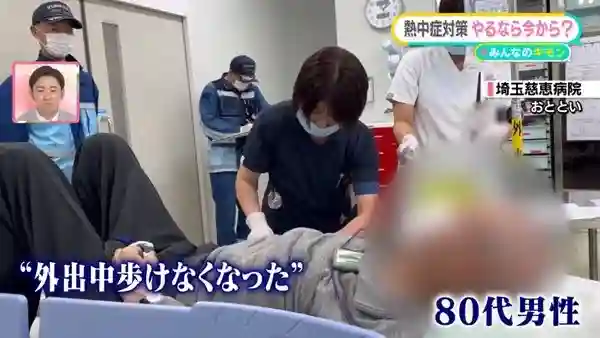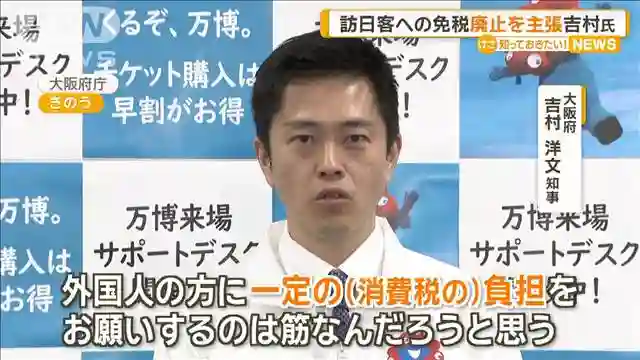「バスはどれも満員、タクシーは捕まらない京都の移動は自転車がおすすめ」。 【写真を見る】京都で大流行した「馬鹿車」 そう言うのは京都生まれ京都育ちの人気小説家・澤田瞳子さん。普段からママチャリで市内を駆け巡り、身近な歴史を拾ってつづったエッセイを『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』にまとめた。同書から京都と自転車の意外なエピソードに触れた回を一部編集してご紹介しよう。 *** わたしは常々打ち合わせ先に自転車、それもママチャリで出かけ、担当者さんに苦笑されているが、正直、これが一番確実で便利なのだ。とくに桜や紅葉の時期は観光地を経由するバスは、来る車両来る車両すべて満員で、なかなか乗せてもらえないし、タクシーは手配しても配車がいつになるか分からず、ただ待つしかないのだから。 世界中から多くの観光客が訪れる京都 京都は三方を山に囲まれた盆地。市街地から外れるとまあまあな坂が待っているが、市内中心部はほぼ平坦なため、自転車はこの地では心強い交通手段だ。通学等に自転車を使う大学生も多く、市内の駐輪場はどこもいつも満車。そのせいだろうか、ありがたいことに京都では、皇族や国賓がお泊りになる老舗ホテルですら、駐輪場が備えられている。これが最近できた外資系ホテルだとそうもいかず、事前に「駐輪場はありますか?」と問い合わせてから打ち合わせに出る。カバンには常にレインコートが入っているので、雨の日だって安心だ。 11月のある日曜日、観光地真っただ中の寺で、わが親類の三十三回忌法要が営まれた。法要自体は構わない。問題は参列者に子供や高齢者が多いため、タクシーを何台も手配せねばならぬことだ。 盆地の京都は、市内中心部はほぼ平坦 「日程といい場所といい、なかなかタクシーは来てくれないと思うよ。せめて私たちだけでも、自転車で行くのはどうかな?」 手配すべき車が一台でも減れば、その分、他の人は動きやすくなる。そんな思いから提案したわたしに家族は、「喪服で自転車!?」と目を丸くしたが、背に腹は代えられない。普段着で自転車移動し、寺で礼服に着替えさせてもらうことで話はまとまった。 「京都で流行した自転車(またの名を馬鹿車)」 自転車は幕末、慶応年間頃に日本に初めて輸入されたと言われているが、正確な時期は意外にも分かっていない。明治3〜4年に描かれた錦絵には自転車が描かれているものが複数あるので、すでにこの頃、東京を中心とした都心部では普及が始まっていたらしい。では京都ではどうかといえば、明治18年(1885)には、「府内で自転車が流行しすぎた結果、通行人に怪我をさせる例が頻発しており、また学生は自転車に夢中になって学業を疎(おろそ)かにする。このため(京都市の前身である)上京・下京の両区では自転車を禁止する」という布告が出ている。こういった自転車禁止令は、それ以前にも大阪府や群馬県などでも発布されているが、学生にわざわざ言及している点は、早くから学校の多い京都らしくて面白い。 一説には外国から高級自転車を取り寄せた日本初の人物といわれる樺山愛輔(かばやまあいすけ)。自転車を使わない時は床の間に飾っていたという (出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」〈https://www.ndl.go.jp/portrait/〉) ちなみに当時、自転車は「馬鹿車」とも呼ばれていたそうで、この布告が出た直後には、「京都で流行した自転車(またの名を馬鹿車)が最近、隣の大津の市街でも流行り出した」という新聞記事もある。馬鹿車とは何ともひどい表現だが、例えば馬車や人力車、はたまた駕籠などは誰かが頑張って乗り手を運んでくれるのに対し、自転車は乗り手自らがせっせと漕がないと動かない。路面が舗装されていたわけでもなく、また自転車そのものの性能とてまだまだ低かった時代。そんな苦労をせねばならぬ乗り物を侮(あなど)って生まれたのが、この言葉というわけだ。 【「京都らしさ」の向こうにある、知られざる歴史を探る】千年の都にして日本最古の観光地・京都には、平安や幕末のみならず、あらゆる時代の痕跡が息づいている。この地に暮らし、日々、自転車で街中を巡り身近な歴史の痕跡を考察してきた直木賞作家が、季節の便りや日常のニュースから思いも寄らぬ史話を掘り起こし、紡ぐ50のエッセイ。京都の解像度が上がる知的興奮の一冊 『京都の歩き方─歴史小説家50の視点─』澤田瞳子/著 もっともこの異名は自転車が便利なものと受け入れられるのに従って消えて行き、明治後期にはほとんど使われなくなる。目新しい道具に対する人々の態度を反映した、瞬間的な流行語だったようだ。 ところでそんな「馬鹿車」の言葉が忘れ去られつつあった明治27年(1894)1月の「時事新報」は、子爵・樺山資紀(かばやますけのり)の長男である愛輔(あいすけ)が、東京から京都まで東海道自転車旅に出たことを報じている。後に伯爵となる愛輔は当時、数え30歳。14歳で日本を離れて欧米諸国で学問を修め、3年前に帰国したばかりの御曹司だ。当時、欧州では自転車旅行が流行っており、この翌年には後に放射線の研究によってノーベル物理学賞・化学賞を受賞したマリ・キュリーが、夫であるピエールと自転車でフランス田園地帯を巡る新婚旅行に出ている。愛輔の自転車旅は、いわば時代の最先端の旅行だった。 その後、貴族院議員として要職を歴任した樺山愛輔は、一説には外国から高級自転車を取り寄せた日本初の人物。イギリスから個人輸入したそれを、使わない時は床の間に飾っていたのが、知人の間では話題になったという。近年はスポーツ自転車の流行に伴い、盗難防止やサビつき防止、インテリアの一環として自転車を室内に置く人も多い。つまり愛輔は、そんな自転車愛好者のはしりと言ってもよかろう。 欧米の文化のみならず、日本の古くからの文物をも深く愛した彼の娘の一人が、後に日本の美にまつわる随想を多く残した白洲正子。彼女は昭和4年(1929)、兄の友人であった実業家・白洲次郎と結婚するが、その結婚式は京都ホテル——現在のホテルオークラ京都で挙げられた。 正子が父の死後に語ったところによれば、愛輔は慎重と呑気が入り混じった気性で、周囲を心配させることも多かった。正子の結婚式の折には、式が始まる夕方までは時間があるから遊びに行こうと言い出し、新郎新婦を誘って車で宇治へと出かけた。そうこうするうち、三人ともすっかり式のことを忘れてしまい、気が付いたのは夕方になってから。彼らが戻って来るまで、親類たちはホテルでやきもきしていたというから、呑気は正子も次郎も似たようなものだ。 ちなみにこのホテルオークラ京都は、私が知る限り、市内老舗ホテルの中でももっとも立派な駐輪場がある。もしやそれは自転車を愛した樺山愛輔の影響では——とは、さすがに勘繰りすぎだろうか。 ※本記事は、澤田瞳子『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』(新潮選書)を再編集したものです。 デイリー新潮編集部