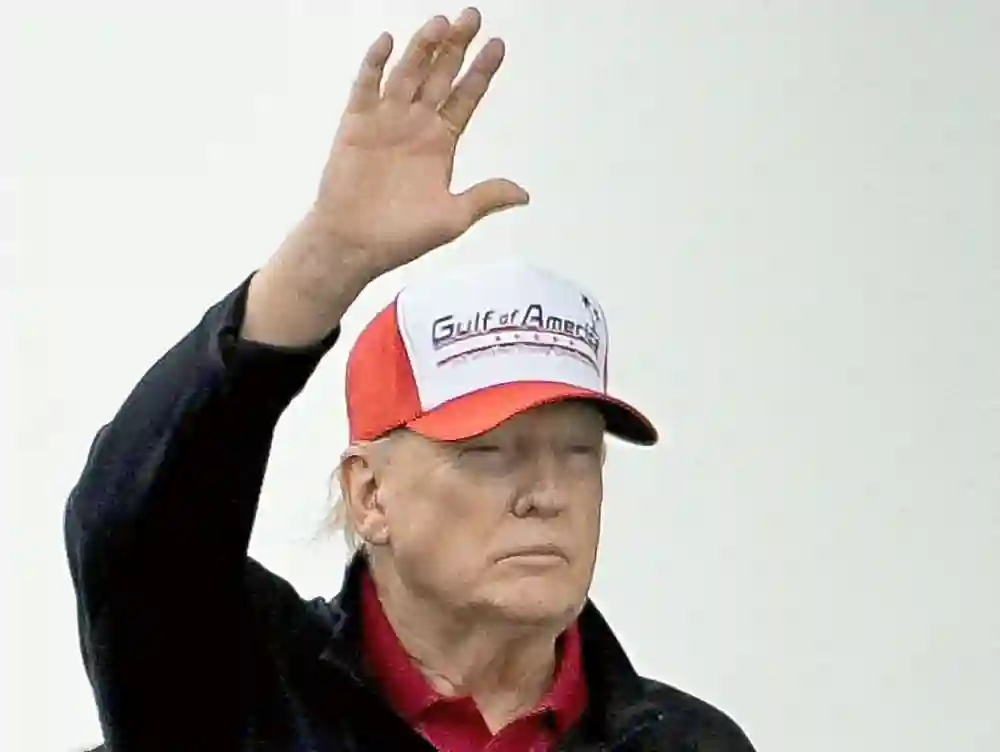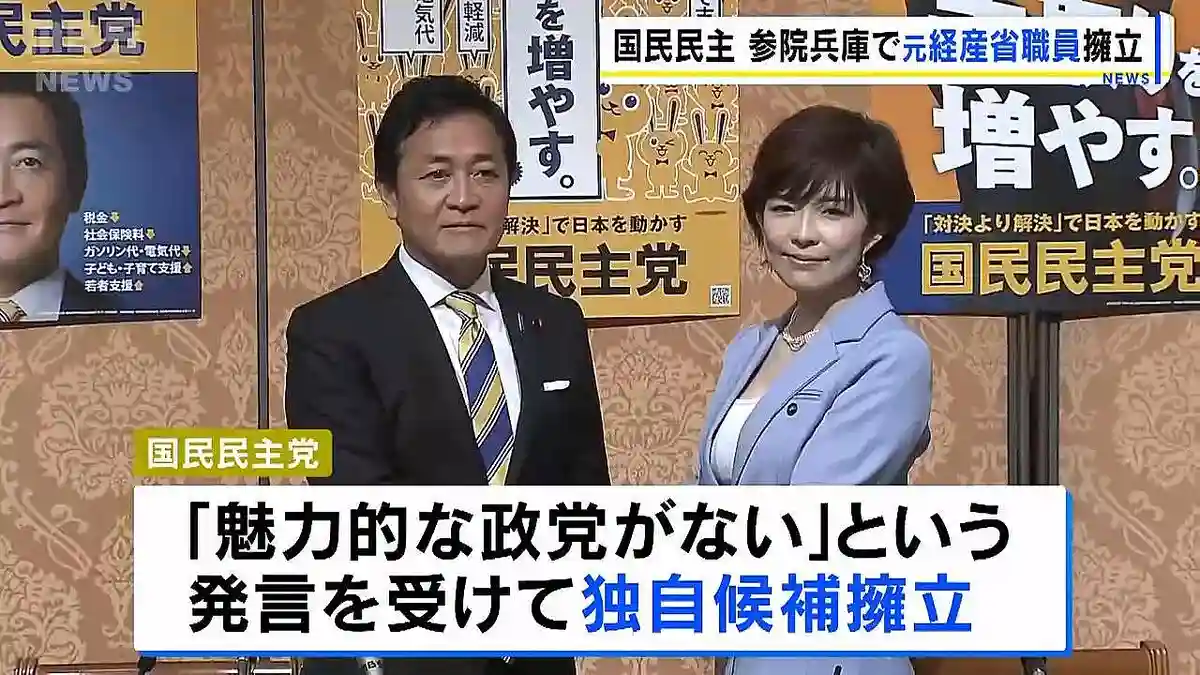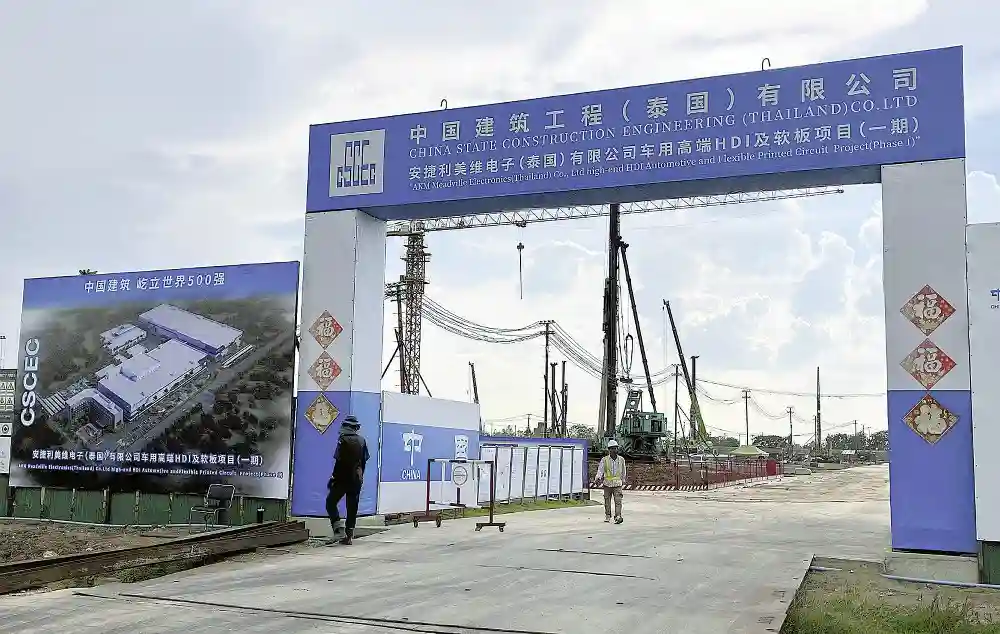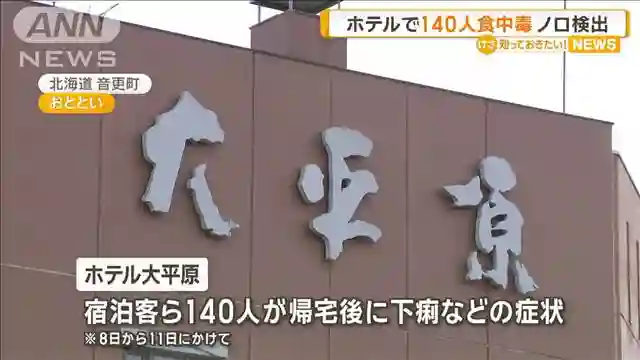社会人なら絶対身に着けたい一生モノの力が、「顧客が何を望んでいるかを知る力」です。どうすればその力をつけられるのでしょうか。 ロングランのアトラクションを数多く手がけてきた松本公一さんが初の著書『なぜ、ゲストはリピートするのか? テーマパークのプロの感動をつくり出す仕事』で、すべて明らかにしています。 40歳でテーマパーク業界に飛び込み、小さな会社を率いて大手の競合相手を圧倒できた秘策や、失敗でつかんだこと、さらにアメリカのディズニーランドのレジェンドたちと働くなかで得た重要なアドバイスもこの連載で伝えます。 エレクトリカルパレードの演出家が見せたこだわり つくり手の「こだわり」により、悪条件が逆に強みになった好例を紹介しましょう。 クライアントの松竹から、大船撮影所の敷地内で計画中のテーマパーク「鎌倉シネマワールド」向けに、ハリウッドをイメージしたアトラクションづくりを依頼されたときのことです。1994年、テーマパークの計画自体はすでに進んでいました。アトラクションが足りないということで、私のところにも話があったのです。 ただ依頼されたのは特殊な場所で、天井だけが吹き抜けで高い、狭いスペースでした。それでもクライアントは、ある程度の人数のゲストが入れるアトラクションにしてほしいと言います。 エグゼクティブ・プロデューサーだった私は、どうしようかと頭を悩ませ、「思い切って立ち見にしよう。この条件下で考えられるのは、高い空間を使った空中ショーしかない」と考えました。 それでイメージしたのが、東京ディズニーランドの「魅惑のチキルーム」です。鳥や花などのロボットが音楽に合わせて歌い踊るショー形式のアトラクションで、現在は「魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ“アロハ・エ・コモ・マイ!”」として、アニメ映画『リロ&スティッチ』のキャラクターたちも登場するショーになっています。私自身、初めて「魅惑のチキルーム」という空中ショーを見たときには、すっかり引き込まれました。 「魅惑のチキルーム」は、360度全方位で勝負をしていますが、この鎌倉のアトラクションでは上だけを見せるようにし、音楽に乗せてロボットのスター歌手たちが歌う形にしよう、と考えました。 ただ、具体的にどう演出に落とし込むかということになると、なかなか難しい。そこで演出デザインには、ディズニーランドの初期のエレクトリカルパレードの演出を手掛けた、アメリカ人の演出家ロン・ミジカー氏を起用することにしました。 「こだわり」が見事なアトラクションを創り出した 彼は「魅惑のチキルーム」を超えるアトラクションをつくろうと意気込んでくれ、鳥を往年の歌手やハリウッドスターに見立てた空中ショーを考え、それをイメージイラストで示してくれました。 マリリン・モンロー、フランク・シナトラ、エルビス・プレスリー、チャック・ベリーなど、そうそうたるスターを鳥の姿で登場させ、当時の大人世代の誰もが知る大ヒット曲を歌わせるという案です。「ハリウッドをイメージしたアトラクション」というこちらの依頼にまさにぴったりの素晴らしいものですが、版権や肖像権が心配でした。しかし、彼は「歌手名を出さずに鳥としてつくるので問題ない」と言います。 JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)経由で、使用料を払えば音楽自体は使えますが、スターの名前や顔にはまた別の権利関係があって、アトラクションに登場させることはできません。 そこで鳥のロボットをスターに見立て、名前はつけないものの、フランク・シナトラ風に帽子をかぶらせる、マリリン・モンロー風にブロンドでセミロングの髪型、頬にはほくろをつける、などとしてスターのイメージを表現しました。メロディーが流れると同時にスターのいでたちをした歌手(鳥のロボット)が、歌いながらゴンドラに乗って降りてきます。こうして、ゲストの目は頭上に釘づけになるのです。 ここでロンさんは、スターの名前がまったく使えないのも寂しい、何とかエルビスだけは名前を使用できないかといって、エルビス財団と交渉しました。その結果、一定の許諾料を払うことでリーゼントヘアの鳥ロボットの横に「ELVIS」という大きなロゴサインを使用する許可をとることができました。 このあたりの彼のこだわりは素晴らしく、結果的に見事なアトラクションとなり、「ロビンのハリウッドスタジオ」と名づけられました。私もいい出来だと満足しましたし、伝統ある映画会社のクライアントから「いいものをつくってくれましたね」と言われたときは、嬉しかったものです。 そしてアトラクションは翌年、ロサンゼルスで開催されるテーマパークの優秀作品授与式で外国部門の優秀作品賞(全米エンターテインメント協会主催)に選ばれました。そのときのトロフィーは今も、ドリームスタジオに飾ってあります。 日本人のノリを見誤った! ただ一点失敗したのは、「ゲストにも踊ってもらおうよ」という話がロンさんから出たときのこと。「それいいね、クラブみたいに踊ってもらおう」と私も賛同したものの、結果的にはうまくいきませんでした。 誘導スタッフがリード役として一緒に踊り、「みんなも一緒に」と勧めます。みんな踊ってくれるだろうと、私は勝手に頭の中で思い込んでいましたが、ゲストは全然踊りません。日本人にはこのノリは難しいんだなと思い知りました。クラブという場まで行けば、踊るのが目的で行っているからみんなガンガン踊ります。でも普通にテーマパークに来たゲストにはハードルが高かったのです。結局、ゲストに踊ってもらうのは途中でやめ、鑑賞に専念してもらうこととしました。 ショーに対する反応が、アメリカと日本ではまったく違います。アメリカ人はノリがよく、ワーッと途中参加してでも踊り出します。ロンさんはアメリカ人をイメージして提案していて、それにうっかり乗ってしまった私のミスでした。 拍手に関しても、アメリカ人は自分が「いい」と思ったらその場で率先して拍手をします。日本人は、感激したりしても見ているだけ。そして静かに「面白いね」「きれいだね」などとつぶやく。その違いが大きいのです。 プロの小集団がつくり出した最高傑作 同じ鎌倉シネマワールドで、もうひとつうまくいったアトラクションがありました。「シネマ・ザ・ドリーム」といって、これはいわば「間隙を縫った」アトラクションでした。 昔アメリカのハリウッド映画には、予告編に著作権がかかっていない時期がありました。そうした予告編映像をコレクションしていた人がアメリカにいて、その現物を譲るというのです。それを使えば、莫大な使用料を払わなくてもいいということで、この予告編映像を使ったアトラクションをつくることにしたのです。 ポイントは、2次元の映画の予告編を、3次元に見せる工夫をしたことです。 「シネマ・ザ・ドリーム」の幕が開くと、ステージに夜のニューヨークの街並みが現れます。この街並みは、建物の形にカットされた複数の板に、遠近法で建物の大きさを変えて絵を描き、前後に並べて立てて立体感を出したものです。 建物の窓のひとつに、『007』のジェームズ・ボンドの映像が映し出され、銃撃の音が聞こえてきます。すると建物に、銃弾に打ち抜かれた穴が開きます。これは建物の板に暗いうちは見えない小さな穴をはじめから開けておき、銃撃とともに穴の後ろのライトが点灯すると、壁に穴が開いたように見える仕掛けになっています。 次に一転して静かになり、『ウエスト・サイド物語』の映像が別の窓に映し出されます。ニューヨークの裏町で、窓辺で恋人を想い歌う主人公マリアと、下から呼びかける恋人トニーの姿が、ライトに照らされ登場します。現代版「ロミオとジュリエット」を思い起こさせ、ふたりの愛が観客にまで伝わる名シーンです。 そこからは一転して、中央の建物の壁に数々の名作の映像が、その映画音楽とともに流れます。『駅馬車』『アラビアのロレンス』『エデンの東』など、全盛期のハリウッドらしいダイナミックな映像です。 クライマックスでは大きく場面が転換し、『風と共に去りぬ』の名場面が流れます。主人公のスカーレット・オハラとレット・バトラーの愛の葛藤、南北戦争でアトランタの街が燃え盛るシーン……。そして最後はスカーレットが生き抜く決意を固めるシーンで、劇場型アトラクションは終わります。 この「シネマ・ザ・ドリーム」という作品は、私が指揮したアトラクションの中で最高傑作だと思っています。 プロを本気にさせたきっかけとは? なぜ最高傑作ができたのか?それは、信頼できるプロの小集団のおかげでした。 制作を手掛けてくれたのは、ほぼすべて、外部の一人親方の会社とフリーランスの人たちでした。彼らに、「今回は、どこにもない画期的な映像アトラクションをつくりたい」と演出内容について熱を持って伝えると、「ならばこうしたらどうか?」と、遠慮なくアイデアや意見が出てくるようになりました。彼らも頼まれるだけでなく、自ら「面白いものをつくり上げよう」という気持ちになってくれたのです。 このときチームメンバーと彼らとの間に一体感が生まれ、「この方法では、動きが遅すぎて迫力が出ないのでは?」などと、場面、場面で熱のこもった話し合いが行われるようになりました。 アトラクションで最大の場面転換を行うシーンでは、ステージ上のニューヨークの建物群をじゃばら状に前に折り畳み、その後ろから大きなスクリーンを登場させて、クライマックスの『風と共に去りぬ』の映像シーンを映し出すこととしました。 ニューヨークの建物群全体を前に畳むためには、鉄骨で組み上げた可動式の骨組と、それを動かす駆動装置が必要でした。これはある一人親方が、設計から制作まで手掛けてくれました。 プロの存在の大切さ もっとも悩んだのは、どうやってステージいっぱいに大きなスクリーンを登場させるかです。上から降りてくる方式では、ありきたりすぎて意外性がない。私は「スクリーンを、床下から上に吊りあげられないか?」と思いましたが、長年「動くメカ」を手掛けてきた人から、「松本さん、それは無理。均等に上に引き上げるのは難しく、のちのちトラブルのもととなる」とダメ出しがありました。 最終的に彼の意見で、床と天井にレールを敷き、それに沿って後方からスクリーンが登場する方式としました。これならスクリーンの上と下が均等に動くのでトラブルが起きにくいのです。スクリーンの動きも面白く、採用しました。 もっとゲストに驚きを与えられないかと考え、『風と共に去りぬ』でアトランタの街が燃え上がる映像シーンでは、スクリーンの両サイドから疑似火を焚きました。赤く薄い布を、風であおりながら赤い照明で照らすことで、炎のように見せるのです。スクリーンをその炎で取り巻くことで、大きな炎が燃え上がるシーンをつくることができました。このシーンはなかなかの迫力で、ゲストは大いに喜んでくれました。 余談ですが、パーク開業のお披露目のときには、松竹の社長が並み居る女優陣を連れて真っ先にこのアトラクションの催し場に行き、「自分はこのアトラクションがいちばん気に入っている」と言ってくれたのを覚えています。 この仕事を通じて感じたのは、前例のないことで、いいものをつくるために「できるものはできる」「ダメなものはダメ」と言い切れるプロの存在の大切さです。組織としてではなく、自分でリスクをとって意見を明確に言い、ときに「こうしたらどうか?」と提案をしてくれる小集団・個人は本当に貴重だと実感しました。 よりよいものをつくり上げようとするとき、自分たちだけで何とかしようとして中途半端な「器用貧乏」になるのではなく、ときには信頼できる外部のクリエイターを起用し、頼ることも大事なのです。 顧客を感動させるにはどうしたらいいか?アトラクションのプロがやっている4つの「こだわり」