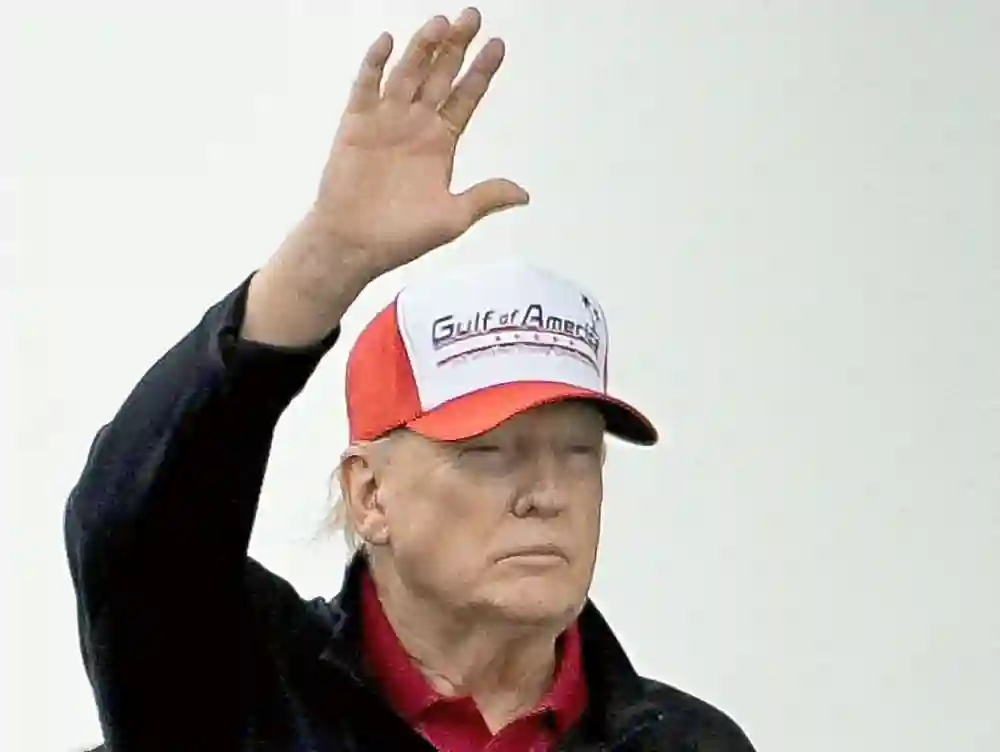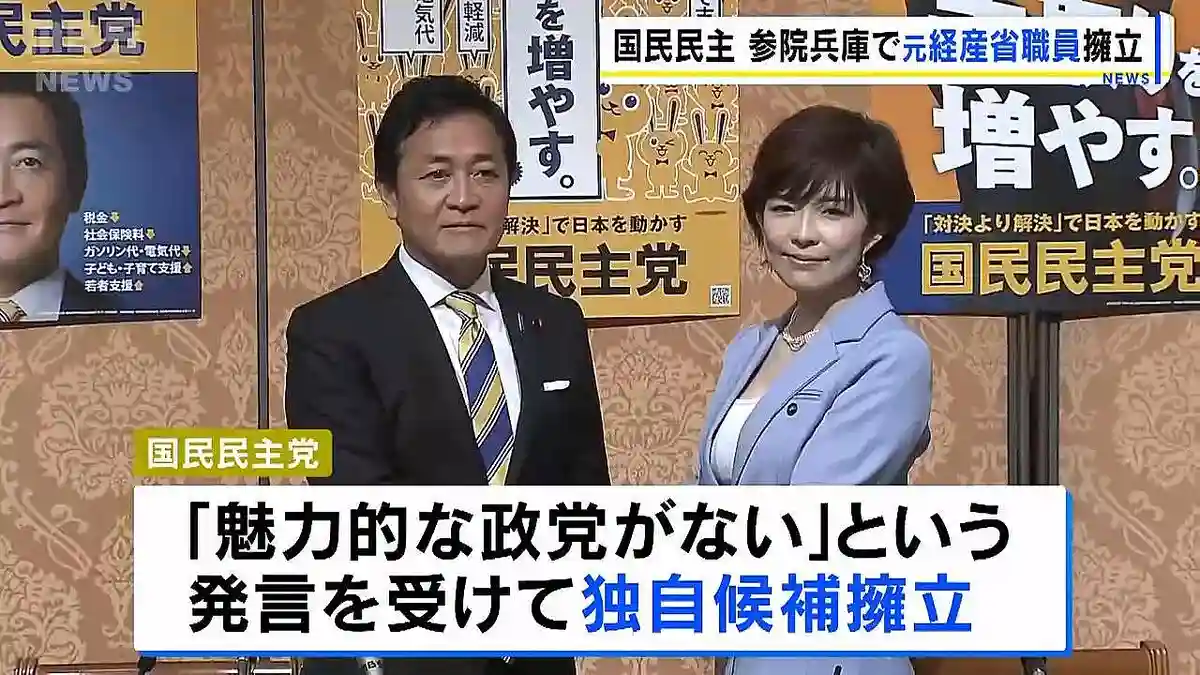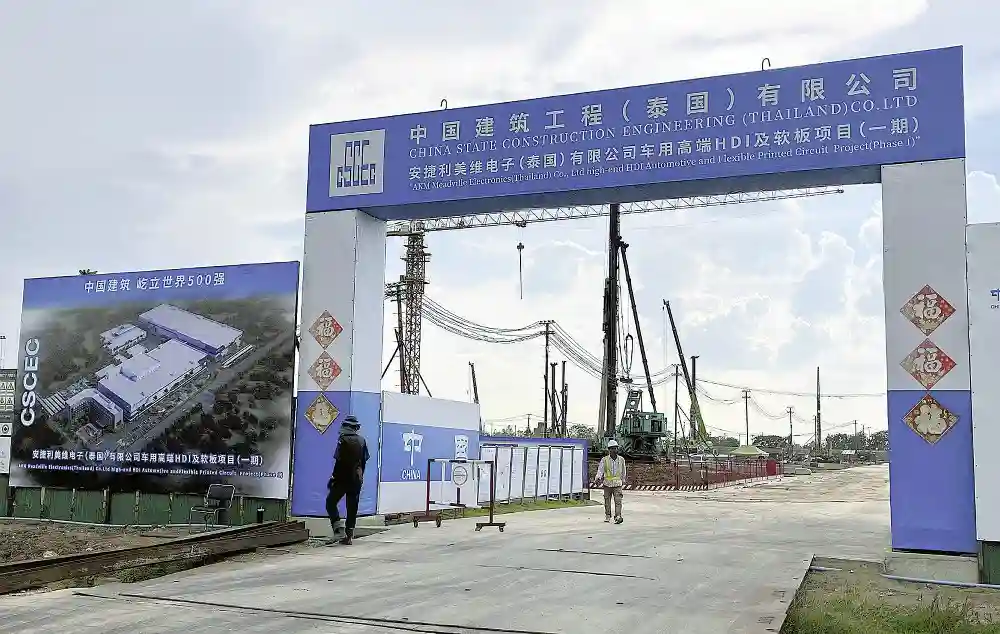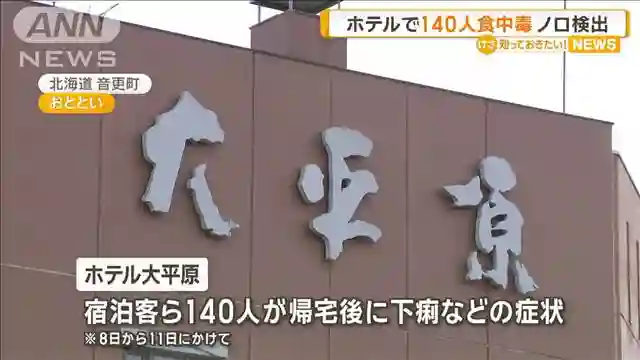大切な人を亡くしたとき、私たちはどうやってそのことを受け止めたらよいのでしょうか。「死に向き合う」という普遍的な事柄を、父の死という個人的な体験から書き綴ったエッセイ『星になっても』が4月23日に発売されます。刊行を記念して、本書の最後に収められている一編「訃報を待つ」をお届けします。 訃報を待つ 入院が決まってからちょうど1年間、父は骨髄異形成症候群という難病と闘い、2023年2月7日10時56分、70歳の誕生日に死んだ。最期は急性骨髄性白血病への移行が認められた。私は自宅のある豊橋で父の訃報を母から伝えられ、やり場のない思いを札幌の病院のベッドで横たわっているであろう父の亡骸に馳せたのである。 だから、私は1年間、父の訃報を待っていたことになる。しかし、人間は必ず死ぬのだから、よく考えてみれば、私は父の死を36年間待っていた、とも言えるのかもしれない。それでも、健康診断で貧血の診断を受け、精密検査をして先の病気が判明してからの1年間は、父にとっても私にとっても、母にとっても弟にとっても、死を待つ特別な1年間だったはずである。端的に言えば、辛い1年だった。 1歳と3歳の息子を連れて豊橋から札幌に行くのは、それなりの準備と覚悟を要したが、妻は愚痴もこぼさずすべての準備を整えてくれた。長男は豊橋駅に向かう途中のタクシーで、いつか自分も死んでしまうのか、と、私と妻に訊ねた。不安そうな顔をして、自分は死にたくない、とも言った。札幌の月寒の葬儀場には大人数が寝泊まりするための広い畳の部屋があり、そこで次男は地道にトレーニングを重ね、葬儀が終わる頃には歩けるようになった。 死にゆく父の傍らで、2人の兄弟は精神的にも肉体的にも成長していく。その光景を見て、私は、息子の父としてうれしくもあり、父の息子としてかなしくもあった。何となく、生と死の間に挟まれたような、そんな気分だった。いつ来るかも分からない父の訃報を待ちながら、私は、半分大人で、半分子どもで、誰もが青年期に感じる居場所のなさに似た感覚を久しぶりに味わったのである。 待つとはどういう体験なのだろうか。ベルクソンは、砂糖水をつくりたいなら、砂糖が溶けるのを待たなければならない、と書いていたが、ここに表現されているのは、砂糖水をつくりたいという欲望が待つという内的な時間性をつくりだす、ということである。しかし、父の訃報を待っていて気づいたのだが、むしろ人は何かを待つことによってそれを求め始めることもある。 一方では、父の死をできるだけ先延ばしにしたかったが、他方では、父の死を待つことで、その到来をどこかで待ち望んでいる自分を見つけてしまうのである。この不謹慎な事実をうまく処理することができず、私は人間の心の機制に戸惑った。時々、自分が何を待っているのかが分からなくなった。 「待つ」という特殊な時間性 数年前、私の恩師がサミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』に言及していたのをきっかけに、久しぶりに文学を読んでみた。が、この本のどこに人間の不条理があるのかを理解できない。もっと正直に言えば、どう読んでいいのかすらも分からずじまい。意味不明の最高傑作である。 しかし、その時に分からなかったことで、少し分かるようになったことがある。それは、待つというのは一種のBGMみたいなもので、待つことそのものを体験し続けるには限界がある、ということである。たとえば私の場合、日清カップヌードルにお湯を入れて出来上がるまでの時間くらいであれば、待つことそのものに集中することもできるかもしれないが、日清どん兵衛になったら無理な気がする。3分と5分。たった2分の違いだが、待つことそのものを持続させるのは案外楽ではないのだ。 以前『ゴドーを待ちながら』を読んだ時には、どうしてもゴドーが何者なのか、それが何のメタファーなのかが気になってしまったが、じつはあの物語は、その名の通り、待つことを書いているのであって、それは演劇上の1つの「設定」なのだという当たり前の事実に、ようやく思い至ったのである。待つということは、まさに何かを待ち始めてからその到来までの時間意識を間延びさせる設定にほかならない。その特殊な時間性の中で私たちは、他のさまざまなことに興じるのである。 いまかいまかと父の死を待つ時間性の中で、私は食事し、おしゃべりし、研究し、バラエティー番組を見、家族と寝る。しかし、何をしていてもそこに流れているBGMは不穏なリリシズムを失わず、私の1年間の気分に影を落としている。それがこの1年の舞台設定なのである。それが訃報を待つということなのである。 葬儀の朝、父が病室で使用していたという電気剃刀を使って髭を剃った。後半は自力で動くこともままならなかった父の顔が、湯灌の儀式の際に綺麗だったのは、死ぬ前に何とか自分で髭を剃ったからである。 私は近視なので、剃刀を使うときにはまず、顔を洗って全体を適当に剃り上げた後、眼鏡をかけて鏡の近くで残った髭を剃るのが習慣になっている。葬儀の朝、眼鏡をかけて鏡を見たら、自分の顔が真っ黒である。顔を洗うこともできなかった父の皮脂や汚れが剃刀にそのまま残っていたのだ。これが父の苦しみなのだと思った。でも、これが父が最期まで頑張って生きた証なのだと思った。 現在、四十九日の法要のために、札幌に帰省している。そういえば、父は坊主が嫌いだった。線香の匂いも嫌いだった。好きでもない坊主に供養されながら、父はきっとそっぽ向いて寝ていることだろう。もしかしたら、悪態をついているかもしれない。しょうがないよな、そういうもんだから。 待つことを終えて、私はかなしいだけ。自宅に戻る頃には、豊橋公園の桜は散り始めているだろう。豊橋は風が強い街だから。一番の読者だった父がこの文章を読むことはもうない。 「父親の死」という個人的な体験について書いてきた哲学者が、読者に伝えたい「当たり前の事実」