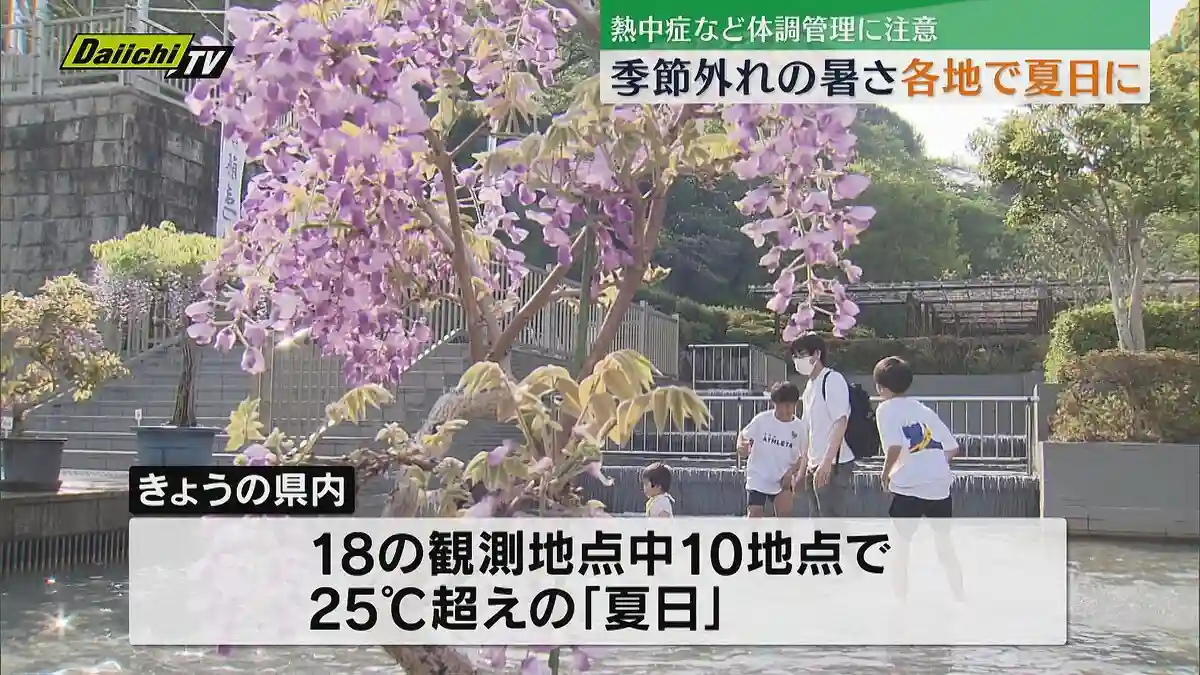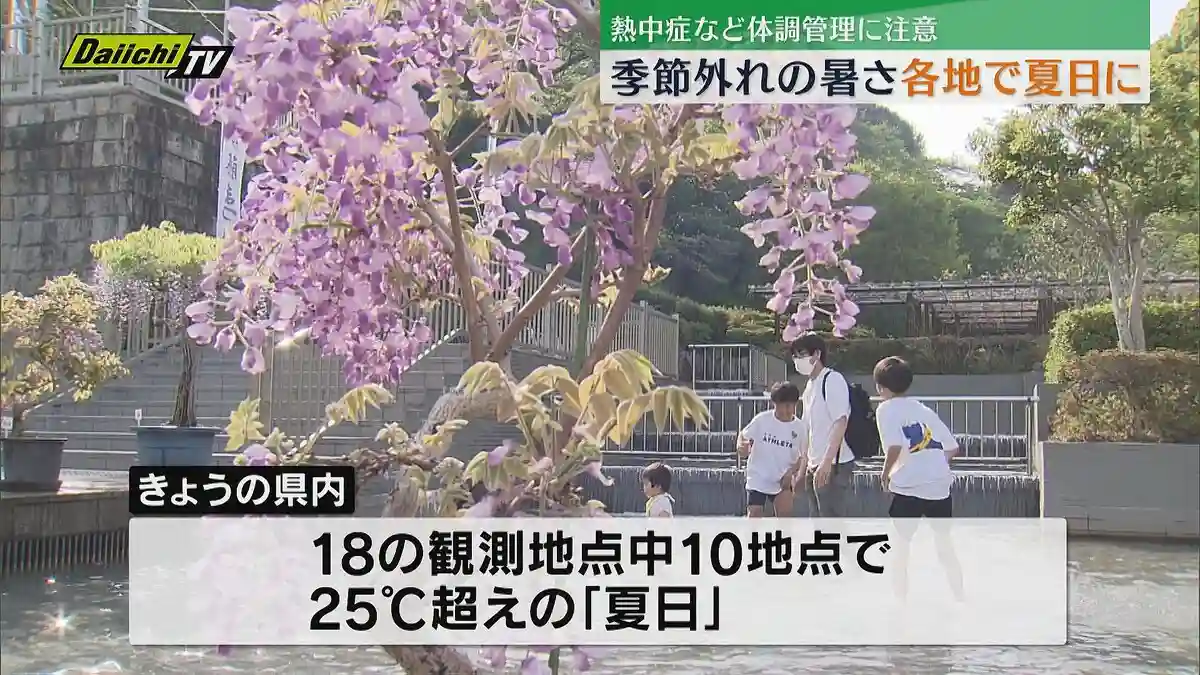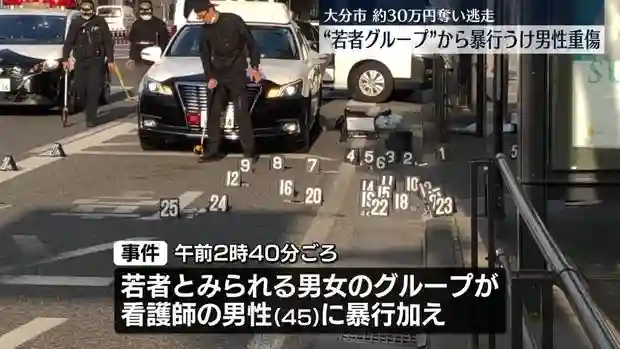ある一人の看護師「千里(ちさと)さん」が奮闘する日々を追いかけ、ナースのリアルを伝える『看護師の正体』(中公新書ラクレ)が売れている。 患者を前に、彼女たちはいったい何を考えているのか? “白衣の天使”たちのセクハラと恋愛事情とは? 医師にイライラするのは、どんなときなのか? 千葉大医学部から転身してクリニックを開業した外科医の松永正訓氏が迫った、「看護師の本音」とは——。 異例のスタイルで始まったVIPの手術 レーゲルとはドイツ語。英語ならルールだ。手術でいうレーゲルとは手順のことである。たとえば胃を切除するとき。患者のお腹を開けてから、どういう順序でやろうかと考えながら手術したら、手術時間がどんどん延びる。素早く、無駄なく、出血なく、手術を終わらせるためにレーゲルは存在している。 最初にこうする、次にこうする、その次はという決まり事がレーゲルである。6時間くらいかかる胃全摘手術でもすべての順序を覚え、レーゲルに沿ってどんどん手術を進めることが外科医には求められる。そしてそれは当然、器械出しの看護師にも求められる。 さらにがんの手術は再建だけでは終わらない。進行症例ではリンパ節郭清が必要になる。胃の周囲のリンパ節を脂肪と一緒に摘出していく。これを郭清という。リンパ節郭清には、はっきりしたレーゲルはない。患者のがんの広がり方によって臨機応変に決めていく。 電気メスで焼くところは焼き、出血しそうな血管は確実に縛ってから切る。千里は新病院のオペ室に来て5年目には、胃切除のレーゲルを完全に覚えていた。そしてリンパ節郭清になっても、術野を見ながらどの器械を出すか、外科医に言われなくても判断できるようになっていた。 外科の部長と副部長が一緒に手術することはない。だが、千里が手術室6年目のとき、市政のVIPが胃がんで入院してきた。こういうとき外科の世界では、いつもどおりのメンバーで手術した方がうまくいくとよく言われる。慣れているからだ。 しかし、このときは部長の判断で、部長が執刀、副部長が前立ちという異例のスタイルで手術することになった。 オペ室の師長はその話を聞いて「えー!」と困った顔になった。外科が最高のメンツで手術に挑むならば、オペ室ナースもエースを出さなければならない。その結果、器械出しは千里、外回りは千里の一番弟子である加奈子が務めることになった。麻酔をかけるのは麻酔科部長である。 部長先生が、患者のみぞおちから臍の下までメスを走らせて手術が始まった。通常なら、「コッヘル!」「コッヘル!」と声が飛ぶ場面である。だが、部長先生も副部長先生も、無言で千里に向かって手を伸ばす。千里は二人の手の中にビシッとコッヘルを入れた。 沈黙を破ったやりとり いつもはJ−POPの音楽が流れる外科の手術室であるが、この日は音楽はなし。部長先生も副部長先生も千里も、レーゲルにしたがって静かに手術を進める。先生たちは器械の名前を一切言わない。その緊張感に加奈子はハラハラした。 次々に器械を出す千里。手術が始まって3時間くらい経ったとき、副部長先生が沈黙を破って、千里に言った。 「レーゲルでは、ここはまだ袴(はかま)ではありません」 袴とは腸を包む布。腸を切ると中身が漏れるので、袴を巻いて清潔を保つのだ。手術がピタリと止まった。 「いえ、ここは袴です」 千里は優しい声で返した。 「いや、袴じゃありません」 副部長先生も譲らない。水を打ったように静まり返った。 「いえ、袴です」 そう言って、千里は部長先生の顔を見た。 「そうだね。ここで袴だね」 部長がそう言うと、副部長は少し首を傾げて「そうでしたっけ」と言いながら、袴を受け取った。 リンパ節郭清もスムーズに進んだ。電気メスで焼いて、糸で縛って、次々にリンパ節のかたまりをきれいにしていく。6時間を過ぎたところで閉腹に入り、手術は終わった。最後まで、二人の外科医は器械の名前を一度も言わなかった。千里は一回も器械を間違えなかった。 まさかの「判断停止」状態 翌年の春、外科には新しい医師が3人研修に来た。7年目の中堅医師と、3年目の若手と、2年目の研修医だ。 その研修医はみんなから竜一先生と呼ばれて可愛がられていた。まじめで素直なところがナースたちには好評だったのだ。からかうと、はにかんで俯いてしまうのも人気の理由だった。 春から夏にかけて、竜一先生は胃がんの手術や腹腔鏡を使った胆嚢摘出術の助手を務めていた。そして鼠径ヘルニアや腹膜炎を伴った急性虫垂炎などの比較的やさしい手術は執刀を任された。助手を務めるということは、間近で手術を見てやり方を覚えるということだ。しっかり覚えれば、次には執刀の機会が回ってくる。 千里も竜一先生をいい外科医だと思った。外科医としては、まだ2年目ということを差し引いても、バリバリと進むような胆力がちょっとない感じがする。だけど、手術前によく勉強してくることはすぐに分かった。手術が終わって患者が麻酔から覚めるまでの時間も、竜一先生は副部長先生によく手術について質問していた。 (もうちょっと自信を持てばいいのに。でもこの先生は伸びる) 千里は、竜一先生のちょっと不器用で、でも真摯な姿を見て心の中でそうつぶやいた。 年末になって竜一先生は胆嚢摘出の手術をやらせてもらった。一歩前進である。そして年が明けると、胃がんの部分切除術の執刀医が回ってきた。一年間の集大成である。その患者の胃がんはおそらく早期だろうとの診断で、リンパ節郭清は行わない予定だった。 竜一先生が執刀、副部長先生が前立ち。そして千里は器械出しに当たっていた。 手術が始まる。皮切と共に、 「コッヘル!」 「こっちもコッヘル!」 と声が飛ぶ。千里は二人の手の中にコッヘルを入れると、次に電気メスを渡した。そして開腹した瞬間、副部長先生が「あ!」と声を上げた。千里にもすぐに分かった。胃の周囲のリンパ節が累々と腫れていたのである。進行症例だった。 竜一先生は、右手を千里に伸ばした。だがその手は、上を向いているのか下を向いているのかはっきりしない、中途半端な手の出し方である。どの器械がほしいのか、その手には意志がなかった。千里は、竜一先生の頭の中が真っ白であることが手に取るように分かった。何をどうしたらいいのか、判断停止である。 「オペ室のナースなんかになって、どうするの?」 千里は剥離鉗子を竜一先生の手の中に入れた。先生は、我に返ったように、剥離鉗子を動かし始めた。副部長先生が電気メスやシーガルを使って竜一先生をサポートする。でも、いったんフリーズしてしまった竜一先生の手はなかなか動かない。器械の名前が出てこない状態に陥った。 千里は次々に竜一先生の手の中に必要な器械を入れた。先生はその器械を見て、次にやることを思い出す。この繰り返しで、少しずつ胃切除とリンパ節郭清を進めた。5時間を超えたが、どうにか目的通りに手術を完遂することができた。 麻酔からまだ覚めていない患者は眠っていた。千里は「下がりまーす」と声を出して、器械台を押して扉に向かった。そのとき、竜一先生が千里に走り寄って頭を下げた。 「ありがとうございます。助けていただき、どうにか最後に辿り着きました」 千里は、「ん、何のことですか」と短く返事して手術室を出た。でも千里の心の中には、自分はある地点まで来たという達成感があった。 大学病院に研修に出るときに、若い外科医から「オペ室のナースなんかになって、どうするの?」と言われたのは、10年近く前だ。その答えが見えた気がした。ナースは決して医師の下働きではない。医師を助けることもできるし、医師と力を合わせて患者のためになることもできる。千里は自分にとっての最後の課題はなんだろうかと考え始めた。 声が出せなくなる患者 その年の3月、医師たちの異動の噂で話が持ちきりの頃、ちょっとした緊急手術が入った。患者は、呼吸器内科に入院している70歳過ぎの男性。年齢は高いが弱々しくは見えず、雰囲気も紳士という感じだった。手術は気管切開である。 その日、フリー業務だった千里は外回りにつくことになった。器械出しは加奈子。と言っても、気切は局所麻酔だし、手術もシンプルである。どんな原疾患で気切になったのか千里には知らされていなかった。でも千里の心の中には、(この人、もう声が出せなくなっちゃうんだね。このあと、どうやって生活していくんだろう)という沈痛な思いがあった。 手術は短時間でサクサクッと終わった。執刀した外科の先生は、「じゃあ、あとはやっておいてね」と言い残してすぐに手術室を出ていった。千里と加奈子は患者を覆っているシートをめくり取って、気切チューブの周囲のイソジンをアルコール綿球で拭き取った。そして気切チューブを固定する紐を患者の首に回してそっと結んだ。 「きつくありませんか?」 千里は尋ねた。 患者は気切の部分を指さし、そのあとで自分の目を指差す。それを何度も繰り返した。千里はハッとした。加奈子に「見たいって言っているのかな?」とささやいた。加奈子も「そうだと思います」と返事をした。 「気切のところ、どうなっているのか、見たいんですか?」 千里が訊くと、患者が、うんうんとうなずく。千里はナースステーションに走った。手鏡を探し出すと、それを持って手術室に急いだ。 千里は鏡を患者の目の前に差し出した。すると、患者は、うんうん、うんうんと何度もうなずく。一生懸命にうなずく。そして気切チューブを指差したあとで、親指と人差し指でOKサインを作った。そのOKサインを何度も振り、満面の笑みを作った。 患者から教えられたこと 千里は患者がオペ室に入って来たときから、この患者が声を失うことをどう思うのかと心配だった。その心配が顔に出ていたのかもしれない。患者はそんな自分たちを見て、「心配しないでいいよ。大丈夫、OKだよ、OKだから」と言っているに違いない。この人は笑って、私たちを励ましているのだ。 千里と加奈子は患者をストレッチャーに乗せてオペ室の出入り口に進めた。そこで病棟の看護師と交代する。患者がいなくなると、加奈子が鼻をすすっていることに千里は気づいた。すん、すん、すんと音を鳴らして涙をこらえていた。でも、千里も、すん、すん、すんと鼻をすすっていた。 加奈子は千里を見て泣き顔になった。 「よかった。私、思わず泣いちゃって。千里さんも同じでよかった。泣いたら千里さんにバカにされるんじゃないかと思った。笑われたらどうしようかって。ひょっとして同じ思いだったんですね」 千里は何か言おうと思ったが、込み上げるものがあり、何も喋れなかった。ただ、涙が流れた。 手術室をきれいにしてから、二人はナースステーションに戻った。そこにいた師長が泣いている二人を見て「どうしたの、あなたたち?」と驚いた声を出した。千里は手術後のことを師長に話した。すると師長は「うん」とうなずき、「それはどうして泣いたのか、考えるべきね」と二人に告げた。 千里はそれからしばらく心の整理がつかなかった。でもちょっと考えてみれば、そんなに難しいことではない。千里は患者の優しさに心を打たれたのだ。これまで千里は病棟とオペ室でさまざまな技術を教わってきた。自分はもう何でもできるというところまで来た気がしていた。 でも看護はやっぱり、最後は心なんだなと思い至った。初対面の患者、わずか15分くらいだけ接した患者に千里はそのことを教わった。 いま病院の現場で「大きな変化」が…!看護師が「患者として入院」して気づいた《心配になったこと》