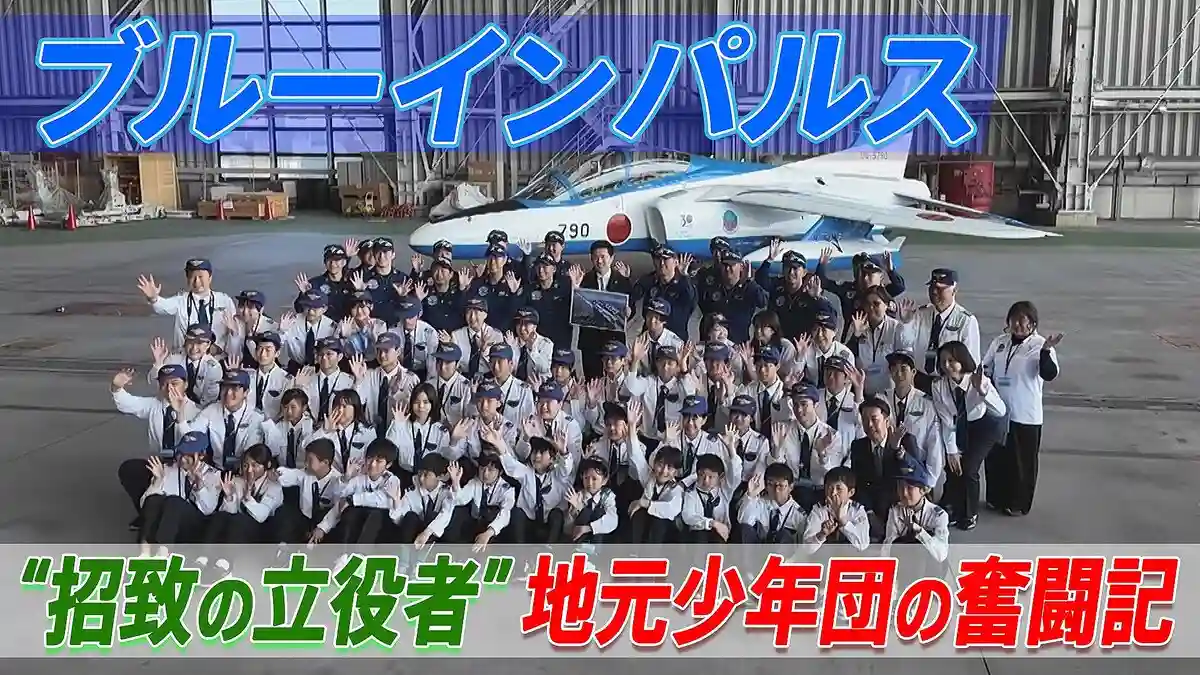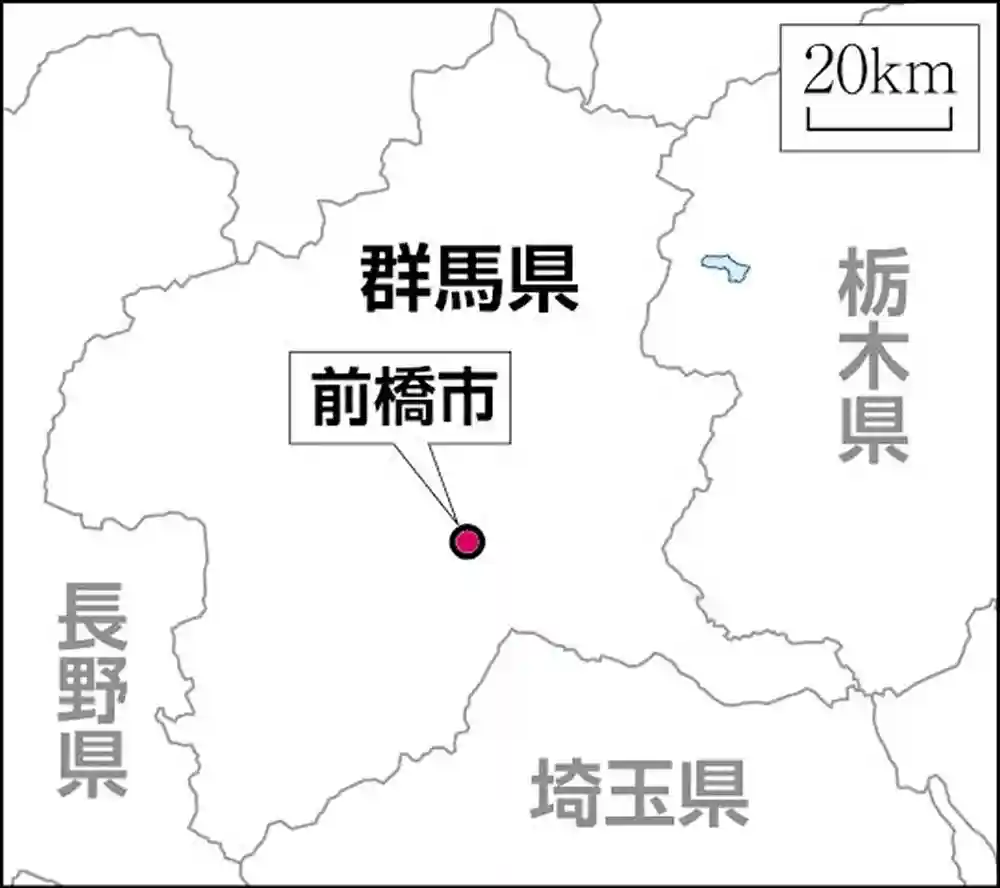4月13日に開幕した大阪・関西万博に出展している熊本の製品に迫ります。※2025年4月11日放送 【写真を見る】大阪・関西万博に “メイド イン 熊本” パビリオン屋根に阿蘇の茅&農業支える球体ロボット パビリオンの屋根に「阿蘇の茅(かや)」 大阪・関西万博には国内外から多くのパビリオンが出展しています。 このうち、熊本出身の小山薫堂さんが手掛けるパビリオン『EARTH MART』は、茅葺屋根が一番の特徴です。 建築家の隈研吾さんがデザインを担当し、全体の4割に熊本県の阿蘇の草原の茅が使われています。 茅を出荷したのは、草原保全に取り組む「阿蘇グリーンストック」。なぜ万博の屋根材に、阿蘇の茅が採用されたのでしょうか。 阿蘇グリーンストック 増井太樹 専務理事「これまでの建築では、作っては壊すことになり、ごみが出てしまう。『循環する素材は何か』と隈さんがいろいろな素材を探したところ、阿蘇の草原でとれるススキ(茅)にたどり着きました。茅は万博終了後にも、別の文化財(茅葺建築)で活用される。究極のサステナブルな循環する素材だと着目されて、阿蘇の茅が使われることになったと聞いています」 5年前から茅葺屋根の材料として、本格的に販売が始まった「阿蘇の茅」。刈り取りは、野焼き前に、ボランティアの皆さんの手で行われ、主に京都の文化財などで活用されています。 現在、茅の産地は全国的に少なく、阿蘇の茅は重宝されるとともに、品質も高く評価されています。 増井 専務理事「毎年、野焼きをしているので、ススキの穂がまっすぐ育つ。品質や供給能力で、阿蘇の草原は心強い場所だと信用され、阿蘇の茅を使ってくれたんだろうと思っています」 屋根材の他にも、万博に出展されるのが茅を使った『茅ソファ』。茅葺の技術を使って作られた製品です。 増井 専務理事「茅葺が屋根ではなく、身近なものになるのが今までなかった。こういうものが草原と私たちの暮らしの接点になっていくんじゃないかなと思っています」 写真や絵画を入れて飾る「茅のフレーム」など、阿蘇の茅製品は、大阪・関西万博の「熊本県ブース」で9月に展示される予定です。 増井 専務理事「茅が一体何なのか知らない人もたくさんいると思いますので、知るきっかけになってくれたらいいと思います」 他にも、熊本県内の大学で開発が進むユニークなロボットも万博に出展します。 棚田で活躍の「球体除草ロボット」 次は、熊本県立大学で開発が進むロボットです。 熊本県立大学 環境共生学部 松添直隆教授「棚田で活躍する球体除草ロボットです」 水田の雑草を自動で取り除くという、画期的なロボット。松添教授が、熊本高専などと連携し約5年、研究開発を進めてきました。 中山間地域で農業を営む生産者の負担軽減を目的に開発。水田内を自律走行し、雑草を除去します。 松添教授「棚田の除草は、今は手作業で行われている。農家の高齢化や担い手の減少などで、棚田の除草ができなくなっている。棚田を守るためには、雑草を防除するロボットが必要だと考えて開発を始めた」 ロボットの重さは約3キロで、田の畔や柵を認識して自律走行します。球体表面のくぼみで、土壌の雑草をかき出す仕組みです。 実験では、水田のやっかいな雑草、ヒエとコナギが見事に取れていました。 松添教授「雑草を除去して、稲は傷めない」 熊本県山都町で有機農業に取り組む野口さんは、生産者として除草ロボットの開発に協力し、大きな期待を寄せています。 生産者 野口慎吾さん「田植え後の初期から除草ロボットを使用すると、ほぼ雑草がなくなるという実験データも出ているし、現場でも実証はしているので、ロボットの良さを実感しているところです。農家が待望のロボットになっていると思います」 「球体除草ロボット」は、6月9日~11日に大阪・関西万博の「TEAM EXPOパビリオン」で展示される予定です。 松添教授「国内はもとより、海外の人たちにも、棚田の素晴らしさと、棚田を守っていくためには除草が大事だという農業の苦労も知ってほしい」