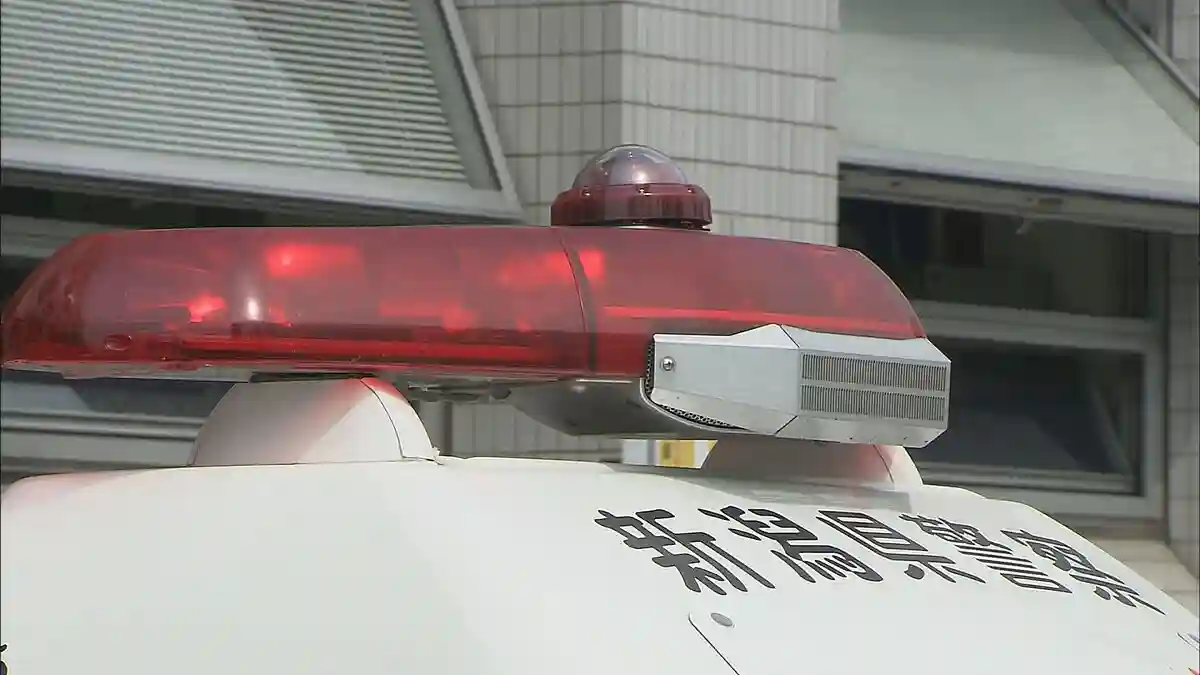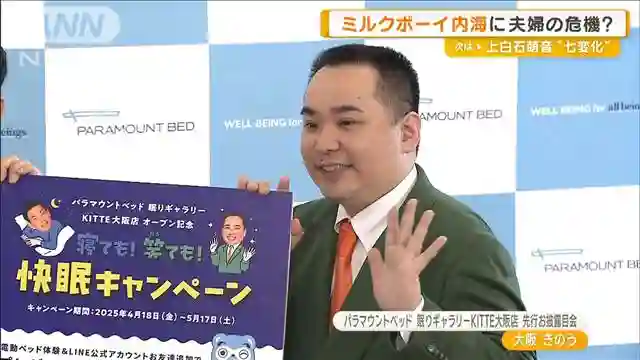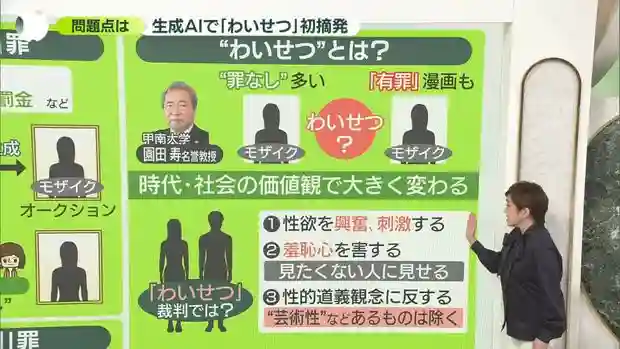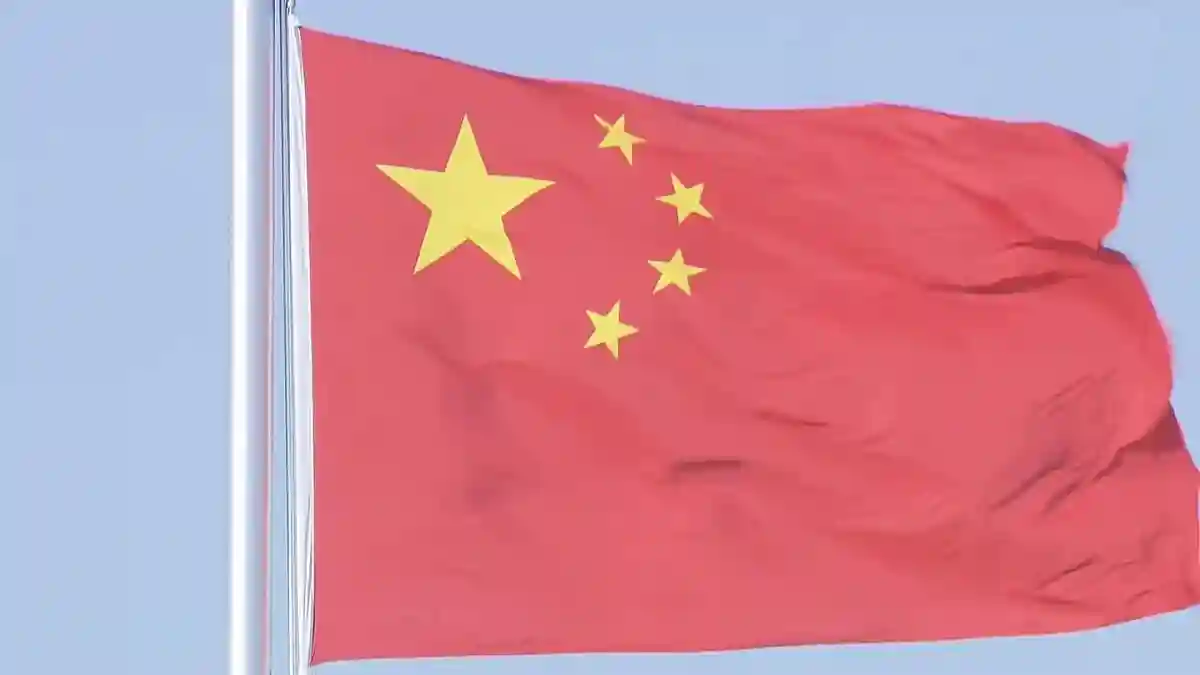5月1日は八十八夜で、初夏の青空に新茶の緑、女性の茜(あかね)だすきが典型的な茶摘みのイメージだ。 ところが、これからは黒いシートで覆われた茶畑が多くなるかもしれない。栽培しているのは、日光を遮る必要がある抹茶の原料「てん茶」。背景には世界的な抹茶ブームがある。 「ハーゲンダッツ」が始まり 京都府南部の宇治地域は国内有数の抹茶の産地として知られる。世界遺産・平等院(京都府宇治市)周辺には「抹茶」の看板や旗が立ち並ぶ。カフェはどこも満席で、座れなかった観光客は抹茶のラテやソフトクリームを手に表参道をそぞろ歩く。 JR宇治駅近くの茶商「中村藤吉本店」では、製茶工場を改修したカフェの前に数十人の外国人観光客が列を作る。目当ては抹茶づくしのパフェやチョコレート。1854年創業の老舗で、6代目の中村藤吉さん(73)は「お茶が売れず、リーフ(葉)だけではあかんとスイーツ開拓に乗り出したのが1998年。それが30年もたたないうちにこの盛況ぶり」と驚く。 ブームの始まりは96年、米発祥のアイスクリームブランド「ハーゲンダッツ」が手掛けた「グリーンティー」だった。主に初摘み茶葉で製造した本格派で、中村さんは「宇治の茶農家はみんなうまいとうなった。あれが『飲む』から『食べる』への転換だった」と語る。 今では大手菓子メーカーやコンビニが独自の製品を開発し、抹茶味の生菓子やスナック、飲料など百花繚乱(りょうらん)の様相だ。 スイーツ人気を受け、抹茶そのものにも熱い視線と期待が集まる。てん茶の国内生産量は右肩上がり。全国茶生産団体連合会によると、2008年が1452トンで、23年には11産地で4176トンと約3倍になった。 抹茶などの粉末茶を含む「緑茶」の輸出額も増えている。財務省貿易統計によると、24年に364億円と過去最高を更新した。15年前の11倍で、7割以上を抹茶などの粉末茶が占める。 抹茶の需要が高まる中、茶の栽培農家は後継者不足にあえぐ。この15年で4万6000戸から2万戸に激減している。農林水産省は今年3月、茶農家に対し、煎茶からてん茶への転換を促す方針をまとめた。煎茶は覆いをかけずに栽培し、急須などで飲む一般的な茶だ。担当者は「抹茶ブームを好機ととらえ、稼ぎ頭として力を入れる。国内外に日本の茶文化に関する情報を発信したい」と意気込む。 産地はブームを歓迎しつつ、過熱する人気に懸念を示す。「ネットで3倍の価格を確認したが打つ手がない」。ある茶業関係者は頭を抱える。転売とみられる抹茶の買い占めが横行し、販売数を制限した。それでも毎日買いに来る人がおり、粗悪品も出回っているという。 杉本宏・京都芸術大日本庭園研究部門長(68)は「産地の願いは、スイーツを食べた若者や子どもが大人になって抹茶を飲んでくれること。産地が培ってきた抹茶のイメージを壊さないでほしい」と願う。 煎茶からてん茶への転換にも不安の声が上がる。全国茶商工業協同組合連合会の藤田文敏・専務理事(72)は「転換には費用と時間がかかり、個人や中小農家にはハードルが高い」と心配する。諸外国が栽培を始めれば、当然価格競争が激しくなる。 宇治の製造・卸「福文製茶場」の5代目、福井景一さん(60)は初代から伝わる話を覚えている。昭和30年代に抹茶ブームが到来したが、コーヒーや紅茶の普及で、40年代には「お茶余り」に陥ったという。その時の生き残り策は「手間暇かけたおいしい抹茶を作り続ける」。ブームを経て得た重い教訓だ。