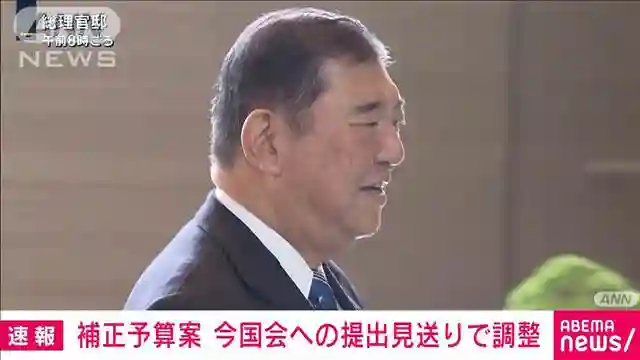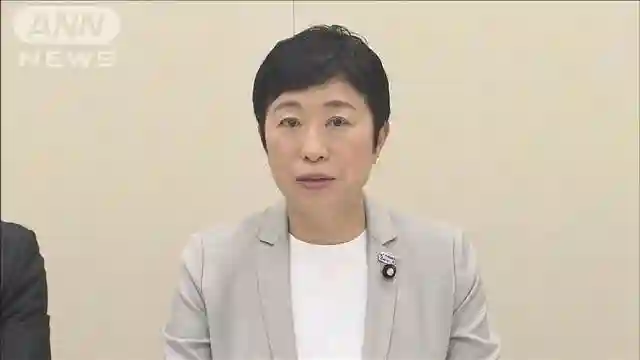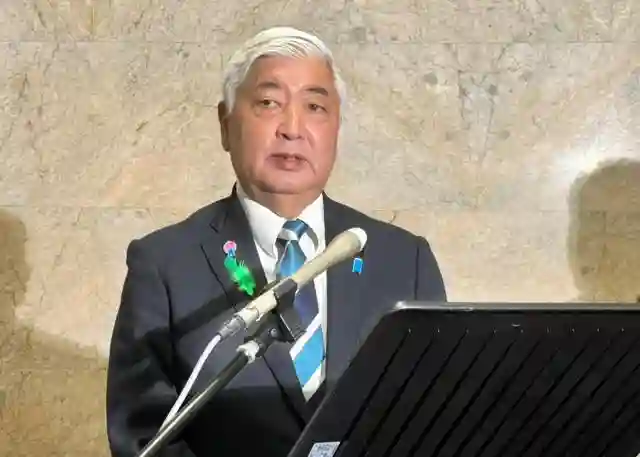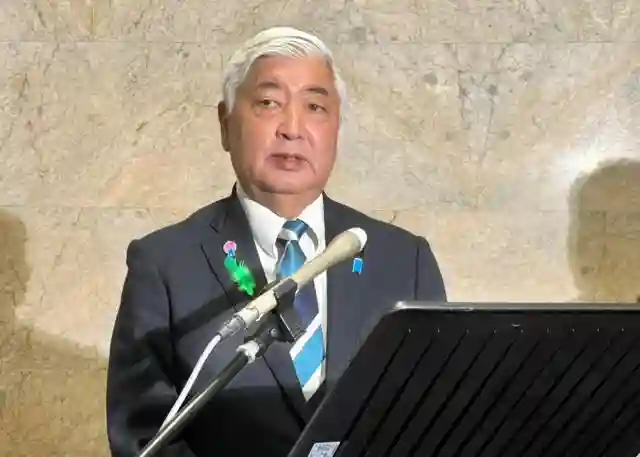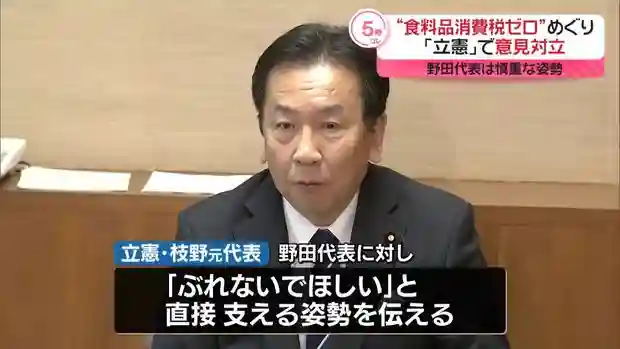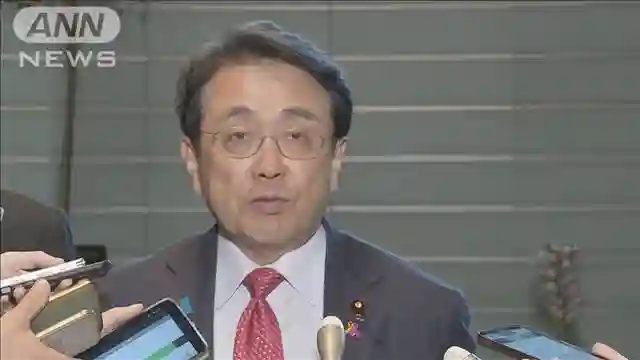高齢化が進む日本社会において、親の介護は多くの家族が直面する課題です。特に、高齢の親との同居は、家族構成や生活スタイルに大きな変化をもたらすため、慎重な検討が求められます。住環境の変化は、高齢者の心身に予期せぬ影響を与える可能性があり、介護の負担増加や経済的な問題を引き起こすことも少なくありません。実情をみていきます。 急速に老けた75歳の母 39歳の正美さんは、夫と2人の子どもとの4人暮らし。地元は新潟県で、大学入学を機に上京しました。卒業後も都内で大手企業に就職し、友人の紹介で出会った同い年の夫・孝さんと結婚。途中で育休を挟みながらもキャリアを重ね、順風満帆な人生を送っています。正美さんの年収は850万円、孝さんの年収は1,050万円、世帯年収にして1,900万円と経済的余裕のある世帯です。 満ち足りた日々を過ごす一方で、ここ最近の正美さんには心配事がありました。それは、新潟の実家で1人暮らしをしている75歳の母のことです。3年前に父が亡くなってから、実家には母が1人で暮らしています。夫婦仲がよく、いつも2人で散歩をしたり、庭いじりをしたりしていたので、1人きりになった母が気落ちしていないか心配していましたが、なんとか前を向いて暮らしているようでした。 しかし昨年末に家族で帰省した際、母がめっきりと老け込んでしまったことに気が付きました。夏休みに帰省したときは、まだ生き生きとしていたはずが、完全にお年寄りの雰囲気になっているのです。「75歳ってこんなに弱々しくなるものなの?」と少なからずショックを受けました。おしゃれ好きだったはずが、髪の毛の手入れは行き届いておらずボサボサ。整理整頓上手だったはずなのに家の中も散らかっており、冷蔵庫は賞味期限切れのもので溢れていました。 1番衝撃を受けたのは、母が使っている軽自動車のあちこちにできていたへこみや擦り傷です。思わず、ニュースで流れる高齢者の暴走事故が頭をよぎりました。「そろそろ免許を返納したらどうかな」と母に提案しても、「まだまだ運転できるし、足がないと困るから」と、返納するつもりはないようでした。しかし、へこみだらけの車を見ると、とても安全運転ができるようには思えません。夫も同じ不安を抱いたようで、帰りの飛行機のなかで「お母さん、1人暮らしを続けるのはそろそろ厳しいかもしれないね」といわれました。 正美さんの頭の隅には、いつも母への心配がちらつくようになりました。 マイホームは二世帯住宅に 同じころ、正美さんと夫の孝さんは「子どもたちも小学生になったし、賃貸暮らしから家を購入しよう」とマイホームについて話し合っていました。さまざまな物件を探しているうちに、ふと正美さんの頭に妙案がよぎります。「実家の母を東京に呼び寄せて、一緒に暮らせばいいのでは?」夫にこの提案をもちかけると、快く受け入れてくれました。母と暮らすのであれば、最低でも4LDKの間取りが必要。物件は戸建てに絞ることにしました。 次の日、正美さんは母に電話して、東京で一緒に暮らさないか、と切り出してみました。すると母はとても驚き、「いまの家を離れたくないし、都会になんて住めないわ」と断ろうとします。しかし、正美さんはあきらめず、孫と住めること、雪かきも必要ないこと、遠くの病院に通う必要もなくなること、車にもう乗らなくていいことなど、東京に住む利点を根気よく説明しました。少し時間が欲しい、といった母でしたが、1週間後に「あなたたちがいいのなら、一緒に住みたい」と返事をくれました。 予算がかさみ、東京郊外に建築 母の了承が得られた正美さんと孝さんは、さっそく土地探しとハウスメーカー探しに取り掛かりました。母のためのキッチンとトイレ、居室を備えた家を各メーカーに設計してもらったところ、やはりそのぶん建物が大きくなり、広い土地も必要なことがわかりました。土地費用がかさんだため、資金計画は9,600万円となりました。自己資金の2,000万円を引いて、住宅ローンの借入額は7,600万円、毎月の返済額は19万9,000円です。いまの住まいである築20年のマンションの家賃が22万円のため、月々の支払いはむしろ安くなります。 とはいえ、これまで正美さんも孝さんも職場までドアトゥドアで20分もかからずに通えていましたが、それぞれ電車で40分+徒歩20分と、通勤時間が大幅に伸びてしまいます。しかし、それを承知のうえで計画を進めていくことに決めました。 問題は実家の処分です。買い手がつくか不安でしたが、そう時間はかからずに地元の不動産業者から申し出がありました。300坪ある敷地に建売住宅を5棟に分譲して販売するらしく、自宅の解体費用は業者が負担、とのこと。850万円という値がつき、検討の末、その業者と売買契約を交わしました。850万円は母の老後資金の大きな足しになります。 同居からわずか3ヵ月後、懺悔した理由 いよいよ新居で母との同居生活が始まります。母は新生活に刺激があったのか、顔が明るく元気な様子でした。近所の商店街に歩いて行ったことなどを嬉しそうに正美さんに話していました。 しかし、次第に様子が変わっていきます。引っ越しから3週間が過ぎたころ、母は夜に眠れなくなってしまいました。夜中にリビングのソファに腰かけ、正美さんが声をかけても上の空。そしてこんなことをいいました。 「お父さんを呼んできて、正美、お父さんにも残しておいたからみんなで食べよう」 亡くなった父のことをいっているようです。はじめは夜中なので寝ぼけているのかと思ったのですが、状態はどんどん悪化。夜になると激しく興奮するのです。大声をあげたり泣きだしたり……。「お父さんが帰ってきたのに夕飯の支度ができてない」「正美が学校で仲間外れにされた」などといい、正美さんも困惑。母をなんとか抑え込もうとつい大声を出してしまい、ぶつかり合います。せん妄は数日で収まりますが、何度も繰り返してしまいます。 そんな様子を目の当たりにした正美さんの息子たちは怯えるように。引っ越しからわずか3ヵ月後、日中に母を家に1人で置くことができる状態ではなくなりました。職場の産業医に相談してみると、「環境の変化で認知症が進行しているのかもしれない。地域包括支援センターに一度相談してみたほうがよい。近い将来、介護施設への入居も検討すべき」とのこと。正美さんは愕然とします。 母を介護付き有料老人ホームへ 軽度の認知症を発症していた母を移住させたことで、母の健康を損なう原因を作ってしまいました。母のために仕事をたびたび休むわけにもいかず、八方ふさがりに。結局、家族への負担も考え、母を介護付き有料老人ホームへ入居させることにしました。月額費用は18万円、一時金に320万円かかります。母の年金で賄いきれない分は貯蓄を取り崩すことに。あまり考えたくないことですが、何歳まで生きるかわからないなか、資金面で不安を感じます。なにより、母自身のことを思うと悔やんでも悔やみきれません。 夫にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。母との同居がなければ、予算内で職場に近い家を購入できたかもしれません。家が完成してからたった3ヵ月で使用しない部屋とキッチンが残されてしまい、大きな無駄となりました。無謀な計画だったと自分を責めるばかりの正美さん。夫は「お母さんを想う気持ちからやったことだから、結果はどうあれ仕方がないことだよ」といってくれますが、正美さんは胸が詰まって仕方ありません。 高齢親に急激な環境変化を与えてしまうと… 正美さんの事例のように、高齢者が生活環境を急激に変えることで心身に不調をきたすことがあります。これは「リロケーションダメージ」と呼ばれ、引っ越しによるストレスが原因で、せん妄、認知症、うつ病などを引き起こしてしまうことです。 安易な環境の変化は、高齢者の健康を著しく損なうリスクを伴うため、慎重に検討しましょう。特に、高齢の親を呼び寄せたり、子ども家族が実家に移り住んだりするようなケースでは、親世代への悪影響に注意しなければなりません。たとえ当人同士が望んだ引っ越しであっても、高齢者の心身には深刻な負担となることがあります。現在の生活環境をできる限り維持しながら、親世代の老後生活と介護にどう向き合うかという視点から考える必要があるでしょう。 高齢化が進む現代日本において、家族のあり方は新たな課題に直面しています。この課題解決には、経済的な負担が避けられません。親世代が元気なうちから将来的なサポート体制と資金計画について家族で話し合い、準備を進めておくことが重要です。