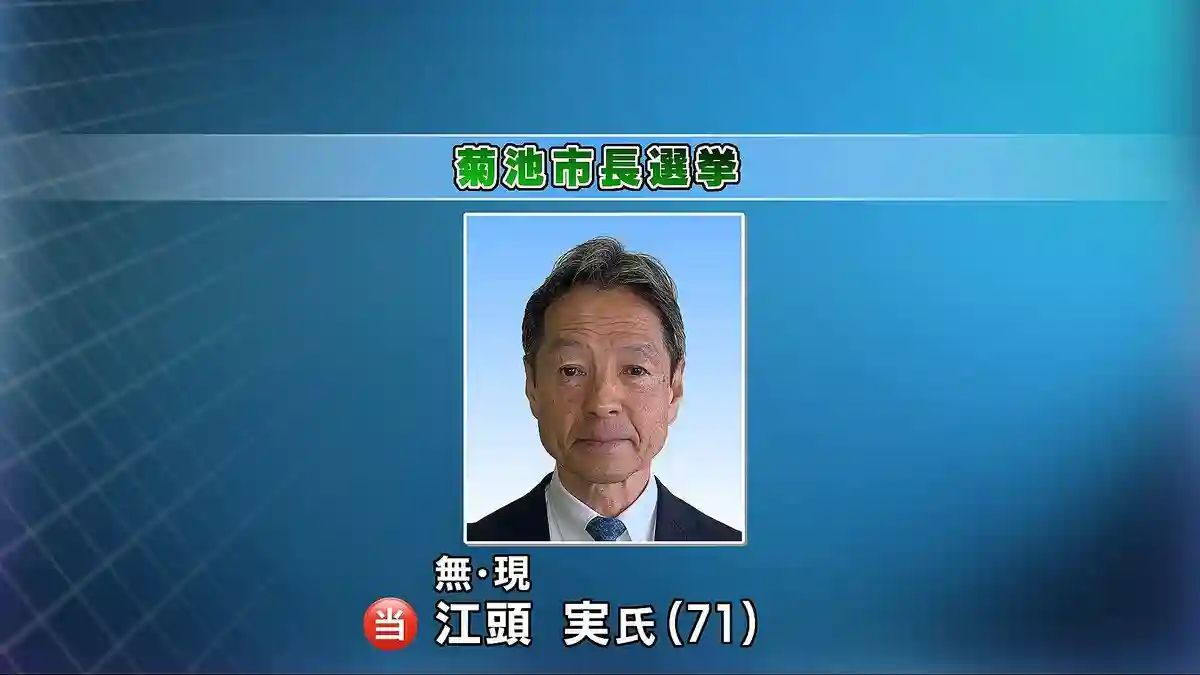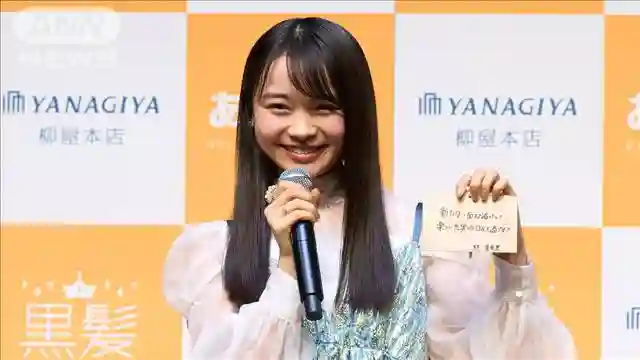颯爽と登場し、瞬く間に世を賑わせている生成AI。 とどまることを知らない技術革新、 スマホネイティブならぬ「生成AIネイティブ」が生まれる日は近い。 生成AIに仕事を奪われる?子育てに生成AIを活用できる? 期待と恐怖が入り混じる世間の反応、そして「生成AIのある未来」に、 物理学者と言語学者は何を思うのか——。 田口善弘氏(『知能とはなにか』)と川原繁人氏(『日本語の秘密』『「声」の言語学入門』)が、生成AIの可能性と危険性を語る。 最先端の思考実験がぶつかり合う刺激的な対談に、刮目せよ。 【対談】拝啓、生成AIネイティブ世代へ #3 スマホの登場で急増する「うつ病」 川原やはり一番厄介なのは、『知能とはなにか』の主題でもありますが、感情とはなにか、知性はなにか、倫理とはなにか、といったことについて、我々自身がまだわかっていないということ。それを生成AIに搭載させようというのは、すごく難しい話なんですよね。だからこそ時期が早いという感想になる。 「おしゃべりアプリ」について考えるにあたって、当初はスマホ問題とは切り離して考えたかったんですよ。仮にスマホに人間に対する悪影響がないのだとしても、それとは独立して「おしゃべりアプリ」はいかん、と思っていたので。けれどもやはり、両者は繋がっていて。 スマホは今、現代人の体の一部になりつつありますよね。相当な中毒性がある。アメリカのデータなんですが、2010年から2012年、スマホが家庭に広がったときから、精神疾患率の急増がひどいんですよ。うつ病は、たった8年で2倍以上になっているんですね。 田口なぜスマホでうつになるんですか。 川原いろいろ言われているんですが、ジョナサン・ハイト(Jonathan Haidt)という心理学者の仮説によれば、SNSの使用が精神にかなりよくない。他人と比較してしまいますから。人間というのは他人と比較する生物ですから、それはしかたがないのですが、その比較する対象が、SNSによって無限になってしまったんですよね。 スマホができる前は、自分の周りにいる人なんて、たかが知れていたじゃないですか。100年、200年前なんて、人生でかかわる人の数は、せいぜい4、50人だった。それが今ではスマホを通じて世界中の人と繋がっていますから、世界中の人と自分を比較してしまう。 しかもスマホの中の世界はキラキラしていますから、自己肯定感はさらに下がって、それがうつ病に繋がってしまう。もちろん、ファクターの一つではあるのですが……。それから、現代人は集中できなくなったというような話も展開されています。先生は、授業中、学生に「スマホはカバンにしまいなさい」といいますか。 田口いや、僕はそういうことを言いたくないから、すべての講義のビデオを配っているんですよ。聞き逃しても、後で聞けばいいですから。教室内で私語している学生には、帰ってくださいと言いますが、それ以外は何をしようと自由。 川原言っても、今の大学生はスマホをしまわないですよね。ふせていればマシという感じで。 田口そうそう。しまわないと思っているから、相手を変えるのではなく、自分の方を変えることにしました。スマホをしまわない学生にも、最終的に内容を理解してもらうにはどうすればいいのかを考えると、すべてを録画して配るというのが合理的。 嫌なのは「選択肢」が奪われること 川原そこは諦めていらっしゃるんですね笑 田口諦めたと言われてしまうと……笑 学生にも「先生は僕らに何も期待していないんですね」と言われてしまったんですが、諦めたというよりも、最終的に分かればいいんだから、別に方法は関係ないというのが僕の考え。でも、そういうときにスマホをしまえる人間に育てた方がいいという考え方の人から見ると、諦めているように見えてしまうのかもしれない。 川原多少は笑 田口ハハハ笑 僕は技術で解決できることはすべて技術で解決します。コロナになる前から、授業ビデオもプリントも配って、学校に一回も来なくても、自分で勉強すれば試験が取れるという授業スタイルでした。 川原わたしはどうしても学生と「対話」したいんですよ。一方通行でしゃべるのが苦手で。学生の顔を見て、面白いと思われていそうな箇所を膨らませたいし、つまらないと思われていそうな部分は、面白くできるように調整したい。その中で、自分の考え方が学生に伝わっていくのを感じるので、そこは譲れないかな。 田口インタラクティブにやりたい先生は多いと思うんですが、そもそもあてられるのが嫌だと思っている学生も結構多いですよね。 川原そういう学生は、わたしの授業に合わないということで笑 幸い、わたしの授業は必修ではないので、納得できる人だけ来てください、と言っていますね。でも、先生のやり方を突き詰めていくと、大学、いらなくなっちゃいません? 田口大学、いらないんじゃないですかね。 川原ハハハハハ笑 田口ただ非常に不思議なのは、授業そのものはやらずに「去年のビデオを見てください」とだけ言うと、ダメなんですよ。授業の評判が悪くなる。そこが人間の変なところです。 川原やはりそれは、学生側は田口先生のメッセージを、少し時差はあるとしてもリアルタイムに受けとめたいということですよね。 田口要するに自分の側に選択肢があればいいんですよね。対面授業をやっているけど、自分はそこには行かない、というのは自分の選択。でも去年のビデオ見ろと言われたら、対面授業を見るという機会そのものが奪われていることになる。 コロナのとき、キャンパスに来る気はなかったであろう学生でも、いざ「キャンパスに来るな」と言われると、ものすごく反発した。キャンパスに入れるのに来ないというのは彼らの自由ですが、「来るな」というのは選択肢が奪われている状態ですから、嫌なんです。 愛に「応えたい」という気持ち 田口だから、大学は一見いらなくなりそうに見えるのですが、依然としてやはり、「授業を自分たちのためにやってくれている」という感覚がないと、やる気は出ない。そこが人間の不合理なところですよね。 通信教育での卒業が難しいというのも、そのせいではないかと僕は思っていて。あれって誰に向かって喋っているかわからないでしょう。そうすると、応えようという気持ちが薄れるんだと思うんですよね。 川原それってさっきの生成AIの話に似ていますね。大きなLLM(大規模言語モデル、Large Language Modelsの略)が一つあって、それに子育てをすべて任せるというのだと人間の……。 田口個別性も、パーソナルな関係もなくなってしまいますよね。 川原それについては、乳幼児の脳科学の面白い実験があります。自分の母親の声や、NICU(新生児集中治療室)に入っている赤ちゃんであれば看護師さんの声に対しては、言語野と報酬系の神経的な繋がりが観測されるんですよ。赤の他人の声では、繋がらないらしい。お母さんでもお父さんでも、自分に愛情をもって接してくれる人の声は、文字どおり心地がよい。だから言葉を学ぶモチベーションに繋がるんですが、他人の声ではそれが起こらないそうなんです。 田口先ほどの「なぜ生成AIのドラえもんではダメなのか」というのも、個別性の話ですよね。ドラえもんは、のび太の子孫が、のび太が将来幸せになるために——幸せにならないと子孫が生まれず、自分が消滅してしまうというフィードバックループがあるから、それは必須なんだけど——送ってくれたロボットなんですよ。 でも多分、生成AIドラえもんにそういうことはできない。そういう意味では、大きなLLMではなく、ローカルなLLMを、たとえば親がゼロから作っていくのであれば、いいのかもしれない。 川原そこまで行くと、もはや「自分で育ててください」と思ってしまいますが……。 田口でも、残業していてどうしても帰ってこれないというとき、今の親御さんって割とスマホをつけっぱなしにしておくとか、Skypeしっぱなしとかいう方法をとっていますよね。 川原確かに。どれだけ「補助的」かというのも、一つのファクターだと思いますね。メインの部分は養育者がちゃんと背負って、どうしようもないときに頼るというのであれば、程度によりますけれども、いいのかもしれない。 物理学者が「創造性は低くてもいい」と断言するワケ…生成AIの驚くべき「活用法」と「危険性」