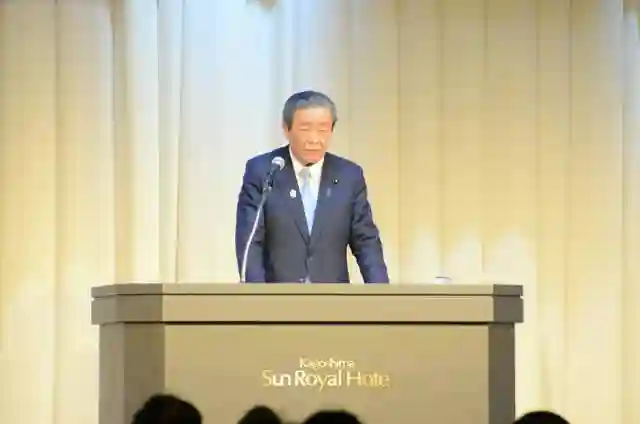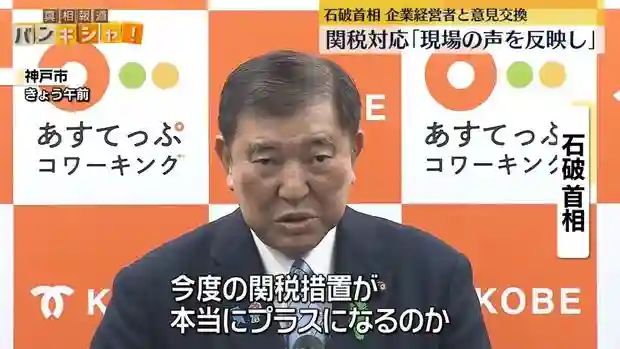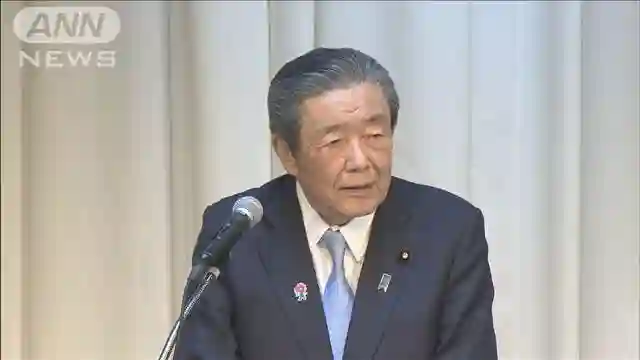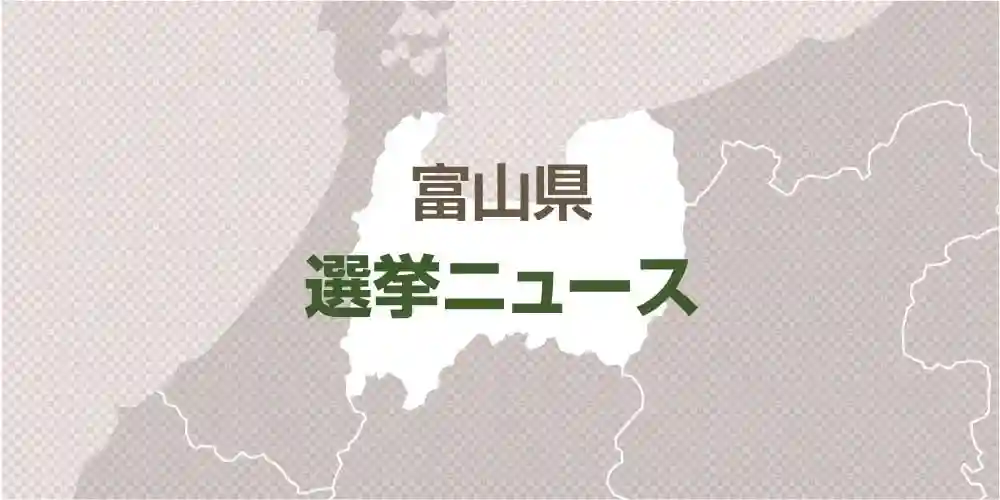告示まであと2か月となった東京都議選(6月13日告示、22日投開票)で、定数127(42選挙区)に対し、12日時点で219人が立候補を予定していることが読売新聞のまとめでわかった。 直後に控える参院選の行方を占う選挙としても注目され、「政治とカネ」の問題で逆風が続く自民党が都議会第1党を死守できるかが焦点となる。また、初の議席獲得を目指す国民民主党、新しい地域政党も候補者の擁立作業を進めており、結果次第では今後の都政運営に大きな影響を与えることになる。 ■擁立作業に遅れ 自民は2017年の都議選で「小池旋風」の前に歴史的惨敗を喫したが、21年の前回選は33人が当選し、第1党に返り咲いた。当初は対立していた小池知事とは協調する路線に転じており、昨年の都知事選でも推薦こそしなかったものの、自民も小池知事の支援に回った。 自民は派閥に続き、都議らの政治資金パーティー収入でも不記載が発覚し、世論の反発を招いた。自民都連は、会派の幹事長経験者で不記載のあった山崎一輝氏(江東区)、鈴木章浩氏(大田区)、三宅茂樹氏(世田谷区)、小宮安里氏(杉並区)、宇田川聡史氏(江戸川区)、三宅正彦氏(島部)——の6人を公認しない方針を示している。 ただ、影響は依然大きい。自民が12日までに公認したのは26選挙区の30人と、擁立作業をほぼ終えていた前回選の同時期と比べて大幅に遅れており、自民都連幹部は「厳しい状況だが、一人でも多くの候補者を擁立したい」と話す。 国政で自民と連立を続ける公明党は、20選挙区に22人を擁立することを決めた。都議選では8回連続全員当選を果たしてきたが、今回は前回選の23人から1人減らした。党勢を考慮したとみられる。 候補者を絞ってでも全員当選を果たしたい構えだが、公明都議たちは「自民の逆風に巻き込まれ、苦戦を強いられるのではないか」と危機感を強めている。公明都本部は、候補者を立てない選挙区でも自民の候補を推薦しない方針を決めており、自民とは一線を画する姿勢を有権者に示したい考えだ。 ■都ファ、国民と連携か 都議会第2勢力の都民ファーストの会は、31選挙区で33人を公認した。さらに複数人を擁立すべく作業を進めている。 女性が12人と4割弱を占めており、特別顧問を務める小池知事と二人三脚で女性登用など都政改革を進めてきたとアピールし、第1党の奪還を目指している。結成してから2度の都議選を戦い、都民への浸透が進んだ一方、都政の刷新を求める層が他勢力に流れてしまう懸念もあり、都ファ幹部は「地力が試される選挙となる」と語る。 昨年10月の衆院選で躍進した国民民主は、11選挙区で11人を公認した。今回の都議選でも勝利し、参院選への弾みをつけたい思惑がある。 都ファと国民民主は協力関係にあり、都議選での対応にも注目が集まっている。小池知事は3月の記者会見で両党の都議選での連携について問われ、「(国民民主の玉木代表は)もともと希望の党を始めた仲間だ」と発言するなど、国民民主との近さをうかがわせている。 ■立民、共産と共闘 小池知事と激しく対立する共産党や立憲民主党は一部選挙区での共闘を図り、「知事与党」勢力の過半数割れを狙う。 共産は現有19議席からの上積みを図り、23人を公認した。うち女性が17人を占めている。 立民は18選挙区に19人を公認した。さらに擁立を進める方針で、第1党への意欲も見せる。共産とは定数の少ない選挙区を対象に、競合を避ける調整を行っている模様だ。地域政党の東京・生活者ネットワークが公認した3人を推薦したほか、都議会の会派「ミライ会議」の都議3人も公認や推薦で引き入れた。 現有1議席の日本維新の会は6選挙区に6人を立て、勢力拡大を狙う。都議会に議席を持たないれいわ新選組や参政党、社民党も立候補予定者を公認しており、議席獲得を目指す。 昨年の都知事選で次点だった前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏は今年1月、全選挙区への候補者擁立を掲げ、地域政党「再生の道」を創設した。候補者の公募には1000人以上が応募。これまでに28選挙区に38人を擁立することを決めた。4月中に擁立作業を終わらせる予定という。