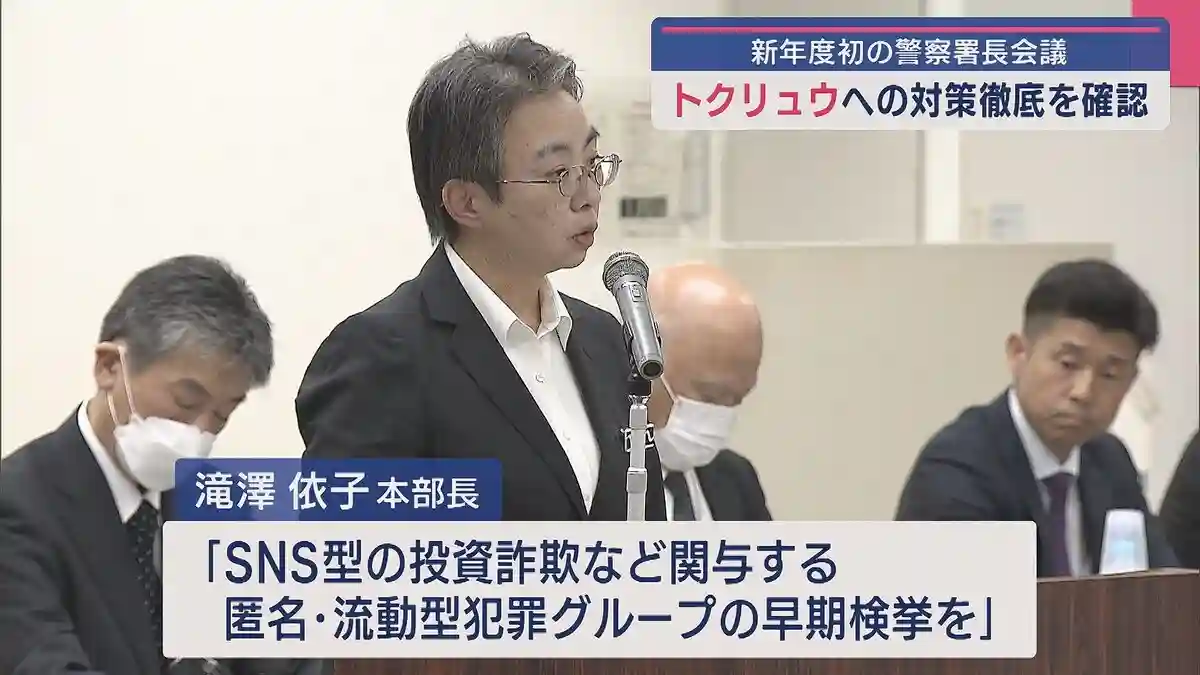「ヤクザ生まれ、施設育ち」 ステージでそう明るく自己紹介をするのは、6人組完全セルフプロデュースアイドルグループ『アイドル失格』を立ち上げ、プロデューサー兼プレイヤーとして活動するえんじてゃさんだ。 ヤクザの親から逃げるため、施設を転々とする幼少期を過ごした彼女が手に入れたのは、不合理に立ち向かう力だった。そして現在は、地下アイドルが抱える「理不尽な収益構造」を壊すべく活動を続けている。 地下アイドルとは、小さなライブ会場での公演を繰り返しながら、ファンとの交流を軸に活動する存在を指す。えんじてゃさんは、運営の裁量によって、夢を追うアイドルたちが利用されている現実を目の当たりにしたという。 「壊されたアイドルへの憧れ」 えんじてゃ氏が5歳の時、母親が自己破産したという。その後、ヤクザだった父親から逃げるように市役所が運営する母子施設へと身を移す。 その後、多くの時間を集団で過ごすなか、徐々にコミュニティへと馴染むことに成功する彼女。 「高校生活では、受験勉強に力を注ぎました。父と母に足りないものは『学ぶこと』という認識が根底にあったからだと思います。ただ実際には、入学金や授業料のかからない、現実的に通学可能な大学に行きました」 大学進学とともに、根本的に考え方や生き方の合わない母親のもとを離れ、自分の力だけで生きていくことにした。 そしてここから『アイドル失格』へ向けた道を歩みだすことになる。 「SNSで顔出しの発信をしているなかで『アイドルになりませんか?』というDMがかなりの数来ていたことが気になっていました。一年生の半ばごろ、インターンで東京へ行く機会があったのをきっかけに、スカウトの方から話を聞いてみることにしました」 母がテレビで男性アイドルをよく観ているそばで、えんじてゃさん自身は女性アイドルに興味をもっていたそう。特に、高校生の頃に観たユニット『生ハムと焼うどん』が織りなす自由で信念のあるパフォーマンスには、かなりの刺激を受けたと話す。 所属した事務所には、既にいくつものグループが結成されていました。デビューライブの会場も予想を超える規模の大きさで、アイドルとして成功する予感にワクワクしたのをよく覚えています。 しかしある日、気付いてしまったんです。私はただの『女の子をできる限り集めて、目の前のお金だけを稼ぐ』ビジネス構造の一つであることに」 彼女はそのまま、運営がおこなっていた理不尽な収益モデルを解説してくれた。 「一度デビューさえすれば、定期公演などをする過程で、熱量高めのファンが2、3人付いてくれます。ここで登場するのが、たとえば1000円でチェキ撮影をしたら、300円女の子に戻るシステムの『チェキバック』ですね。チェキの原価は安く、仮に100円だとしても、運営の手元には600円残るわけです。つまり、女の子を多く抱えているほど、運営はローリターンで多額の収入をゲットできると考えられます」 さらに、基本的に固定給は発生せず、チェキ以外ではお金を稼ぐ手段がなかったとのこと。 その状況から、人気のアイドルになる道筋もあるのではと尋ねると、さらなる現実的なエピソードが語られていく。 「事務所は、女の子一人ひとりをスターにする気なんて、サラサラなかったんですよ。いつまでも宣伝をせず、MVも作らず、ただただ週に3.4回ライブステージを用意するのみ。私たちは、1日にチェキを10枚撮ったとしても、3,000円しか給料になりません。この場所に居続けても、夢の先へは導いてくれない。そんな現実に気がついたときは悲しかったです」 楽屋に戻ってみれば、薬物の中毒者であろうアイドルが暴れている姿を発見してしまい心は限界になる。そして、活動休止を宣言する。 「自分の好きだったアイドルが、こんな残念な形で終わってしまうのは、正直やりきれない気持ちでいっぱいでした。同時に『アイドルに対する希望と社会への無知さを利用し、運営だけが得をする収益構造』を壊したい気持ちが止まらなくなっていきました。 地下アイドルのあり方を変えつつ、自分が居たいと思えるグループを作る。そのためには、もう自分がプロデュースするしかないと思いました」 「地下アイドルビジネスへの疑問」恋と愛の違いとは そして、これまでの人生で培った行動力を駆使し、急ピッチで『アイドル失格』を発足。グループ名は、太宰治の 『人間失格』から取ったという。 「太宰治の文学は、王道だけど発想自体は変わっていて、本人もどこか様子のおかしいところが特徴です。でも、どこか光るものがあるがゆえに、いまもなお誰かを支えています。 『アイドル失格』では、大暴れをして炎上するなど、王道と外れたことをしたいわけではありません。理不尽な時代でも踏ん張る姿を見せつつ、常に目が離せない存在になっていく。そんなひと味変わったグループにしたいと思い、ほかでは見ないような名前にしました」 「ひと味変わった」というワードを聞いて、ますます引っかかることがある。『アイドル失格』には、男性メンバーが所属しているのだ。 「結成当時の私は21歳で、どうしても下に見られてしまう傾向がありました。男性がいれば、コミュニケーションの柱になってもらい、スムーズにビジネスをしていけるのではと思ったんですよね。彼はもともと友人だったので、私の考えにも理解を示してくれました。そしていざ矢面に立ってもらうと、私たちが表現していきたい『クリーンさ』にも一役買ってくれることに気付きました」 「クリーンさ」に対する説明を求めると、またも地下アイドルのあり方を考えさせられる答えが返ってきた。 「地下アイドル界隈には、本物の彼女と錯覚させるほどの『ガチ恋営業』を仕掛けて、コアな顧客を生み出していく手法があります。それが私はすごく嫌で、ファンとはキリスト教の『隣人愛』のような関係性を作りたいと思っているんです。 具体的には、起伏の激しい『恋』ではなく、居心地の良さを重視した『愛』を大切にするクリーンな関係を目指しています。男性の存在がある限り、独占欲あふれる過激な思考の人が現れにくいと感じていて。実際に、現在の現場の雰囲気はとても良好です」 続けて、地下アイドルではもはや当たり前と思えるようなビジネスモデルにも、疑問を覚えていることを話してくれた。 「地下アイドルにありがちな、都内で週に何回も対バンライブをおこなう傾向に対しては『ペルソナは誰なの?』と思ってしまいます。開催日程もセットリストも直前で決まるなか、付いてこれる客が果たしてどれだけいるのかと。 そもそも私は、グループの動きにひたすら振り回されるような行動をファンにしてほしくないと考えています。デビュー当時は私たちもライブをよくおこなっていましたが、早い段階で断念しました。 『地下アイドルが好きで、頑張っている姿を応援したい人が通いやすい現場作り』を模索するなか、現在は月に1回のワンマンライブを中心に活動しています」 月に一度の公演に思いを込めることで、構成を練ったステージにできることも魅力だと話すえんじてゃさん。根強いファンも、毎回新鮮な笑顔を見せてくれるそう。 また、インターネットでのコンテンツ配信を日常的におこない、ポートフォリオのように行動が積み重なる構造を意識していることも教えてくれた。グループを知ってもらう機会を増やしながら、地下アイドル特有の親しみやすさも打ち出していくのが狙いだ。 「異常者のままで良い」 ここまで、ひたすらに真っ直ぐみずからの行動を信じる姿を見せてくれた彼女。ふと、生まれながらの理不尽な境遇が、いまの人生にどれほど影響を及ぼしているかを聞いてみた。 「もし普通の環境で生きていたら、アイドルになるどころか、グループ立ち上げすらしていなかったかもしれません。 これまで受けてきた理不尽は、将来もずっと私のなかに残り続けます。しかし『あれは仕方なかったことなんだ』と許してしまうと、過去の自分をいつまでも救済することはできないと考えています。 あの頃の自分を肯定する方法の一つ。それは、同じ境遇の人にみずからの経験を届けることです。たとえ異なる生き方であっても、苦しい思いをしている人に手を差し伸べていけば、自分をもっと好きになれると思っています。 いま、そのような生きづらさや辛い気持ちを抱えている人たちの伴走者になれていることは、アイドルをやるうえでのモチベーションです」 そう話すえんじてゃさんの目からは、迷いの感情は一切感じ取れない。笑顔で過去を語り、未来のあるべき姿を提示していく彼女の心の強さには、頼もしさを感じるほかなかった。 最後に、理不尽な環境に生まれてしまったと嘆く人に向けて、等身大のメッセージを届けてくれた。 「家族のなかで、私はずっと異常者として扱われていました。みんなの考えに逆らい続け、強い意志のもと行動していたのですから、当たり前だと思います。 世の中には、恵まれない子どもに生まれてしまったと、人生ごと諦めてしまう人がいるかもしれません。そのような人にこそ、私みたいにたまたま上手くいった例があることをぜひ知ってほしいです。 逆境を跳ね除けながら、自分のことを好きでいてくれる存在に囲まれ『この世界には愛がある』と証明している人間がいる。ネガティブが止まらないときは、私という存在に会うことを選択肢に入れてくれると、とても嬉しく思います」 包丁で床を滅多刺し、虐待されるのが日常…ヤクザの娘からアイドルになった女性が告白する「シェルター生活」