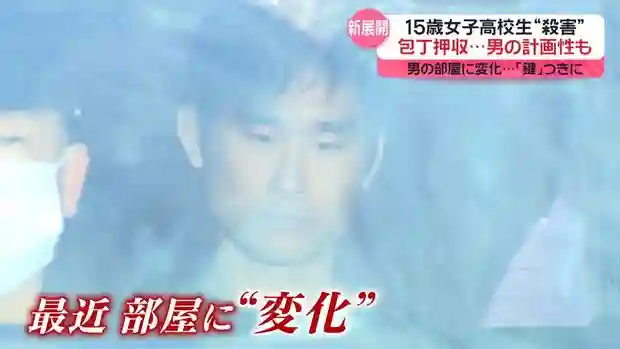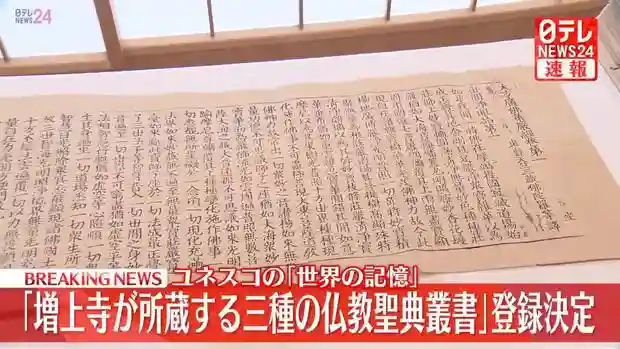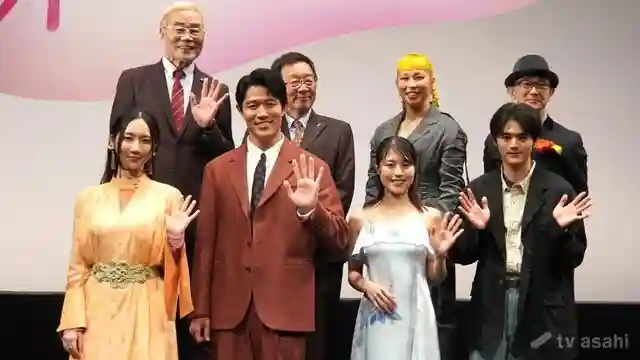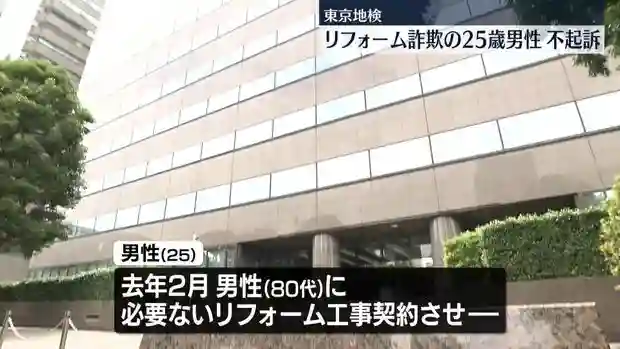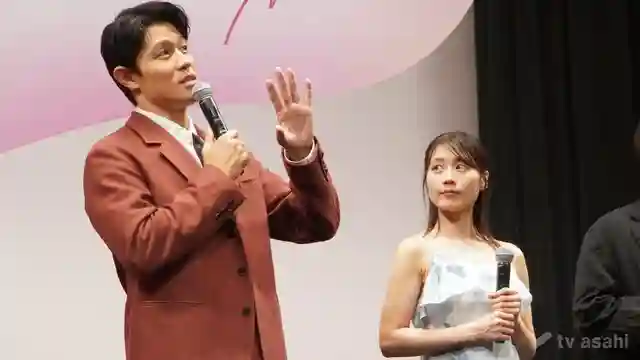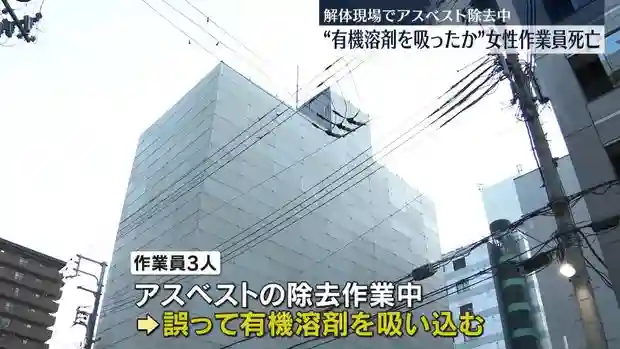地政学リスクの高まり、米中対立の激化に加え、SNSによる情報過多や偽情報の流通、スパイによる技術流出などによって、ビジネス環境の先行きがますます読めなくなってきた今、「インテリジェンス」の必要性を疑う企業はないだろう。しかし、企業にとっては新しい概念だけに、それを社内で担う人物にはどんな能力や適性が必要とされるのか、きちんと定義されていない。インテリジェンスの現場とコンサルティングファームで経験を積んだ元警視庁公安部捜査官の稲村悠氏による新著『企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法』(講談社+α新書)から、「インテリジェンス・サイクル」に必要な人材と能力をご紹介しよう。(4回連載の第3回) 『企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法』 (講談社+α新書) 「「とりあえず調べておいて」が蔓延する職場の悲劇」より続く インテリジェンス担当者に必要な能力 インテリジェンス・サイクルにおいて、実際に情報を収集・分析し、インテリジェンスを意思決定者に報告するのがインテリジェンス担当者です。企業によっては経営企画部門にインテリジェンス担当を置くケースもあれば、インテリジェンス担当部門として経済安全保障室のような専門チームを設けている場合もあります。この担当者が高い専門性を発揮しなければ、意思決定者がいくら明確な問いを立てても、適切な情報が集まらず、分析にも不備が生じることになります。 インテリジェンス担当者には、インテリジェンスに関する多くの素質が求められます。 ●情報収集能力 現代の環境では、インターネット上の公開情報や、SNS、各種有償データベース、さらには業界の専門家や学界の研究者とのネットワークなど、情報源は非常に多岐にわたります。インテリジェンス担当者は、これらの情報源を駆使して効率的に必要なデータを収集できなければなりません。ある新興国への進出戦略を検討する場合、現地政府の公表統計やローカルメディアのニュースサイト、専門調査会社のレポートに加え、SNSのリアルな声を拾うといった、多層的なリサーチが求められるでしょう。さらに、必要に応じて在外公館や業界の有識者へのインタビューを行うなど、オフラインの調査手法も重要になります。そうした幅広い情報源の選択肢を把握し、状況に応じて使い分ける柔軟性が鍵を握ります。 しかし、情報源を知っているだけでは不十分で、情報の入手に関するコスト・信頼性・網羅性などを総合的に考慮できる能力が必要です。高額な国際情勢レポートを購読する必要性を判断する際、そのレポートがどの程度ダイレクトに経済安全保障上の懸念に応えるか、そもそも信頼できる調査機関か、といった検討が求められます。リソースが限られている企業ほど、この判断が成果を大きく左右するでしょう。 ●処理能力 多様な情報源にアクセスできるとしても、情報の量が膨大になりすぎているため、すべてに目を通すのは事実上不可能です。そこで、意思決定者が提示した情報要求を軸に情報を取捨選択し、時には情報を統合し、分析の優先順位を決める能力が求められます。たとえば、「競合企業Xの広告キャンペーン実績を調べたい」という問いがある場合、まずは直近1年間の広告出稿媒体とその費用対効果を最重点で調査し、過去5年分の長期トレンドや他社比較は次のフェーズで検討するといった段取りを組むことが考えられます。こうした計画を明確に立てないまま、「ありとあらゆる情報を集めよう」としてしまうと、時間がかかるうえに資料の山に埋もれ、結局要点が見えなくなる危険性が高まります。そこでやはり要求されるのが、「問いを立てる力」なのです。 その仮説が間違っているのでは? さらに、誤った前提の情報要求に対して疑問を呈し、必要に応じて修正を働きかける「チャレンジ精神」も重要です。日本企業にしばしば指摘される「揉め事を嫌い、前提を疑わずに指示に従う」傾向を乗り越えるには、担当者側が積極的に声を上げる文化を育む必要があります。時には、「情報要求自体が誤った仮説ではないか?」という問いさえ持つことも重要なのです。 また、情報の鮮度にも敏感でなければなりません。特に変化が激しい現代では、状況が数ヵ月で一変することもあります。「どの情報をリアルタイムで更新すべきか」「どの部分は長期的な傾向を見れば十分か」を見極める能力が求められます。これを踏まえて取捨選択のプロセスを管理し、意思決定者のスケジュールに合わせて必要最低限の情報を確実に入手・整理する能力が、インテリジェンス担当者の真価を発揮するところです。 情報を収集し、処理するだけでは不十分です。それが何を意味し、どのような示唆をもたらすのかを論理的に示す力が要求されます。とある国の特許情報を調べたとしても、ただリストを並べるだけでは経営者は判断できません。そこから「この技術領域に注力しており、能力を獲得した後に、他国(私たち)の締め出しが見込まれる」といった仮説を導き出し、そのリスクと対処案を提示するところまで踏み込む必要があります。業界知識や情報要求に関する領域情報といった各情報を高いレベルで統合する能力が求められます。 また、先の意思決定者にも要求されたように、批判的思考によって、情報要求自体の適切性や自身の分析についても問いを設定していくことが求められます。 ●成果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力 インテリジェンス担当者が発揮すべき重要な能力として、コミュニケーション能力を挙げることができます。どれほど優れた分析結果を導いていても、意思決定者がその内容を短時間で正しく理解できないのであれば、インテリジェンスの価値は大幅に損なわれます。一般に経営層は多忙を極め、かつ多くの情報にさらされています。長い報告書や専門用語にまみれたレポートをじっくり読む余裕がないことが考えられます。そこで、ポイントをきわめて簡潔に示し、詳細データや根拠は別途参照できる形に整備するといった工夫が必須です。 また、質疑応答の場では、意思決定者からの「この数字の根拠は?」「過去事例と比較するとどう違う?」といった質問にも迅速に答えられるよう、ストックしている情報やデータを構造化・整理して準備しておく必要があります。優秀なインテリジェンス担当者ほど、意思決定者が疑問を持ちそうなポイントを事前に想定し、準備を整えているものです。 情報の優先順位を付けるためのフレームワーク インテリジェンス担当者は、限られた人員・時間・予算を有効に活用しなければなりません。扱うテーマが多岐にわたる場合、「すべてに完璧に対応する」ことは事実上不可能です。そこで有効になるのが、優先順位付けのフレームワークです。たとえば、以下のフレームワークが挙げられます。 ・インパクト×発生可能性 まずは、リスクや課題が実際に発生したときのインパクトの大きさ(企業業績や社会的信用への影響度、法令・レギュレーション違反リスク、レピュテーションリスクなど)と、それがどの程度の確率で起きるのかを評価し、優先順位を付けます。大きな不祥事に発展する可能性があるテーマは最優先で情報収集を行い、比較的マイナーな事例や緊急度の低い課題は後回しにするといった具合です。これは非常に一般的な「リスク・マトリックス」と呼ばれるもので、珍しいものではありません。 ・時間軸×組織スケジュール 経営会議やプロジェクトのマイルストーンなど、意思決定のタイミングから逆算して「いつまでに、どの情報が必要か」を決めます。長期的な調査が必要なテーマは早めに着手し、意思決定までに必要最低限のアウトプットを間に合わせるように計画を作成します。 ・コスト×効果 有償データベースの購読や外部コンサルタントへの依頼など、コストが高い手段を使う場合は、その投資によるリターンを評価します。リターンについては、金額換算によるリスク回避だけでなく、「将来の経営判断や事業戦略をどれほど正確かつ効率的に行えるか」という質的な面も含めて判断するとよいでしょう。 ・複数の情報要求×整合性 社内で複数のプロジェクトが同時並行で情報要求を出してきた場合、共通するデータソースや分析手法があれば横串を通し、一度の調査で複数案件に対応できるようまとめてしまうなど、効率を高める工夫が必要です。同じ情報基盤を活用してスピードアップを図ることで、担当者の負荷を軽減するだけでなく、成果の一貫性も保ちやすくなります。 このような優先順位付けを明確にしておくことで、限られたリソースの中でも重要度と緊急度の高いテーマに集中し、意思決定者への成果物を迅速かつ的確に提供できるようになります。 インテリジェンス担当者を支援する取り組み また、インテリジェンス担当者が効率的にリサーチ・分析を行うには、意思決定者がバックアップとして体制面やツールを整備することが大切です。たとえば、以下のバックアップが有効です。 ・情報共有プラットフォームの導入 企業内ポータルやクラウドベースのナレッジ共有システムを導入し、各部門からの情報提供とインテリジェンス担当者の成果物を一元管理します。必要なニュースフィードやレポート情報を自動収集し、担当者が注目すべき項目をピックアップできる仕組みを備えると効果的です。社内のコミュニケーションツールとも連携させ、必要な情報へアクセスしやすい環境を整えましょう。 ・分析支援ツールの活用 オシントやSNS分析を自動化するツールを用いることで、人手による単純な情報収集作業を省力化できます。あらかじめ設定したキーワードをもとに、ニュースやSNS投稿を自動的にクローリング・要約してくれるソフトウェアを導入すれば、インテリジェンス担当者はより高度な分析に時間と労力を振り向けられるでしょう。 ・部門横断連携体制の整備 経営企画部門・法務部門・IT部門・現場部門などが連携できるワークフローを整備し、重要テーマの情報共有や意思決定プロセスがスムーズに進むようにします。新規市場への参入リスクを評価するときは、法務が法規制面を、ITがシステム対応面を、現場が実務上の課題をそれぞれ提供し、それらをインテリジェンス担当者が統合して経営層へレポートする、という流れを明確にしておくとよいでしょう。 ・人材育成と外部ネットワークの活用 ITツールだけではカバーしきれない専門知識や生の情報を得るために、外部ネットワーク(行政機関、大学研究者、業界団体、シンクタンクなど)を活用しやすい体制を作ることも重要です。意思決定者が予算や契約の面で後押しをすることで、担当者は必要なときに専門家からの助言や追加データを迅速に得られるようになります。 こうした体制整備やITツールの導入によって、インテリジェンス・サイクルを効率的に回しやすくなります。結果として、企業が抱えるさまざまなリスクや課題に迅速かつ的確に対応し、戦略的な意思決定をサポートできる土台が整うのです。 情報を部署に閉じ込めず、それでも機密を守れる組織をつくる