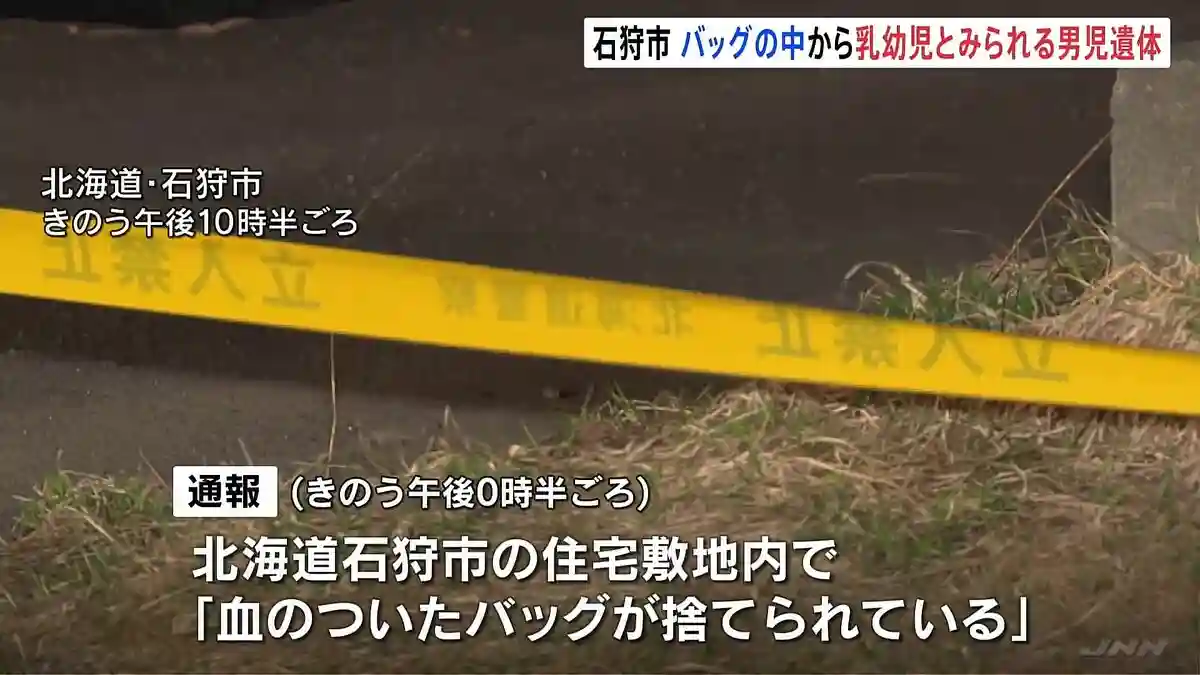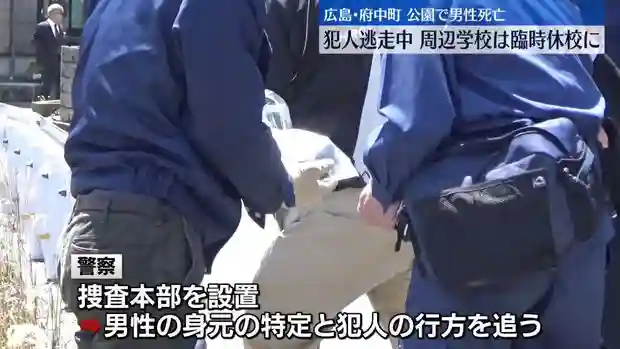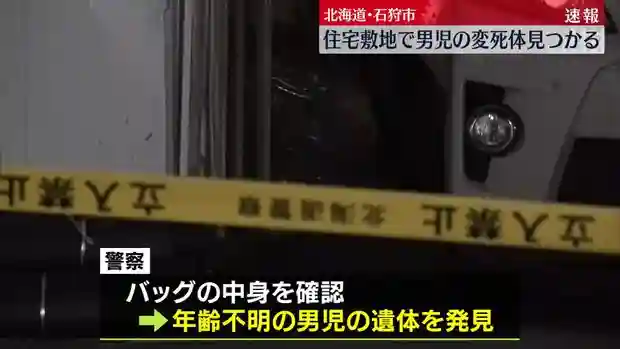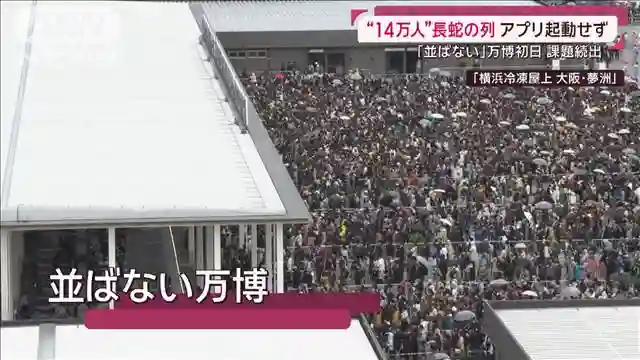物価高騰が続く昨今、外食産業は大きな岐路に立っている。株式会社リクルートの外食市場に関する調査・研究機関『ホットペッパーグルメ外食総研』が実施した最新調査によると、消費者の多くが日常的な外食に「1000円の壁」という心理的ハードルを感じていることが明らかになった。この「壁」は、消費者が外食において1,000円以上の価格に対して抵抗感を示す現象として、業界内で広く認知されている。 「1000円の壁」を一番感じないメニューとは ホットペッパーグルメ外食総研の田中直樹氏によると、この「1000円の壁」という概念は2010年代後半頃からSNSやメディアで注目され始めたという。その背景には、小麦や豚肉などの原材料価格の高騰と、飲食店の人件費上昇がある。 特に問題となったのは、「中華そば一杯に1,000円も払うのか?」という根強い消費者の相場観と、値上げせざるを得ない飲食店側の現実とのギャップだ。このギャップが顕在化し、SNS上で議論されるようになったことが「1000円の壁」という概念の始まりであった。 ホットペッパーグルメ外食総研が、全国の20代〜60代の男女1,035人を対象に行った調査では、ピックアップした30種類のメニューのうち、実に26メニューにおいて4分の3以上の人が1,000円以上の支払いに抵抗を感じているという結果が出た。 先に、「外食をする際、事前情報なしで初めて訪れた飲食店で1,000円以上であっても悩まず注文できる、いわゆる1,000円の壁を感じない」と回答した人の割合が高かったメニューを見ていこう。 1. 海鮮丼:43.4%の人が1,000円以上でも抵抗を感じない 2. とんかつ:31.7%の人が1,000円以上でも抵抗を感じない 3. パスタ:28.9%の人が1,000円以上でも抵抗を感じない 田中氏は海鮮丼が「壁を感じない」割合が高い理由として、「消費者に高価格相場があるかどうか(コスト面)」と「何をもって価格に相応しいと判断するか(パフォーマンス面)」の2軸を挙げ、「海鮮丼は普段あまり食べるものではなく、高い価格でも抵抗感が少ない」と説明する。ただし、詳しくは後述するが、年代によっても「相場」の違いが存在する。 「とんかつ」と「かつ丼」の価格感覚が違うワケ 一方で、「1000円の壁」を感じないと答えた人が少ない(=1,000円以上の価格に抵抗を感じる)メニューとしては次のようなものが挙げられる。 ・ラーメン:76.6%の人が1,000円以上に抵抗を感じる ・かつ丼:84.0%の人が1,000円以上に抵抗を感じる ・カレー:82.8%の人が1,000円以上に抵抗を感じる 特に「1000円の壁」議論の中心的な存在である「ラーメン」については、約8割の人が1,000円以上の支払いに抵抗を感じているという結果が出ている。多くの消費者にとって「ラーメン」は依然として「1,000円以下」であるべきという価格感覚が根強く残っているようだ。 今回の調査で特に興味深いのは、同じ食材を使っていても料理の形態によって価格感覚が大きく異なる点である。「とんかつ」単品と「かつ丼」の間にある価格許容度の差がその典型例だ。 調査結果によると、「とんかつ」については約32%の人が1,000円以上でも抵抗を感じないと回答しているのに対し、「かつ丼」については約16%しか「壁を感じない」と回答していない。同じ豚かつを使った料理でも、丼にすると価格に対する抵抗感が約2倍に増えるのである。 この現象について田中氏は、「『とんかつ』と『かつ丼』の決定的な違いは、とんかつは専門店で食べるイメージが強いのに対し、かつ丼は大衆食堂や定食屋のメニューというイメージが強く、家庭でも比較的簡単に作れる日常食という位置づけがある」と分析する。 さらに、「とんかつは単品ではなく定食で提供されることが多く、豚汁やキャベツ、ご飯などが別々に味わえる。盛り付けやボリューム感も演出しやすく、差別化しやすい点も価格許容度に影響していると思う」と付け加えた。 年代差による「1000円の壁」の感じ方の違い 調査によれば、「1000円の壁」は年代によっても感じ方に大きな違いがあることがわかった。田中氏は「例えば現在のZ世代は、自分のお金でラーメンを食べるようになった頃には既に1,000円を超えるラーメンが普通になっていたため、高い価格に対する抵抗感が少ない傾向にある」と世代間の価格感覚の違いを説明する。 調査の年代別データによると、ラーメンについては20代では約30%が「壁を感じない」と回答しているのに対し、60代以上では約18%しか「壁を感じない」と回答していない。つまり、60代以上の方が若い世代よりもラーメンに対する「1000円の壁」をより強く感じているのである。 一方で、興味深いことに海鮮丼については逆の傾向が見られる。20代では約40%が「壁を感じない」と回答しているのに対し、60代以上では約50%が「壁を感じない」と回答しており、この場合は若い世代の方が「壁」を強く感じている。60代以上には海鮮丼の高価格相場が身についているということだろう。 「ハンバーガー」に関しては世代間の差がさらに顕著で、若い人の約75%が1000円の壁を感じないと回答しているのに対し、60代では約16%しか「壁を感じない」と回答していない。田中氏は「若い世代は値が張るグルメバーガーとして認識している一方、60代以上の世代はマクドナルドのようなファストフードのイメージが強いため、この差が生まれているのだろう」と分析している。 「1000円の壁」を越えるための戦略 飲食店がこの「1000円の壁」を越えるためには、どのような戦略が効果的なのか。田中氏は、単なる値上げではなく、消費者の納得感を生み出す工夫が必要だと指摘する。具体例としては、「金沢まいもん寿司」などの回転寿司チェーンの取り組みを挙げる。 「単に美味しい回転寿司というだけでも高いパフォーマンスだが、どこで採れ、いつお店に届いた魚で、と素材ごとの鮮度やエピソードといった要素もパフォーマンスに加わる。結果として1皿100〜200円ではなく500円でも、その価格に対する体験価値を見出せるようにしている」 サービスの演出も重要な要素である。「上ロース肉1,500円を焼肉屋が提供する場合、1枚目の焼き方を店員がちゃんとロースターで焼いて、『女性の方からいきましょうか』などと声をかけるだけで、価格に納得感が生まれる」と田中氏は説明する。 「ストーリー」もまた価格の壁を越えるのには欠かせない。 「例えば新大久保で売られている韓国パンや韓国風ドーナツは、本質的にはパンやドーナツなのだが、『韓国で流行っている』というストーリーがつくことで、高くても買いたくなる効果がある」 SNSの発達はストーリーの伝達に追い風だと、田中氏は続ける。 「静止画だけでなく動画で店内の様子や立地まで含めた体験を共有できるようになり、立地条件の悪いお店でも集客できるようになった。並んでいる様子すらも『並んで食べたという体験の価値』としてSNSでシェアされるようになっている」 「1000円の壁」は今後どうなるか? 物価の上昇が続く中、「1000円の壁」は今後どうなっていくのか。 田中氏は「価格の壁は徐々に右肩上がりにじりじり上昇している。麺類であれば、パスタやラーメンは現時点で平均1,000円前後になっているし、供給側がどんどん価格設定を変えていけば、基準額自体がぐっと上がり、今度は1,000円は当然で1,200円という話になってくるだろう。壁そのものがじりじり上昇する現象は間違いなく起きるだろうと思っている」と予測する。 この価格上昇は業界全体の流れでもある。実際、「食団連(一般社団法人日本飲食団体連合会)」などの業界団体も値上げの必要性を認め、飲食店向けに値上げ告知用のポスターを無料配布するなどの支援を行っているという。 このように日本人消費者が感じる「1000円の壁」が少しずつ上昇していく一方で、海外からの観光客(インバウンド客)にはそもそもこの「壁」が存在しないという興味深い現象がある。田中氏は「インバウンド客にとっての『1000円の壁』は存在せず、むしろ日本の食事は彼らからすると安いと認識されている」と話す。 その背景として、「海外では食事はエンターテイメントの一部として捉えられており、彼らにとっては食べたことのない料理を体験すること自体が価値である。また、海外では日常食でも2,000〜3,000円は普通に超えるし、何より決定的に違うのはチップ文化の有無など、サービスに対してお金を払うという考え方の違いがある」と指摘する。 この違いは外食産業の未来に示唆を与えている。田中氏は「一部の先進的な飲食企業では、こうした海外の文化を取り入れた『投げ銭システム』を導入し始めている」と言うように、新たな価値観を受け入れることが、1000円の壁を越えるためのさらなるアプローチにつながるのだろう。 ・調査概要 調査方法:インターネットリサーチ 調査対象:全国20代〜60代男女(株式会社マクロミルの登録モニター) 有効回答数:1,035件(男性517件、女性518件) 調査実施期間:2024年11月1日(金)〜2024年11月2日(土) 調査機関:マクロミル 「吉野家は有楽町、餃子の王将は荻窪」がひと味違う…⁉飲食店チェーンなのに《他より美味しい店》が生まれるワケ