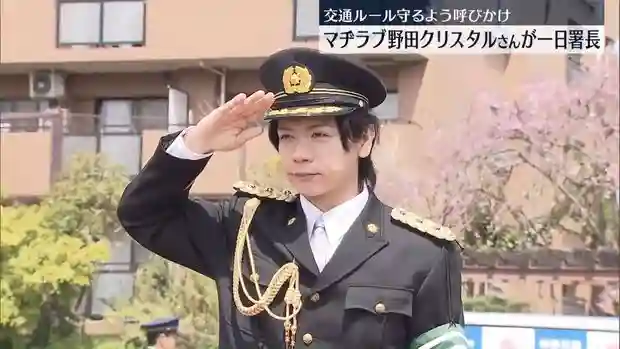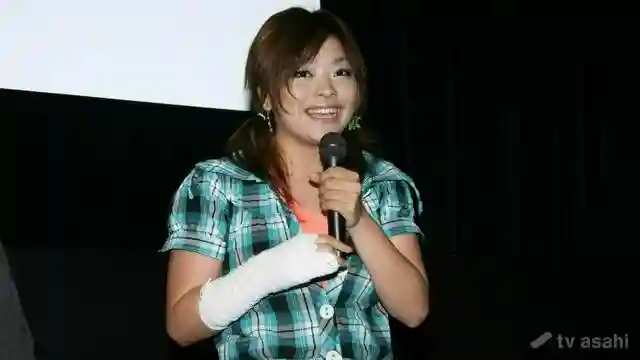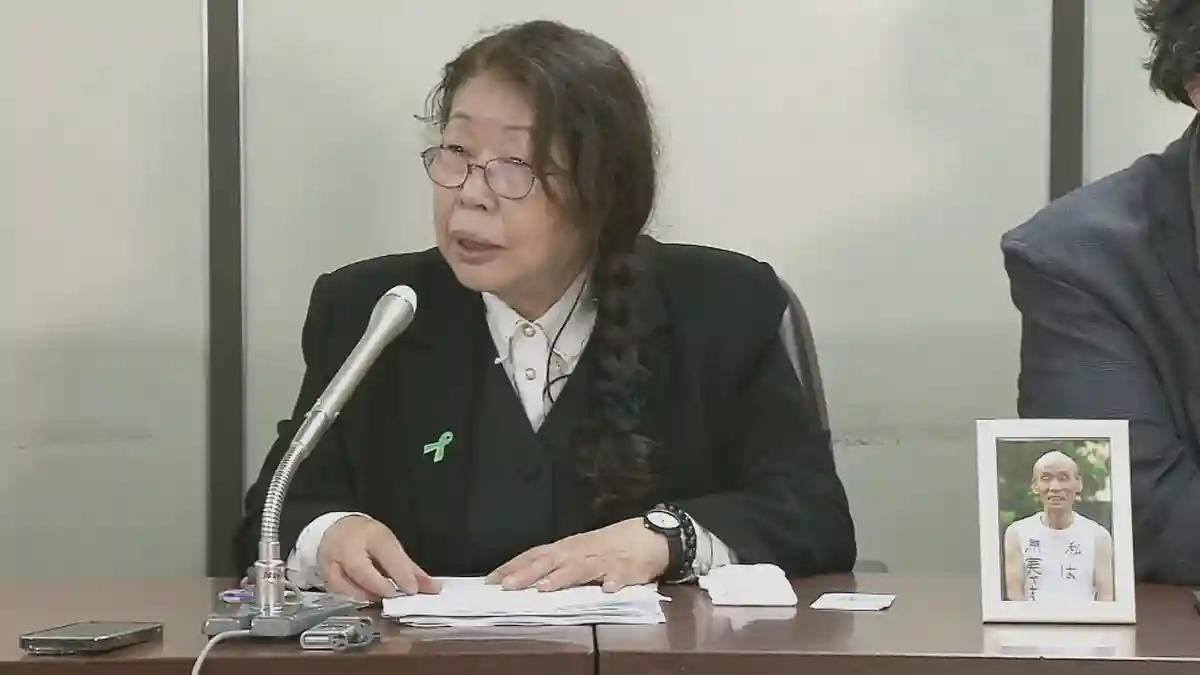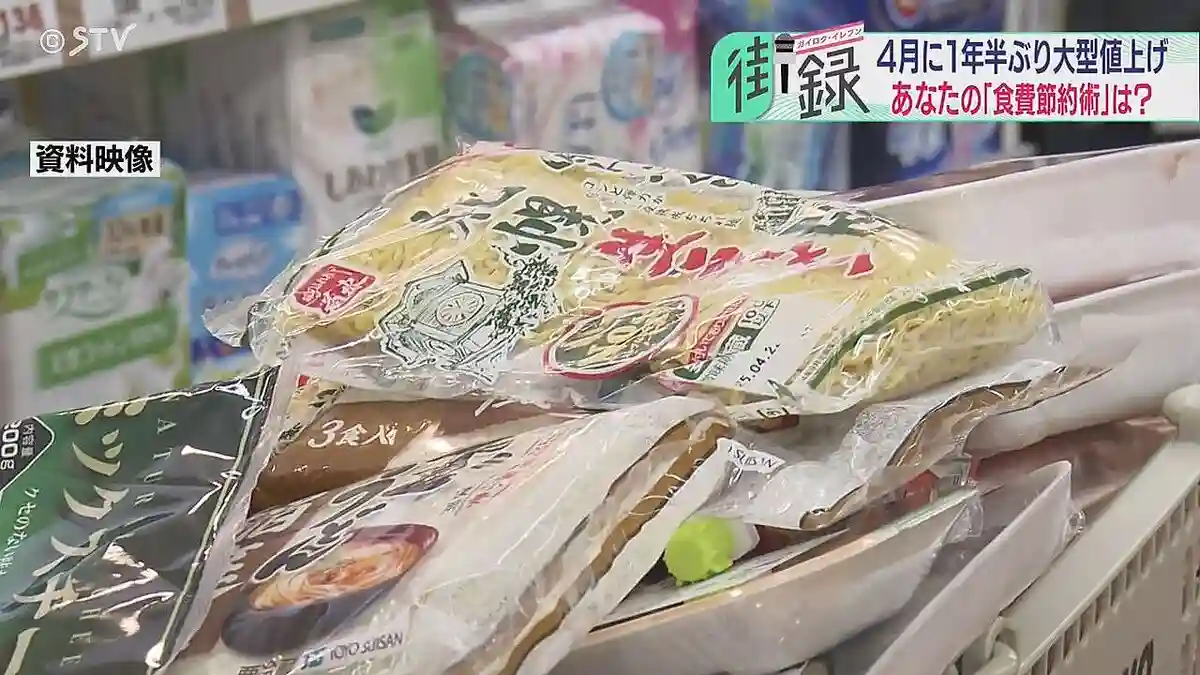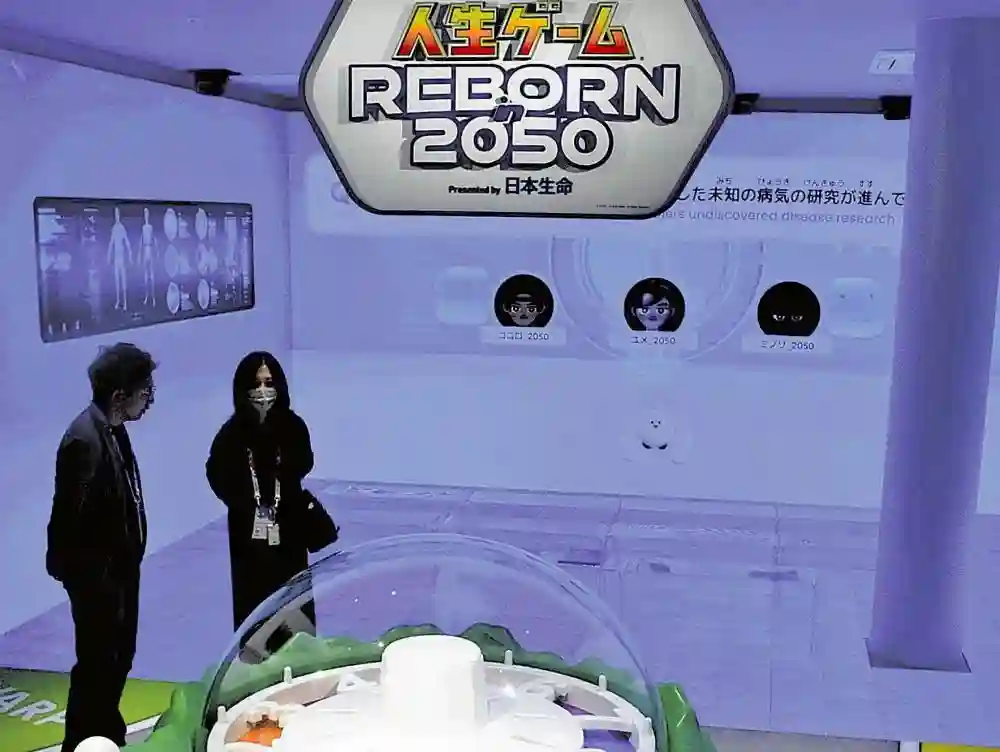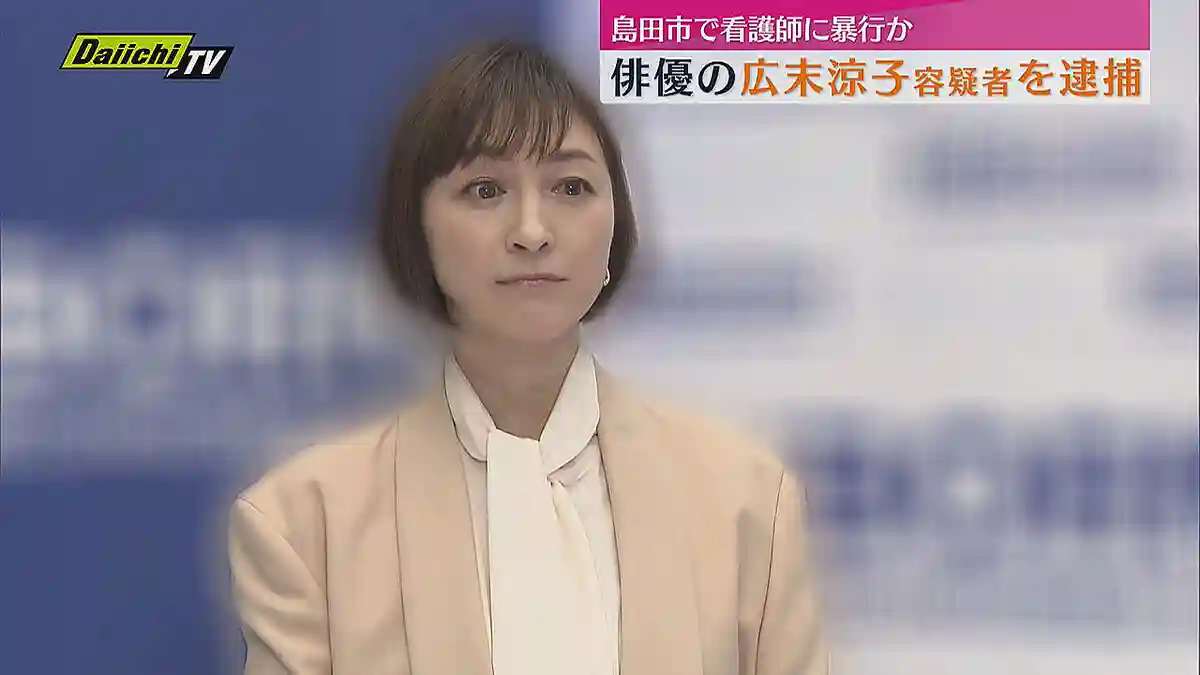汗ばむ陽気が続くと、気になるのが「臭い問題」。たとえ周囲の社員が業務に支障をきたすほど強い体臭でも、本人に自覚がないのがこの問題の難しいところ。ある会社で起きた「スメルハラスメント」騒動の事例をもとに、会社がとるべき具体的な措置を、社会保険労務士の上岡ひとみ氏が考えていく。 本記事の登場人物 村山部長: 35歳。 株式会社Fテクノロジーの総務部長。部下の新谷主任の体臭問題に頭を悩ませている。 新谷:22歳。株式会社Fテクノロジー システム開発部の新入社員。技術力は高いが神経質な性格。最近は業務で徹夜続きだった。自身の体臭について指摘を受け、パワハラだと主張している。 田島課長:28歳。株式会社Fテクノロジー 開発部の課長。新谷主任の体臭問題について村山に相談した。 上岡ひとみ:社会保険労務士。村山がスメルハラスメントの対応について相談した専門家。 *本記事に登場する固有名詞はすべて「仮名」です 本人との面談で確認すべきこと 株式会社Fテクノロジーで起きた「臭い問題」について村山から相談を受けた上岡は、会社としての具体的な対応策を提案した。 「具体的な対応としては、他のハラスメントと同様に通報窓口を設けることが基本です。そして、申告があった際には、本人からのヒアリングを含めた調査をして、具体的な状況に即した再発防止策を検討する必要があります」 上岡は実際の判例も紹介した。 「東京地裁平成20年12月19日判決では、2着の衣類を洗濯せずに着回しており、複数の従業員が悪臭に不快感を述べていた事案で、『執務に差し支える程度の臭いがする』ことを理由に解雇が有効と判断された事例があります。ただし、臭いの問題は本人に自覚がないケースが多く、伝え方によっては本人の尊厳や人格を傷つける可能性がある点に注意が必要です」 上岡はさらに具体的なアドバイスを続けた。 「まず、新谷さん本人と個別に面談し、臭いの原因について心当たりがないか確認してください。臭いの原因が身体から生じる改善が困難なものか、それとも香水や柔軟剤など改善が容易なものかを具体的に把握する必要があります。強いストレスや疾患が関係している可能性もあるため、必要に応じて産業医の面談を勧めることも検討すべきでしょう」 さらに、会社全体の対応として、スメルハラスメントを含む職場環境問題の相談窓口を設置すること、服務規律に「周囲の人に不快感を与えることなく、自身を清潔に保ち、他の従業員に精神的苦痛または不快感を与えないこと、職場の環境を悪化させないこと」といった規定を盛り込むことなども提案された。 臭いの原因は、じつは… 村山は上岡の助言をもとに、新谷との再面談を実施。今回は産業医も同席し、より専門的な視点からアプローチした。 話し合いの結果、新谷は最近の過重労働とプロジェクトのプレッシャーから生活習慣が乱れていたこと、また制汗剤アレルギーがあり使用を避けていたことなどが判明した。 会社側は新谷の働き方の改善(残業時間の削減、休息の確保)を約束。また、社内に休憩室を設け、長時間勤務の社員が身だしなみを整えられる環境も整備することにした。 さらに、全社的な取り組みとして「職場環境改善プロジェクト」を立ち上げ、スメルハラスメントを含む様々なハラスメント防止と対応のためのガイドラインを策定。社員研修も実施することにした。 3か月後、新谷の働き方は改善され、臭いの問題も解消。職場の雰囲気も徐々に回復していった。 「問題の本質は個人攻撃ではなく、互いを尊重しながら職場環境を改善することにあったんですね」 村山は上岡に報告しながらそう振り返った。 「そうですね。ハラスメント対応の基本は、誰もが尊厳を持って働ける環境づくり。スメルハラスメントも例外ではありません」 上岡はにっこりと笑いながら締めくくった。 「今回の件は、明確な基準がない問題でも、個別具体的に丁寧に対応することで解決できることを示してくれましたね。他社の参考にもなる事例だと思います」 心ない人に「マウンティング」されたら使いたい…相手をビビらせる「言い返し」フレーズ