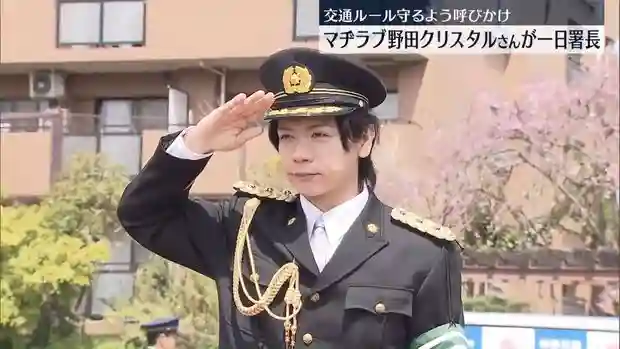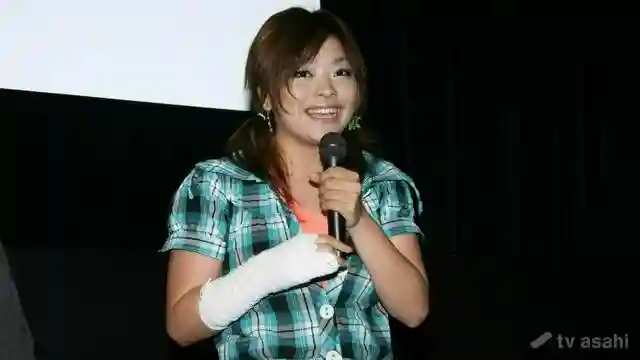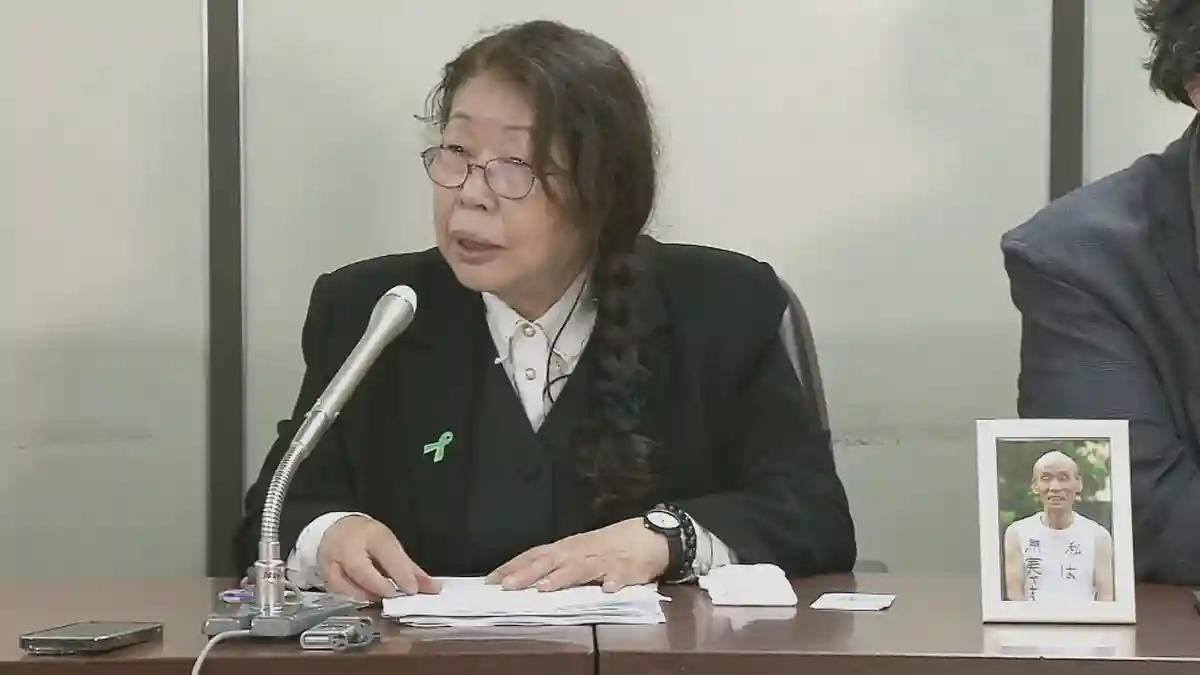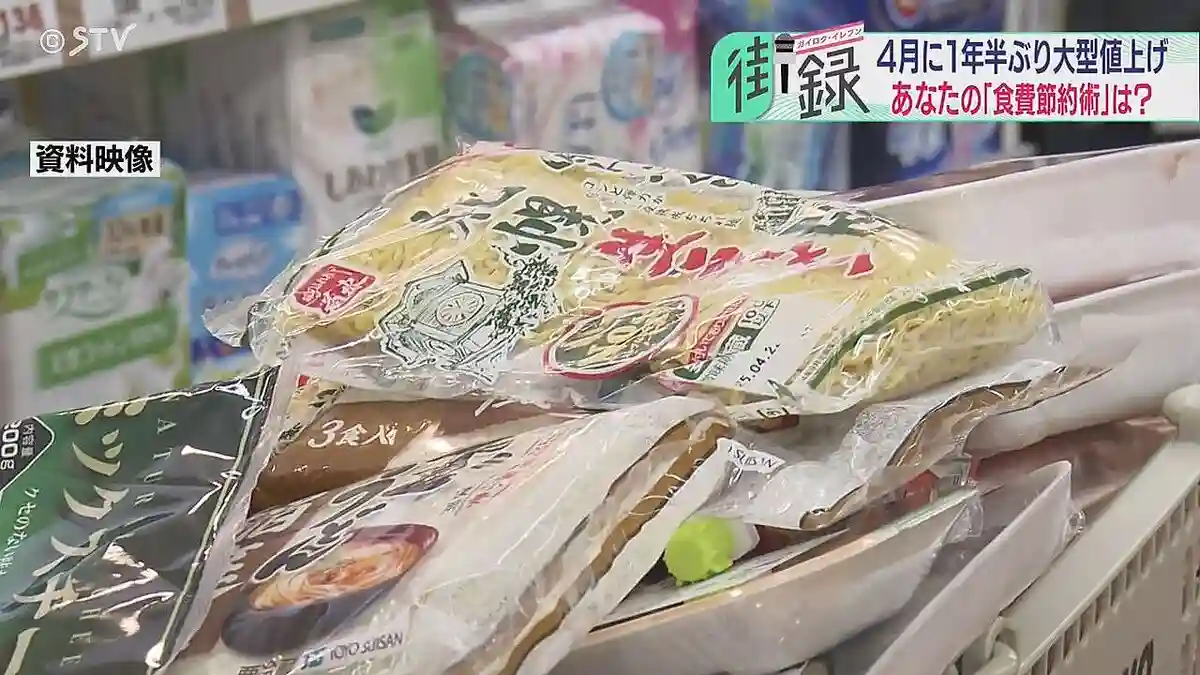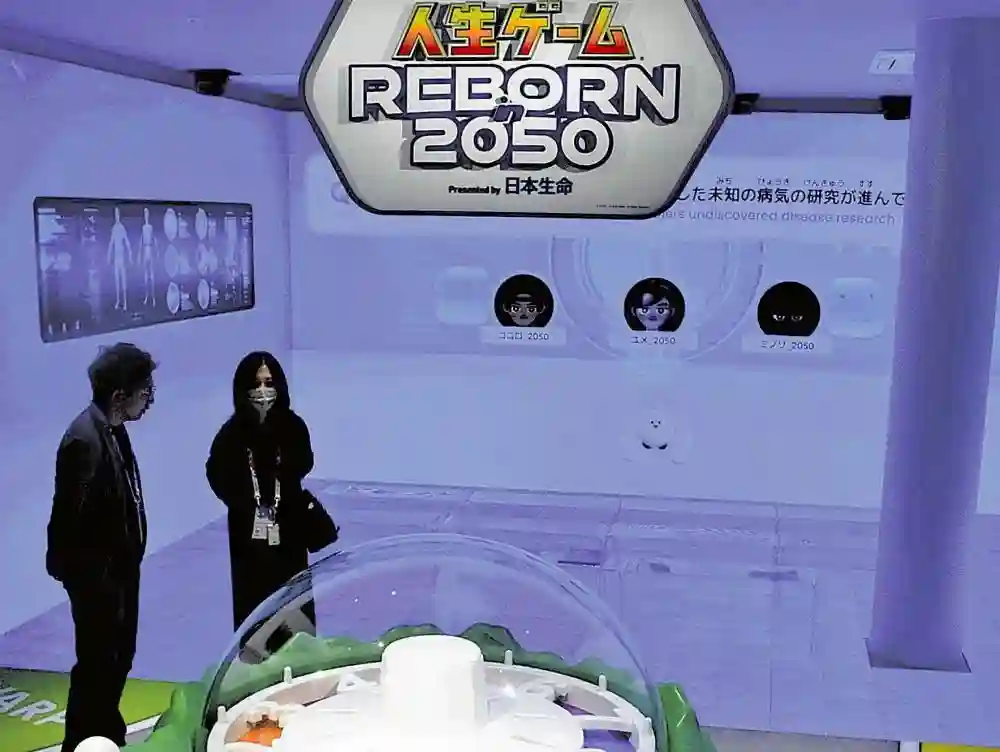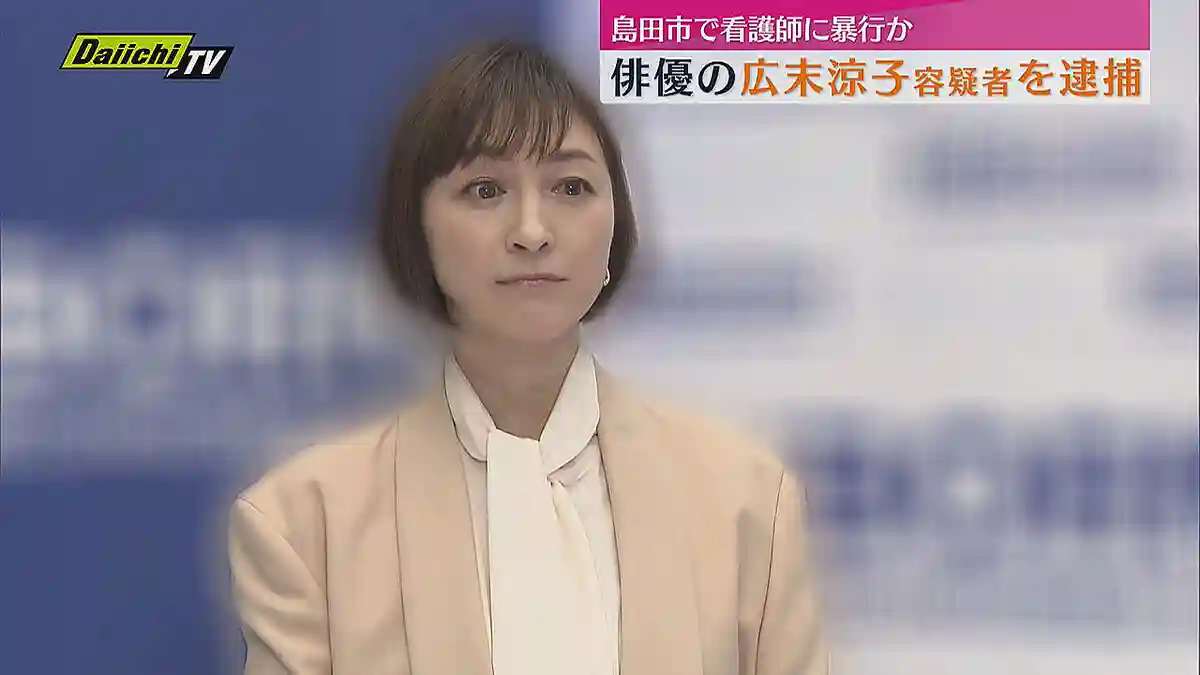「業務の延長線上」における性暴力であったと認められる——元タレント・中居正広氏とフジテレビの女性アナウンサーの間のトラブルは、2025年3月31日に公表された第三者委員会の調査でそう認定された。 中居氏と親しかった編成制作局幹部は、タレントの求めに応じ自社の女性社員を食事会に呼び出すなどの卑劣な行為を繰り返していた。 さらに、女性の異変に気づいたアナウンス部管理職や報告を受けた社長をはじめとする経営陣も「人権問題と捉えることができず」、中居氏への配慮を優先させたすえ「思考停止に陥り、浅い思慮により対応方針を決定した」(報告書)。 第三者委員会の報告に先立つ27日、41年にわたって事実上の経営トップに君臨していた日枝久氏(87)がフジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスの取締役相談役を退任すると発表された。 長年にわたって日枝氏が権力を握った結果、役員をはじめ幹部人事は同氏の意向に沿った形で行われ、パワハラ・セクハラなどの問題行動があった人物が幹部に登用されるなど社内のモラルは崩壊していたと言っていい。 今回の中居氏と女性アナウンサーのトラブル、そして事後処理の悲劇的なまでの誤りは、その腐敗が顕在化したもの以外の何物でもない。 フジテレビを根深くまで腐らせた「日枝支配」は、どのように完成したのか。 1992年の「鹿内宏明会長排斥クーデター」と、2005年の「ライブドア事件」を詳細にレポートしたノンフィクションの傑作、『メディアの支配者(上)』『メディアの支配者(下)』(中川一徳・著)から、一部を抜粋する。 舞台は、1992年7月21日、産経新聞社の定例取締役会である。 あまりの急展開 すべて打ち合わせどおりだった。澤(昭義)と近藤(俊一郎)、二人の専務が口火を切り、一気に勝負をつける。それが入念に組み立てられたシナリオだった。 副社長の小島宣夫は、前触れもなく緊迫した場面を呆然と眺めていた。 〈話はやっぱり本当だったのか〉 取締役会の直前、役員の一人から「実は今日、会長を不信任します」とだけ耳打ちされていたのだ。開会時間が迫り詳しい話を聞くことはできなかった。 驚きはしたものの、元来、社内政治に疎い小島にとっては、なぜこういうことになるのか見当もつかなかった。 鹿内宏明(フジサンケイグループ議長)もまた、事態のあまりの急展開に内心驚愕を隠せなかった。しかし、動揺を振り払うように役員を見渡し、努めて平常心を保とうとした。 「その前に、本日の議案ですが、株式譲渡承認の件と業務報告の件と、この二題だけでありまして、いまの役員の件については議案にございませんので、事前に議案にないものは取締役会議で論議することはできないものと思います」 すかさず提案者の澤が反論する。 「ただ、商法二百六十条によりますと、各取締役が提案権を持っています。したがいまして、緊急動議として提案をいたしたいと思います」 「会社を首になるかもしれない」 ここで、代わりの議長に指名された社長の羽佐間(重彰)が野太い声で初めて口を開いた。 「では、ただいまの提案につきまして取締役のみなさんのご意見を伺いたいと思います」 左隣に座る羽佐間が動議に沿うような進行を始めたことで、宏明は、羽佐間もまた、澤、近藤の二役員と示し合わせていることを思い知らされた。 近藤は昨夜、密議を交わしたホテルにそのまま泊まり込んでいる。決行の日がついに来たかという思いでなかなか寝付けなかったが、朝方になって妻に電話した。 「今日、ひょっとするとおれは会社を首になるかもしれない。路頭に迷うことになるかもな」 事情を知らない妻は、何を馬鹿なことを言っているのかと取り合わない。相手にもされなかったことで、近藤はかえって不安な気持ちが消えていくのを感じた、という。 とはいっても、何も起きなければ、来年には専務定年となる年齢を迎えることも事実だった。同期の澤もそうだし、羽佐間にしても来年、内規で定まった社長定年の年齢に達する。そうした定年間近の三人が、そろって解任の口火を切ったのである。 役員会議室には、ただならぬ気配が立ち込めている。取締役会が始まって、まだ三分と経っていない。 社長の仕切りに不意をくらった宏明が「ちょっとお待ちください!」と声を張り上げた。だが、「異議なし」という役員の声が会議室に響く。 それでも宏明の必死の抵抗は続いた。 「役付きの変更は事前の議題提出なくしてできるわけではないので、これは次回の議題としてなされるべきものと思います」 発言を無視して決議に突き進む羽佐間 しかし羽佐間は、宏明の発言を無視して決議に突き進んだ。 「商法の第二百六十条によりまして、私がただいまの提案についての議長を務めさせていただきたいと思いますが、これについて賛成の方、ご起立願います」 過半数を超える十数名の役員が一斉に立ち上がるのを確認して、羽佐間が続ける。 「鹿内宏明氏が我が社の代表取締役会長職の地位にありますが、会長及び代表取締役が不適任であるから解任決議されたい、との提案です。何か質問その他ございますか」 「ございます」 すでに多数が示し合わせていることは明らかで、敗色は濃くなりつつあったが、宏明は抵抗を止めるわけにはいかなかった。 「採決の前に、そういう強引なやり方ではなく、納得する形で進めるべきだと思います」 だが、羽佐間はいよいよ「仮面」を脱ぎ捨て、問答無用と切り捨てた。 「私は、しかし、いま商法に決められたことによって議長になりました。したがって、現在の鹿内氏の会長及び代表取締役解任決議について賛否を問います」 宏明はなおも「議題として認められない」と取締役会規則に則った筋論を繰り返したが、羽佐間によっていとも簡単に棚上げされてしまう。 「と、現在、鹿内氏は言っておられますが、これについての正否は後ほど法的に処理したいと思います。ですが、ただいまの役員並びに出席数を総務部長、あるいは秘書室長、確認願います」 たしかに商法では、各取締役には提案権がある。だが、一方で産経新聞の取締役会規則には、議案は事前に提出されなければならないと定められていた。こと産経新聞の場合は、事前提出されなかった議案の決議については法的有効性で論議の分かれるところなのだ。 異様な事態が進行しつつあった。法的に問題があろうがなかろうが、ともかく先送りにして採決だけ急ごうというのだ。 「国民の42万人が死亡するかもしれない」…あのとき、コロナ8割おじさんが犬笛を吹いた理由《話題沸騰「奔流」の読みどころ》