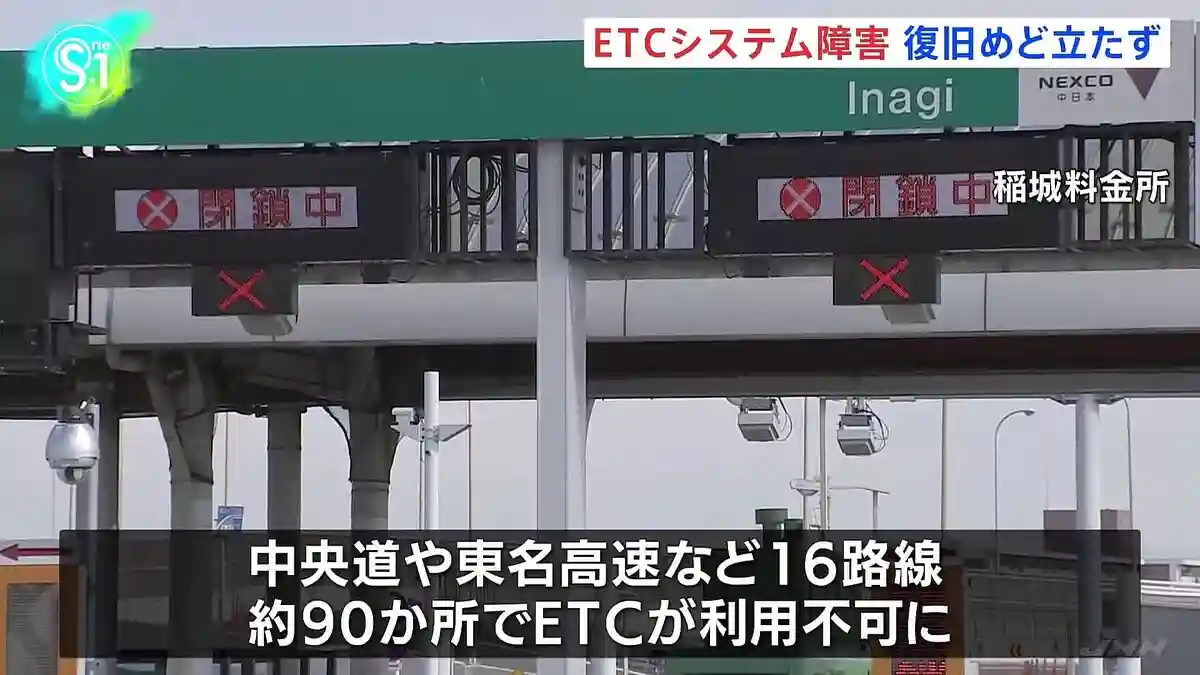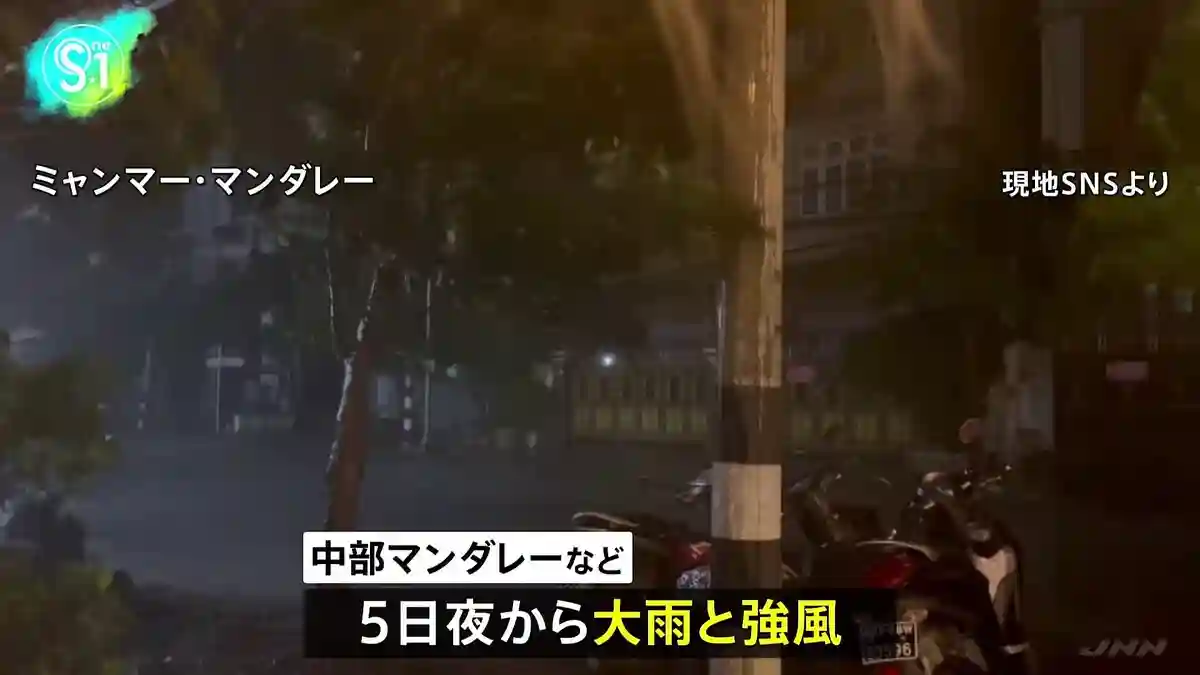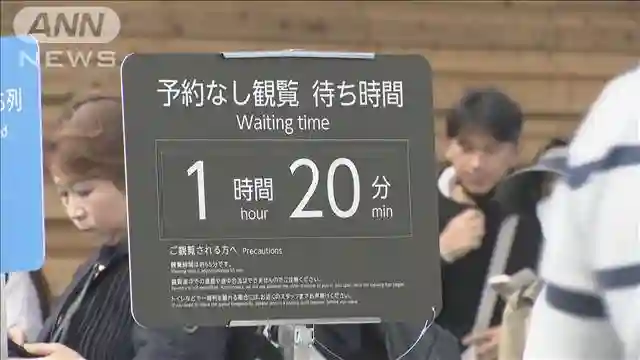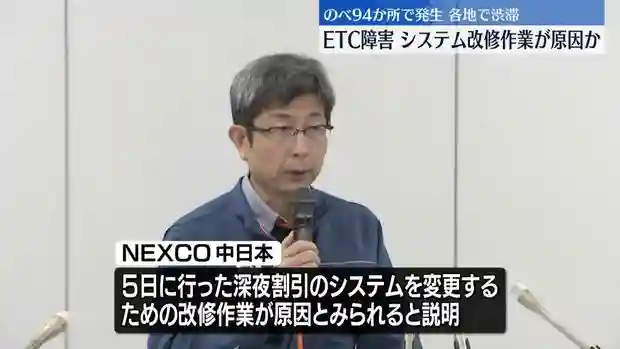顧客から理不尽な要求などを突きつけられるカスタマーハラスメント(カスハラ)の北海道防止条例が今月1日、東京都、群馬県などと並んで全国で初めて施行された。 道内では施行に合わせてカスハラ対策を導入する企業や自治体が増えつつある。機運の醸成は進むのだろうか。 「自身が被害者や加害者になっていないか確認を」 「カスハラ対策は個人ではなく組織の問題。カスハラを許さないという明確な姿勢を打ち出すことで救われる人がいる」 3月23日、留萌市内で開かれた消費者向けのセミナーで、北海道勤労者安全衛生センター(札幌市)の斉藤勉さん(66)は力説した。セミナーは道条例の制定を受けて留萌消費者協会などが主催した。斉藤さんは約60人を前に、条例の内容を説明しながらカスハラの定義を理解し、自身が被害者や加害者になっていないか、確認してほしいと訴えた。 参加した留萌市の会社役員の女性(55)はかつてカスハラ被害に遭ったという。「社内研修を通じて社員に条例や対応の方法を伝えていきたい」と語った。 カスハラ対策「人手確保の追い風に」 道条例は2024年11月、議員提案により成立した。カスハラを「客からの要求などが社会通念上不相当なもので、従業者の就業環境が害される行為」と定義し、そうした行為を「行ってはならない」と禁止を明文化。事業者には対策への協力や、防止に主体的に取り組むことを責務だと規定した。罰則規定はないため、実効性への課題が指摘されている。 道内では留萌消費者協会のような団体や企業でカスハラ対策に向けた動きが広がっている。 道内スーパー大手のアークスグループ(札幌市)は24年12月、対応基本方針を策定。商品の価格より高額な代金や解雇の要求など具体例を挙げて従業員に周知し、相談・報告体制を整備するとした。担当者は「従業員からカスハラの声は多く、安全を守るためでもある」と語る。 道内バス大手の北海道中央バス(小樽市)も今年1月、対応の基本方針を公表。担当者は「カスハラ対策を通じて、(人員不足の)運転手確保の追い風になれば」と話す。 市町村でも同様の動きが進む。 紋別市は1月、市の正規職員や会計年度職員約400人を対象に調査を実施。回答した約150人のうち、半数以上の77人が市民などからカスハラ被害を受けたとした。市は近く対応指針を策定する。 函館市は3月に基本方針を公表し、職員向けのマニュアルを今月1日から施行した。市によると、業務中に市民から土下座を要求されたり、長時間拘束されたりする例があったという。担当者は「市が指針を作ることで、市内企業のカスハラ対策につながれば」と期待を寄せる。 道は25年度、道内の事業者などを対象に調査を実施してカスハラの実態を把握するほか、札幌市や函館市、旭川市など道内6か所でセミナーの開催を予定。カスハラに関する専用のホームページを開設した。道雇用労政課は「実態調査や道議会への報告などにより、抑止力につながる」としている。 氏名公表の自治体も…三重県桑名市 カスハラの防止条例制定の動きは全国に広がっている。地方自治研究機構(東京)によると、北海道、東京都、群馬県、同県嬬恋(つまごい)村、三重県桑名市で4月1日に条例が施行された。 このうち4自治体はカスハラをした人物への罰則や氏名公表などの措置は設けていない。一方、桑名市は悪質な場合、専門家による審議や警告などの手続きを経てカスハラをした人物の氏名を公表するとしている。このほか、愛知県、和歌山県、長野県松本市なども条例の制定を目指している。 北海道大の駒川智子教授(労働社会学)は「自治体レベルで条例の制定が進んでいるのは、国を動かす意味でも重要だ。カスハラ対策は本来、国が取り組むべき課題で、社会全体でカスハラを許さない風土の醸成が期待される」と語る。