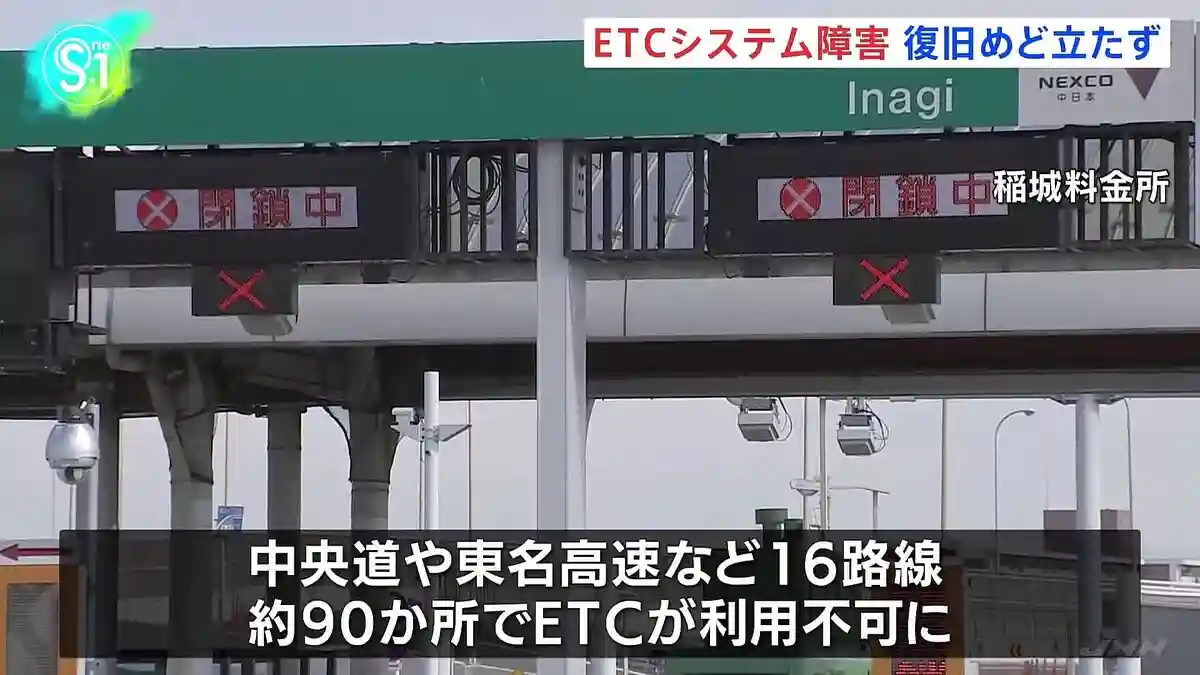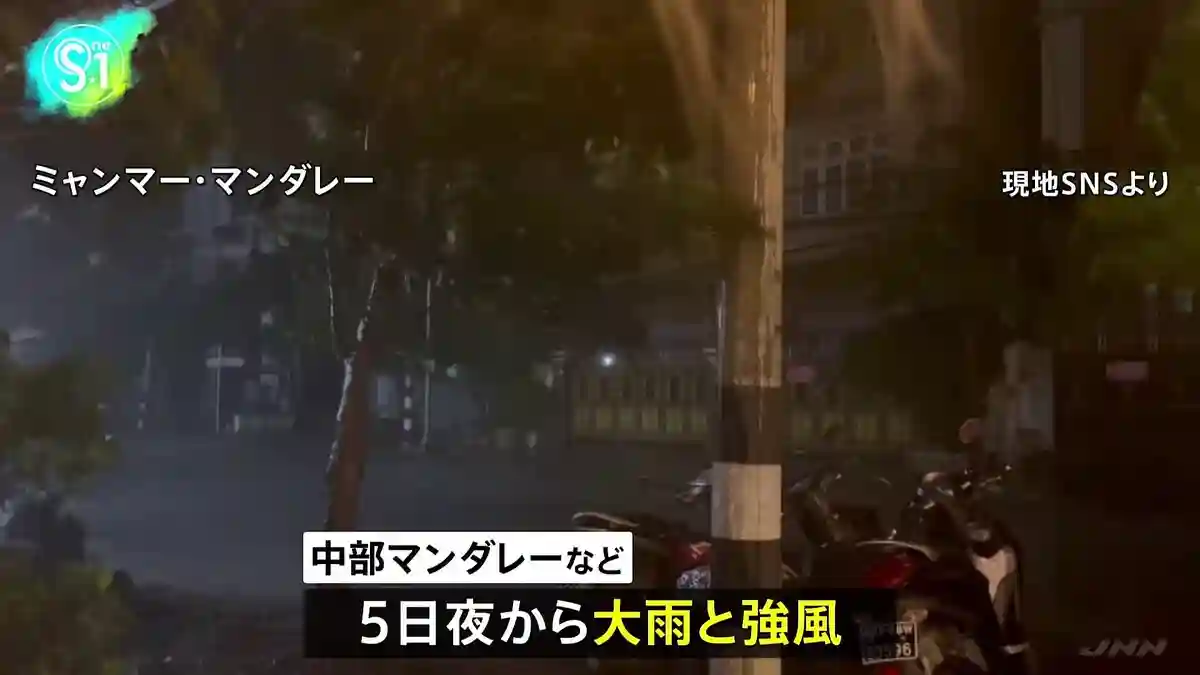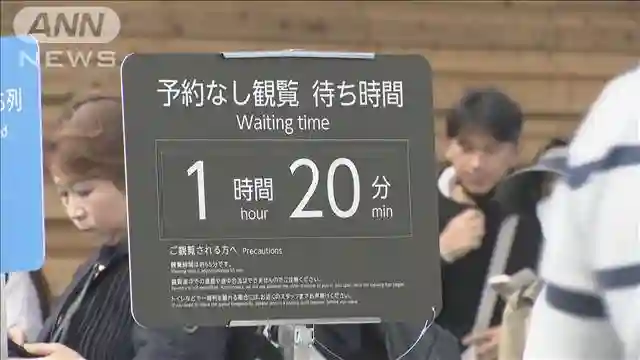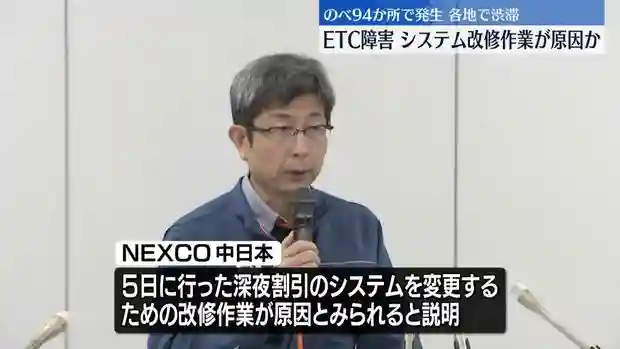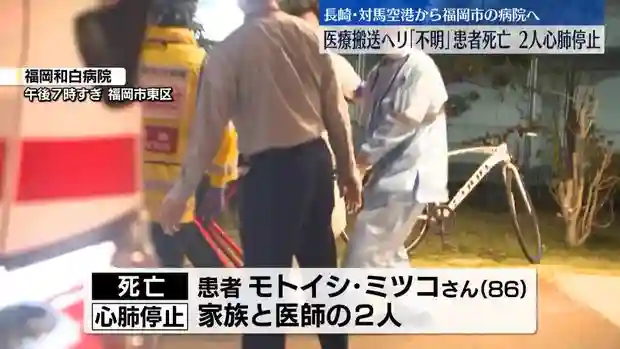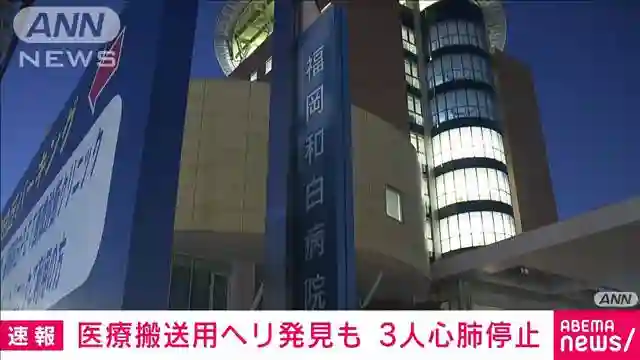明らかになった盲目の高利貸しの実態 吉原を代表する女郎、五代目瀬川(小芝風花)を1,400両(1億4,000万円程度)もの大金で身請けした盲目の富豪、鳥山検校(市原隼人)。そのあまりに豪勢な生活を支えていたのが、幕府から盲人への優遇策として認められていた高利貸しだった。しかし、「座頭金」と呼ばれる盲人のあくどい高利貸しのために、多くの人が追い詰められている実態が次々と明らかになった。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第13回「お江戸揺るがす座頭金」(3月30日放送)。 【写真をみる】“生肌”あらわで捨てられて…「何も着てない」衝撃シーンを演じた愛希れいか 幕府で座頭金を問題視したのは、老中の田沼意次(渡辺謙)だった。勘定吟味役の松本秀持(吉沢悠)には、鳥山らの屋敷や身代を調査させ、江戸城西の丸(将軍の世継ぎや隠居の居所)で献上品などを管理する長谷川平蔵(中村隼人)には、座頭金に手を出している者が西の丸にいないかどうか調べさせた。 田沼意次を演じる渡辺謙 その結果、松本からは、借金を返せない者が家督を乗っ取られることさえある、という報告が上がる。また、長谷川によれば、西の丸では小姓組の旗本の森忠右衛門が、借金を返せないのを苦に逐電したという。 事態を解決するために、意次は策を講じた。将軍徳川家治(眞島秀和)のもとを嫡男の家基(奥智哉)と、老中首座の松平武元(石坂浩二)が訪れると、そこに意次が現れ、森忠右衛門(日野陽仁)と息子の震太郎を招き入れ、説明をさせた。森によれば、俸禄つまり給料だけでは家族を養えず、座頭金に手を出したところが、高利のために借金がどんどん膨張し、ついには家督を譲るように脅迫され、切腹を覚悟。だが、息子に止められて逐電し、出家したという話だった。 教科書では「賄賂政治家」だったが そのうえで意次は「森は遊興とは無縁。常に質素倹約を心がけてきた者が、ここまで追い詰められたのにございます」と訴え、座頭金に手を染めている西の丸の関係者の名簿を家基に見せた。そしていった。「高利貸しを行う鳥山らを、一斉に取り締まらせてはいただけませんでしょうか」。 松平武元が、盲人の優遇策は神君家康公の意向だ、と反発すると、意次は声を荒げて熱弁をふるった。本当に弱い盲人には手を差し伸べるべきだ、という前提で、「不法かつ巧妙な手口でかような蓄財をなしえた検校らは、もはや弱き盲ではない! いま徳川が守らなければならぬ弱き者は、どこのだれなのでございましょうか」と。意次のこの言葉は将軍を動かした。家治は「余は徳川家臣および、検校に金を借りておる民草を救うべきと考える」と述べ、息子の家基に「そなたはどうじゃ?」と問うた。 この田沼意次の訴えは至極真っ当である。それに、これまでも『べらぼう』では、意次は常識人として描かれてきた。だが、違和感を覚える視聴者もいるのではないだろうか。かつて田沼意次といえば、教科書でいつも「賄賂」とセットで表記され、悪徳政治家のイメージが定着していたのだから。 また、ドラマ等に登場してもたいていは、時代劇の定番の「悪代官」よろしく、欲深い目つきで小判が詰まった菓子折りを受けとる人物だった。 ところが、悪徳政治家という評価は、いまではかなり修正され、まったく異なる田沼意次像が明らかになっている。 めざましい出世と苛烈な転落 田沼意次が発揮した力の源泉は、9代将軍家重と10代将軍家治の2人から厚く信頼されたことにあった。とはいえ、まだ8代将軍吉宗の時代、17歳にして家重の西の丸小姓に抜擢されたとき、前年に死去した父の意行から受け継いだ家督は、600石にすぎなかったが、以後の昇進はめざましかった。 元文2年(1737)、19歳にして従五位下主殿守という大名並みの官位を叙任され、延享2年(1745)に家重が9代将軍に就任すると、随伴して本丸に仕えた。寛延元年(1748)には小姓組番頭に昇進して、上総(千葉県中央部)と下総(千葉県北部と茨城県南西部)に1,400石の知行地をあたえられ、宝暦5年(1755)にはさらに3,000石が加増され、同8年(1758)には、40歳にしてついに大名になった。 宝暦11年(1761)に家重が死去しても、まったく力を削がれないどころか、むしろ政治上の影響力を強めた。明和4年(1767)には側用人に就任し、5,000石の加増を受け、従四位下に叙位され、さらに加増を重ねて2万石の大名になり、遠江(静岡県西部)の相良(牧之原市)に築城を許されている。 明和6年(1769)に老中格、同9年(1772)には名実ともに老中に昇格したが、そのまま将軍のそば近く使える側用人も兼務したため、老中としては首座ではなかったにもかかわらず、権力が意次に集中することになった。最後の加増は天明5年(1785)1月の1万石で、これで5万7,000石の中級譜代大名になった。 ところが、天明6年(1786)8月25日、将軍家治が死去する。その直前、家治に遠ざけられ、死去の2日後には68歳にして側用人兼務の老中職を解かれ、閏10月には家治の治世に加増された2万石と、江戸の上屋敷や大坂の蔵屋敷を没収された。 すべては将軍家の恩に報いるため この意次の昇進と転落は動かしがたい事実だが、そこに強欲や金まみれのイメージを重ねると、この人物を見誤ってしまう。翌天明7年(1787)5月、意次は苦境から脱したい思いで、大元帥明王にすがっている。捧げた願文には、こう書かれている。 「惇心院様(家重)浚明院様(家治)ニ仕エ奉リ、莫大之御高恩ヲ蒙リ、剰ヘ老職(老中)に補セラレ、大禄ヲ下シ賜リ、御慈恵月々ニ厚ク、年々重シ。其高キコト嶽ノ如ク、其深キコト海ノ如シ。然レバ則チ、昼夜心力ヲ尽シテ、御高恩ノ万箇之一報ジ奉ラント欲スルノ外、更ニ他事無ク、偏ニ天下之御為ヲ奉ジ奉リ、聊カモ身ノ之為ヲ致サザル処ハ、上天日月之ヲ照覧シ、神明仏陀同ク共ニ、之ヲ明知シ賜フベキ也」 要するに、家重と家治に仕え、山のように高く海のように深い恩を賜り、大きな禄をいただいた。力を尽くしてきたのはその恩に報いるためで、少しも自分のためでなく、ひとえに天下のためだけに尽力してきたことは、太陽も月も見ているし、神仏も承知している——。そう必死に懇願している。文面からも、これは真摯な心情の告白だろう。 『べらぼう』の第13回でも意次は「私はただ、徳川の世を守りたいだけの者にございます」と強く述べたが、その台詞はこの願文とそのまま重なる。 そんな意次の政策は「重商主義的」経済政策と呼ばれる。代表例として株仲間が挙げられることが多い。じつは株仲間自体は吉宗も認めていたが、それは商人を統制するためのものだった。一方、意次は運上金や冥加金という営業税を徴収して、幕府の財政を補填しようとした。 殖産興業にも積極的だった。蝦夷地の開発や鉱山の振興を進めようとしたが、そういうときは民間の献策をもちい、民間活力を利用しようとした。白砂糖や朝鮮人参の国産化に際しても同様だった。 幕府の利益を追求しすぎた結果 この時代、否応なく商業活動が拡大し、農業が商業に組み敷かれるようになってきていた。以前は、そこで商業を統制し、農本主義への回帰が指向されたが、それは不可抗力で膨張していく商業の前に虚しい抵抗だった。一方、現状を受け入れ、商業が拡大しているなら、そこから利益を引き出せばいいと考えたのが、田沼の政治のあたらしさだった。 だが、民間から次々と献策を募る状況下では、賄賂が横行するのも不思議ではない。田沼時代の代名詞のように語られてきた「賄賂」は、実際、数多く見られたようだ。ただし、意次の名誉のためにいえば、彼が賄賂を受け取ったという記録はない。 そして、意次にとっては重商主義的な政策、すなわち利益追求型の政治は、彼がのちに大元帥明王に誓うように、自分の懐を潤すためではなく、幕府の利益のためだった。すなわち将軍家にとって意次は、きわめて儒教的な忠義の家臣だったのである。 ただし、追求したのが幕府の利益に偏りすぎていたため、次第に諸藩が抵抗し、商人たちも抵抗するようになり、意次は足を引っ張られる。 先の願文を書いた天明7年(1787)10月2日、意次はさらに所領2万7,000石と相良城を没収された挙句、隠居および謹慎を命じられる(辛うじて1万石は孫の意明のために残された)。そして失意のうちに、翌天明8年(1788)7月24日、70歳で没した。 しかし、この処分は、私利を追求したから下されたのではない。幕府の利益を追求しすぎたがゆえのものだった。異例すぎる出世を遂げたばかりに、それを実現してくれた将軍家への恩返しという意識に縛られすぎたのかもしれない。 香原斗志(かはら・とし) 音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』(ともに平凡社新書)。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。 デイリー新潮編集部