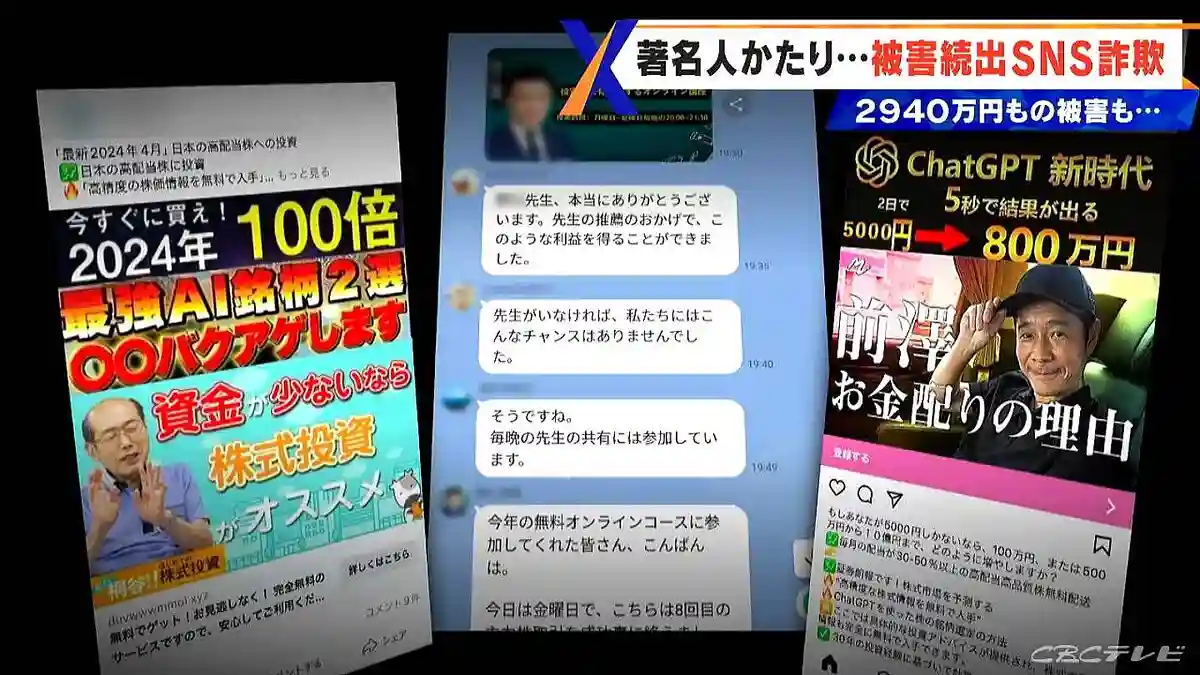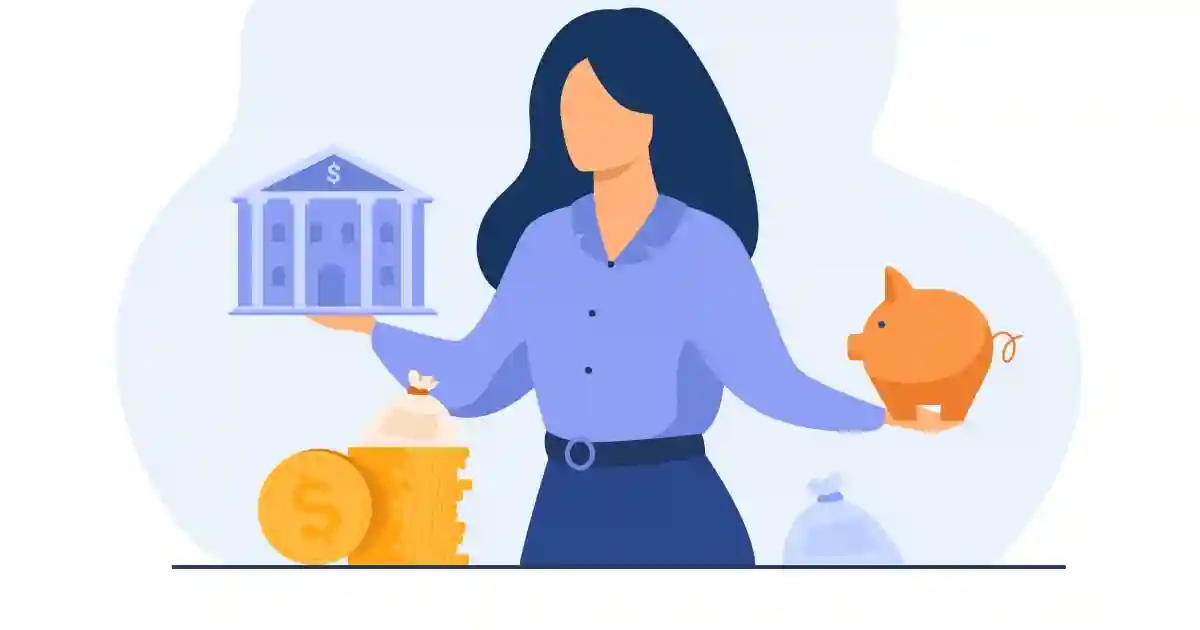
「お金を稼ぎ続けなければ生きていけない」、「生きてくためには会社を辞めるわけにはいかない」、「生きるためには仕事の質なんて言ってられない」……。 これらの言葉はコミュニティデザイナーとして活躍する山崎亮さんが、まちづくりのワークショップなどを行う中で出会った、参加した地域住民の方々の意見の一部です。 現代を生きる私たちにとっては、常識的に感じられるこれらの言葉。しかし、違和感を覚えた山崎さんは、こういった「経済の常識」がどこから生まれたのかを調べるために、アダム・スミスやマルクス、ケインズなどの経済思想を辿りなおします。 その中で見えてきたのが「面識=顔の見える」関係の重要性です。ほかにも、ジョン・ラスキンやウィリアム・モリス、柳宗悦、イヴァン・イリイチ、ジェイン・オースティンなどの数多くの思想家の書物を紐解き、多岐にわたる「経済の考え方」を分析しながら、山崎さんご自身の経験などをもとに著された一冊が『面識経済』です。 そんな『面識経済』より、一部を公開いたします。 『「分業」すると「仕事の悦び」がなくなる? 分業しない働き方が見直されている「理由」』より続く 重商主義という時代背景 ここで、スミスが『国富論』を書くことになった時代背景についても触れておきたいと思います。『国富論』より前のイギリスは、ヨーロッパの覇権争いに心血を注いでいました。軍事力を高め、植民地を拡大し、うまく経営してイギリスに多くの金銀を集中させることが国を富ませることになる。そう考えられていました。いわゆる「重商主義」です。 だから政府は輸入を制限して金銀が流出しないようにしつつ、輸出を促進して対価としての金銀を増やそうとしていたのです。「国の富は金銀の量が決める」というわけです。 その結果、軍事力強化のために多くの費用をかけ、他国を支配しては不平等な交易によって金銀を増やす。国家は金銀が得られる輸出を推奨し、逆に金銀を国外に支払ってしまう輸入は控えるよう規制する。これが国を富ます方法だと信じられていたようです。 金銀財宝は食べられないし、土も掘れない そんな風潮に対して、スミスは異を唱えた。国富とは他国の支配や貿易で金銀を増やすことではない。自国の懸命な労働によって物を増やすことこそが国富である。そう主張したわけです(*1)。 私はスミスについて語り始めた冒頭に「物をたくさん持つ国が豊かだという、現代から見れば時代錯誤な考え方をしている」と書きましたが、その背景には重商主義からの脱却という命題があったのです。 少なくともスミスの時代には、「金銀を多く持つことが国の豊かさではなく、国民が使うことができる物やサービスが多く存在する国こそが豊かなのだ」と言わなければならなかった。そういうことなのでしょう。 だって、金銀財宝は食べられないし、土も掘れないし、ピンの先を削ることもできないのだから。だからこそ、市民が必要だと思うものを別の市民が作り、それを自由にやりとりできる市場を準備することこそが「国富」につながる方法だと主張したわけです(*2)。 (*1)スミスは『国富論』の第四編第一章で「商業、つまり重商主義の体系と原動力について」述べています。その一節で「富は貨幣であるとか、金や銀であるというのは、交換の手段および価値の尺度としての貨幣の二重の機能から自然に発生する通俗的な観念である」と語り、続く二節で「豊かな国とは、金持ちの人間と同じ仕方で、貨幣がたくさんある国のことだと考えられているし、どの国であれ、金や銀を蓄積することは、国を富ませるもっとも手短な方法だと信じられている」としたうえで、第十七節で「富は貨幣に、すなわち金や銀にあるのではなく、貨幣が購入するものにある」とスミスは述べています(アダム・スミス著、高哲男訳『国富論(上)』講談社学術文庫、2020、p615-628) (*2)金や銀をたくさん手に入れるために他国と戦争したり、金や銀を国外へと流出させないよう政府が貿易を規制したりすることを、スミスは『国富論』第四編第一章の後半と第二章で批判しています。それが、先に挙げた「公共のためと称して貿易に影響を及ぼした人々によって、多くの望ましい結果が達成されたことなど、私は聞いたことがない」という言葉につながるのです 「富」とは何か スミスが『国富論』を書いてから約100年後、同じくイギリスの思想家であるジョン・ラスキンは『この最後の者にも』(1862年)を書きました。このなかでラスキンは、「人生こそが財産である。その財産を使って他の人に良い影響を与えましょう。そういう人生こそが豊かな人生であり、そういう人がたくさん住む国こそが豊かな国なのです」という国富論を説きました(*3)。 「国の富とは何か」についていえば、私はスミスよりもラスキンの考え方が好きです。ただし、これは時代が違うし時代背景も違う話なので、後世から見た人間の勝手な好き嫌いの話だと聞き流してください。スミスやラスキンが「富んだ国」と表現したものを「富んだ地域」と読み替えてみれば、私には金銀をたくさん蓄えた地域(重商主義的地域)が富んだ地域だとは思えないし、物をたくさん蓄えた地域(国富論的地域)が富んだ地域だとも思えない。 むしろラスキンが言うように、「他の人に良い影響を与え続ける人」がたくさん住む地域こそが富んだ地域だと思います(*4)。もちろん、「他の人に与える良い影響」のなかには、必要な物を生産したりそれを販売したりすることも含まれますが、その量だけが地域の豊かさを測る指標だとは思えないのです。 (*3)この点については次章で詳述します (*4)ジョン・ラスキン著、飯塚一郎ほか訳『この最後の者にも』中央公論新社、2008、p158 「公平な観察者」は対話から生まれてくるものだ だからこそ、コミュニティデザインのワークショップでは顔が見える関係づくりを重視し、信頼できる関係性を構築し、他の人に良い影響を与えるようなつながりを生み出したいと考えています。同時に、しつこいくらい他者との対話を繰り返したいと思います。 なぜなら、道徳感情の共感や、心の中に育まれる「公平な観察者」は、他者との対話から生まれてくるものだとスミスが指摘しているからです。地域で貨幣のやりとりが生じてもいいと思いますが、他者を押しのけたり欺あざむいたりしないフェアプレイであることや、貨幣をたくさん蓄えることが目的化しないように注意したいと思っています。 以上のようなことを考えながらワークショップで出る意見を聞いているので、参加者からの意見の背景にある経済思想がどんなものなのかがとても気になるのです。古典派経済学と呼ばれるスミスの考え方は、地域社会における対話、交流から発想した『道徳感情論』と、そこから発想して金銀を溜め込むのではない『国富論』を大胆に論じたという意味で好きな思想です。そして、スミス以後にもマルクス、ケインズと振り子を大胆に揺り戻すような思想が登場しました。これらについても本の中で概説してみたいと思います。 【つづきを読む】「“公共のため”と気取っている人が成果を出した例を私は知らない」アダム・スミスの言葉の「本当に意味」を読み解く