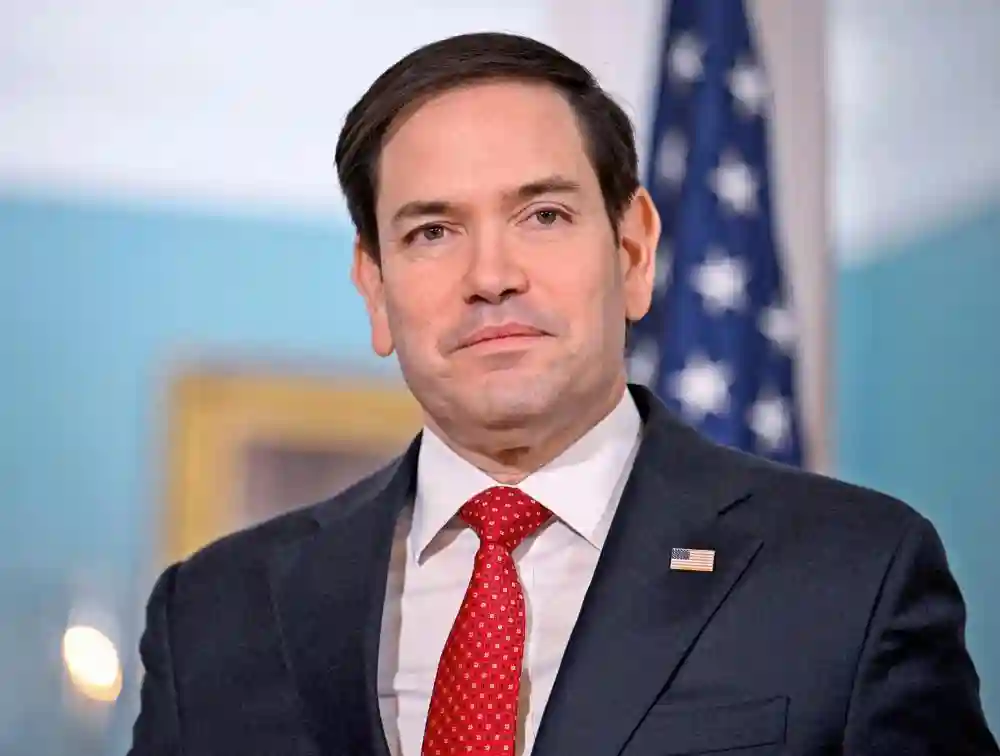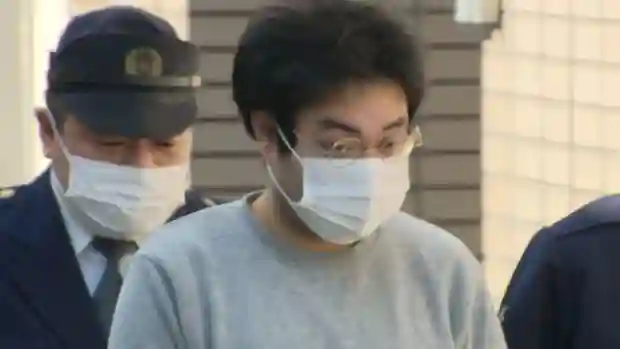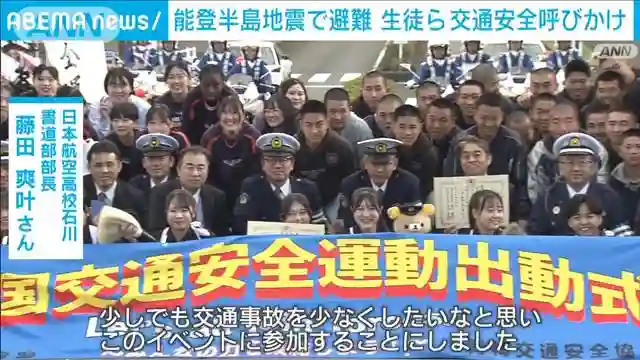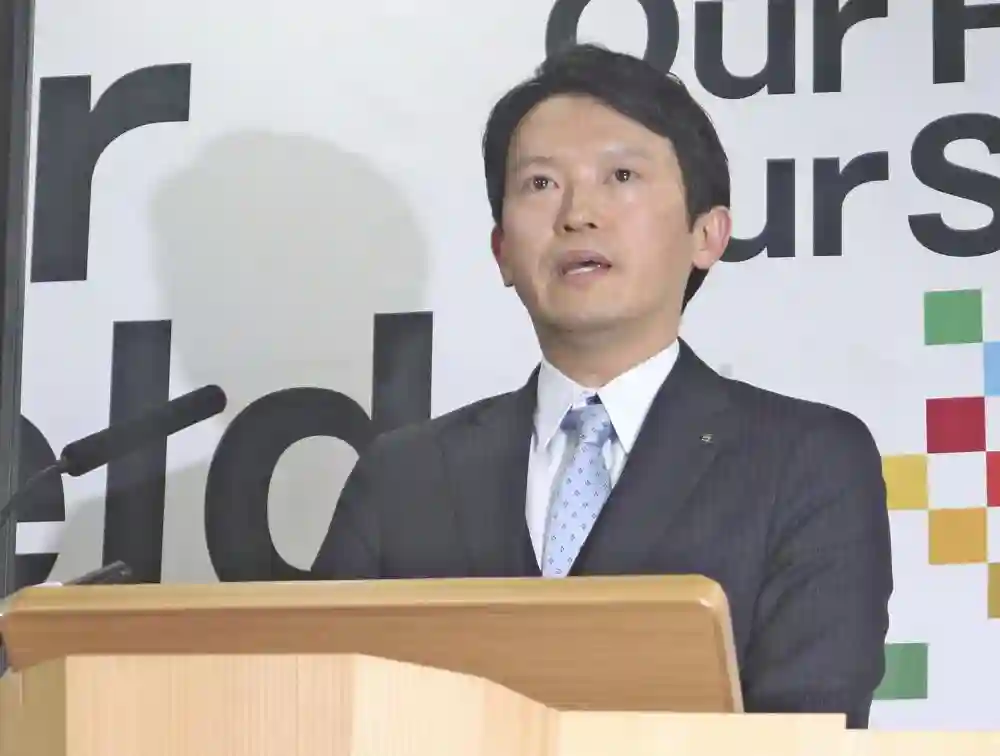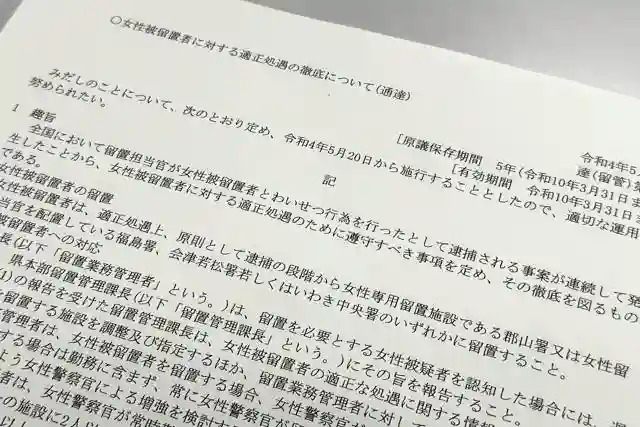的確な情報を要求し、新たな変化と危機を察知し、他社より素早く判断を下す。 社会を味方につけ、ルールメイキングで主導権を握り、競合を突き放す。 組織の弱みをあぶり出し、最強最高のチームをつくる。 これらを可能にする決定打が「インテリジェンス・サイクル」であると、かつて官の立場で諜報事件捜査に従事し、民の立場で経済安全保障対応などコンサルティングファームで経験を積んだFortis Intelligence Advisory株式会社代表の稲村悠氏は訴える。たしかに、地政学リスクの高まり、米中対立の激化に加え、SNSによる情報過多や偽情報の流通、スパイによる技術流出などによって、ビジネス環境の先行きがますます読めなくなってきた今、「インテリジェンス」の必要性を疑う企業はないだろう。しかし、その認識が高まっても、「インテリジェンスって使えるの?」と言われる現実もある。ではどうしたら「使えるインテリジェンス」ができるのか。新刊『企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法』(講談社+α新書)から連載でお届けする。(4回連載の第4回) 『 企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法 』 (講談社+α新書) 「経済安全保障の部署はできたけど、いったい何をすれば……?」より続く 経営者が課題を正しく設定できない 現場から聞こえてきた声は、まさにインテリジェンス・サイクルにおける日本企業の課題を示すものでした。その課題はある意味、企業病にも通ずる部分が多分にあると考えます。見えてきた課題は、主に次のようなものです。 ●不適切な情報要求 インテリジェンス・サイクルの機能不全を起こす重大な要因として、経営層の課題設定が正しく行われずに適切な情報要求がなされないことが挙げられます。これでは、インテリジェンス・サイクルの前提が破綻してしまいます。不適切な情報要求を受け取ったインテリジェンス担当者は、当然ながら不適切なインテリジェンスしか生成できません。この不適切な情報要求は、「問いを立てる力」、つまり適切な課題設定をする能力に直結し、インテリジェンス・サイクルの肝となってきます。 また、「将来世界がどうなるのか知りたい」といった具体性に欠ける情報要求がなされると、インテリジェンス担当者は困惑し、具体性に欠けたインテリジェンスや期待しないインテリジェンスを生成してしまいます。 そもそも、インテリジェンス・サイクルによって得たインテリジェンスから何を成し遂げたいのか、明確な戦略・ゴールが描けていないケースもあります。インテリジェンス・サイクルを回す土俵にすら立っていないと言えるでしょう。 ●戦略・理念の共有不徹底 インテリジェンス・サイクルが形骸化する要因として、戦略や理念の浸透が徹底されていないことが挙げられます。インテリジェンス・サイクルを回すには、情報要求の正しい理解、つまり意思決定者が何を欲しているかを明確に理解する必要があります。それには、意思決定者側にも明確な目的と指針が必要です。 しかし、多くの企業では経営層が掲げるビジョンや目標が具体的に現場へ伝わらず、担当者が「何のために情報を集めるのか」を理解しないまま業務を進めてしまうケースが目立ちます。すなわち、担当者が意思決定者の描くビジョンを汲み取ったうえでのインテリジェンスを提供できなくなるのです。戦略論の文脈では、類似のケースが複数報告されていて、「ビジョンが曖昧だと現場が翻弄される」といった事例が散見されます。いずれも、戦略レベルの曖昧さがインテリジェンス担当者や情報分析チームの業務効率を低下させる典型パターンとして紹介されています。 このような曖昧さが続くと、インテリジェンス・サイクルが無駄に膨らみ、現場と経営の間に不信感が生じます。そして、形骸化した無駄なインテリジェンス・サイクルがカラカラと回ることになるのです。 失敗を報告するのがタブー視されると起きること ●フィードバック不足によるモチベーション低下 また、インテリジェンス・サイクルが適切に回らない要因の一つとして挙げられるのは、フィードバックの不足です。担当者は、日々膨大なデータを収集し、分析し、レポートとしてまとめる労力をかけています。しかし、これが社内の重要な意思決定に反映されない、あるいは評価されない状態が続くと、「何のためにやっているのかわからない」とモチベーションを失いがちになります。 「あとで読んでおきます」とか「はい、わかりました」といった報告先の曖昧な対応が続くと、苦労して作成したアウトプットを報告しても、インテリジェンス担当者は自分の仕事が組織にとって不要なのではないかと感じ始め、やがてやる気を失います。こうした状況が積み重なることで分析結果の質まで低下し、インテリジェンス・サイクルそのものが形骸化していくのです。 米国のあるソフトウェア企業では、データ分析チームが毎月提出していた市場動向のレポートに対し、上層部からの反応がほとんどありませんでした。分析結果が経営の議題に反映されることも少なく、半年後には重大な市場の変化を見逃してしまったのです。インテリジェンス担当者は後に「私たちの仕事が見過ごされていると思っていた」と証言しており、フィードバックの欠如が組織全体の学習能力と応答性を損なった一例と言えます。 さらに、失敗を報告することがタブー視される企業文化も、インテリジェンス・サイクルの正常な運用を阻害します。そもそもインテリジェンス・サイクルは学習と改善のプロセスである以上、失敗やリスク情報を共有することがきわめて重要です。しかし、組織文化として失敗を一切許容しない場合、担当者は自己防衛に走り、問題を隠したり過少報告したりしてしまいます。その結果、意思決定における信頼性が低下し、再びサイクルが断絶されるのです。 加えて、このような状況に陥る段階で、担当者が情報要求者に対して「迎合」する傾向が顕著になります。インテリジェンス活動はもともと負荷が高く、「生みの苦しみ」を伴うものです。したがって、「失敗を避けたい」「早く終わらせたい」という心理が強くなると、情報要求者の意図に寄り添った楽なアウトプットをしてしまいがちになります。これがいわゆるエコーチェンバー現象を企業内で引き起こし、意思決定者にとって都合のよい情報ばかりが集まることで、インテリジェンス・サイクル全体が歪んでしまうのです。 日本企業の悪しき体質として、社員が揉め事を嫌い、前提を疑わずに指示に従う傾向があることが、インテリジェンス・サイクルの機能不全を生む大きな要因になっています。 部門ごとの独自の理念が無視されると ●コミュニケーション不足による情報断絶 企業内におけるコミュニケーション不足は、当然インテリジェンス・サイクルの運用を著しく阻害する要因です。これは、「タテ」「ヨコ」それぞれのコミュニケーション不足が大きな障害となります。たとえば、「タテ」のコミュニケーションでは、インテリジェンス担当者が、意思決定者とのコミュニケーションに障害を感じることで、意思決定者の情報要求の意図を深掘りできなくなります。そうなると、「これはどういう意味ですか?何を見据えていますか?」という情報要求の重要な部分での質問が遮られることになります。 また、インテリジェンス・サイクルでは、情報要求、収集、処理、分析、報告・配布の各段階で複数部門との連携が必要となります。「ヨコ」のコミュニケーションでは、マーケティング部門からの情報ニーズ、研究開発部門からの技術動向に対する要件、経営企画部門からの競合調査など、それぞれの情報ニーズを束ねて優先度をつける作業が欠かせません。 しかし、この調整プロセスがうまくいかないと、インテリジェンス・サイクルの最初の段階である「情報要求」自体が曖昧となり、独善的なものになり得ます。部門ごとの独自の理念が無視される場合、部門間での対立や摩擦が発生し、独りよがりなインテリジェンス・サイクル運用に陥る危険性もあります。 さらに、共有プラットフォームにデータをアップロードする際に偏りが生じることや、形式だけの共有が行われることが一般的です。その結果、インテリジェンス・サイクルが情報の有効活用を目指す本来の目的を果たせなくなります。 このように、「タテ」「ヨコ」のコミュニケーション不足により、各人が孤立するジレンマに陥ってしまい、効果的なインテリジェンスが生成されなくなってしまいます。そして、不要なインテリジェンスが生成されることで、組織内でインテリジェンスの信頼性に疑問が生じ、インテリジェンス・サイクルがどんどん形骸化していきます。 リモートワークが普及した昨今では、部門間の情報共有だけでなく、同じ部門内でのコミュニケーションにも課題が生じています。オンライン会議やチャットツールの利用が標準化された一方で、対面での雑談や即席のアイデア交換が激減し、細やかな調整や暗黙知の共有が難しくなりました。このようなコミュニケーション不足が、情報要求、情報収集や分析の質を低下させる一つの要因となっています。 自分の仕事さえ完了すればOK!? ●個人主義化 インテリジェンス・サイクルの形骸化には、担当者やチームメンバーの帰属意識の低下も密接に関わっています。 現代の労働市場では、特に若年層を中心に転職志向が高まり、「自分のキャリアを重視する」という意識が強まっています。このような背景から、インテリジェンス・サイクルに携わる担当者が組織内で蓄積したノウハウを長期間維持することが難しくなっています。 その一例が、インテリジェンス・サイクル担当者が数年で退職してしまうことです。退職後に新たな担当者がゼロから業務を学ぶ必要があり、インテリジェンス・サイクルの継続性が損なわれます。 帰属意識の低下は、情報共有の意欲や責任感の欠如にもつながります。インテリジェンス・サイクルの各段階で発生するミスや不足を補うには、強いチーム意識が必要ですが、それが欠落していると、個人が「自分の仕事さえ完了すればよい」と考え、インテリジェンス・サイクル全体の統一性が失われてしまうのです。このような環境では、個人プレーが強まり、結果として組織の意思決定が非効率になるリスクが高まります。 情報のゴミ箱化 ●現代特有の情報過多がもたらす困難 現代の企業は、インターネットとSNSを中心に膨大な情報を瞬時に入手できる環境にあります。市場動向や競合企業の動き、技術革新のレポート、政治・経済ニュース、さらには顧客の声や口コミなど、多種多様なデータを日々キャッチすることが可能です。しかし、この「情報過多」はしばしば逆効果を生み、「何を優先して分析すればいいのかわからない」「信頼性の低い情報まで大量に流入してきて整理しきれない」といった混乱を引き起こします。 また、情報を精査するスキルや時間が社内に十分ないまま、やみくもに収集だけが進むと、「データはあるけれど使える形になっていない」という「情報のゴミ箱化」が起こる可能性があります。インテリジェンス・サイクルのステップとしては収集と処理・分析が分かれているものの、その境界が曖昧になっている企業も多く、結果的には情報過多が意思決定を遅らせる要因にさえなってしまうのです。 もう一つの現代的特徴として、社員個々人が自由に情報を取得・発信できる環境が挙げられます。SNSアカウントや個人のブログ、情報共有プラットフォームなどを通じ、誰でも多様な情報に触れられるようになりました。一方で、正式な手順を経ずに非公式情報が分析されたり、十分なチェック体制を経ないまま経営層に報告が上がってしまったりと、統制不能になりやすいリスクもあります。 以上の各課題が解決されないことで、最終的には「形だけインテリジェンス・サイクルを回しているように見えるが、実際には誰もきちんと使っていない」という状態、すなわち形骸化に陥ります。形骸化は一度進行すると、「インテリジェンス・サイクルなんて役に立たない」という社内認識が広まり、制度や仕組みの形だけが残って実態は何も変わらないという状況を生み出しやすくなります。実際に、導入段階では大きな期待を持たれていたインテリジェンス・サイクルが、数年後には「なんとなく残っている」程度になっている企業事例は少なくありません。 『 企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法 』 (講談社+α新書) 的確な情報を要求し、新たな変化と危機を察知し、他社より素早く判断を下す。社会を味方につけ、ルールメイキングで主導権を握り、競合を突き放す。組織の弱みをあぶり出し、最強最高のチームをつくる。 そのために今、最も必要なのが「インテリジェンス・サイクル」の実装だ。 地政学リスクの高まり、米中対立の激化に加え、第二次トランプ政権によってグローバル経済が大転換する今、企業にはますます「インテリジェンス」が必要になっている。一方で、その認識が高まっても、「インテリジェンスって使えるの?」と言われる現実もある。インテリジェンスの現場とコンサルティングファームで経験を積んだ実務家が、企業を襲う危機の対応から新規事業創出まで可能にする「インテリジェンス・サイクル」の構築を指南する! (「はじめに」より) 本書でお伝えしたいのは、「企業が戦略を実現するためのインテリジェンス・サイクル」です。インテリジェンス・サイクルとは、戦略の立案や課題解決のために、組織のトップ層が「情報要求」=つまり正しく課題を設定することでインテリジェンスの生成を命じ、その答えを導くものを見つけていくプロセスを指します。生成されたインテリジェンスを分析し、さらに次のインテリジェンスを生み出すべくフィードバックする。そのサイクルを繰り返すことによって、インテリジェンスは組織全体を束ね、的確な方向性を示すコンパスとして機能します。 インテリジェンス・サイクルが有効なのは、地政学リスクや技術流出、不祥事への対応だけではありません。企業が新たな技術やサービスを世の中に広めたいと願うとき、または戦略的な目標を実現するために積極的に情報を収集・分析しながら、多様なステークホルダーとのコミュニケーションを通じて合意形成を図る「攻め」の動きでも、インテリジェンスの思考法が大いに役立つのです。 【目次】 第一章 日本企業のインテリジェンス・サイクルは機能しているか 第二章 新しいインテリジェンス・サイクルの形 第三章 インテリジェンス・サイクルの成功を握る鍵 第四章 インテリジェンス・サイクルに必要な人材と能力 第五章 「守り」のインテリジェンス・アプローチ——リスク・インテリジェンス・サイクル 第六章 「攻め」のインテリジェンス・アプローチ——インテリジェンス・アプローチ1 第七章 企業が主体となって社会を変える——インテリジェンス・アプローチ2 付録1 インテリジェンスにおける情報取扱適格性チェックリスト 付録2 意思決定者向けレーダーチャート インテリジェンス担当者向けレーダーチャート 【つづきを読む】経済安全保障の部署はできたけど、いったい何をすれば……?