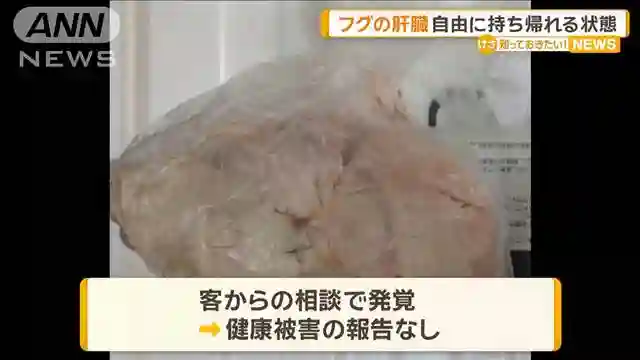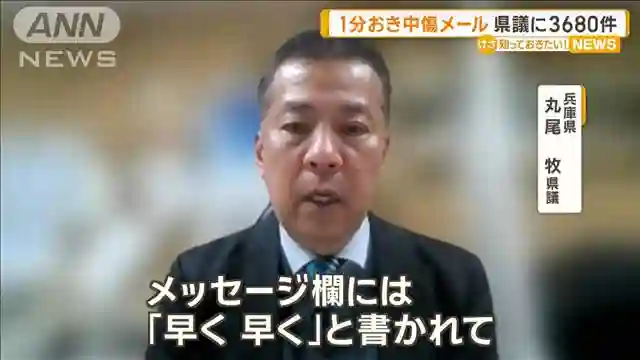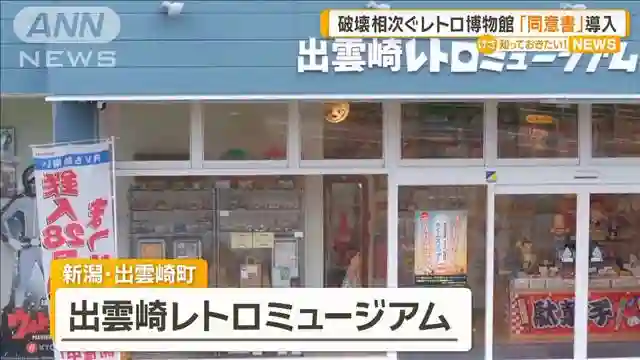2013年にインターネット選挙が解禁されてから、10年あまりが経過した。選挙運動におけるSNS運用などのウェイトが高まる中、現行の公職選挙法のルールは、多くの面において実態に適合しなくなっている。『法が招いた政治不信』の著者で弁護士の郷原信郎氏がその問題点と対策を提案する。 ネット選挙に合わせて、公選法を見直す必要がある 前編記事では公職選挙法の問題点として「SNS上のデマ投稿」をあげた。 次に、選挙運動ボランティアの原則、すなわち報酬支払の禁止と、SNS選挙との関係である。 もとより、選挙コンサルタントなどが、高額の報酬を得て、「当選請負人」のような業務を行うことが公選法の目的に照らし許されないのは当然だが、一方で、SNS運用が選挙で不可欠のツールになりつつある現実の下で、業務としてのサポートを厳格に禁止すれば、候補者自身あるいは陣営のSNS活用のノウハウ・スキルの程度で選挙の当落が決まることにもなりかねず、それも公職選挙の在り方として望ましいとは言い難い。 これまで公職選挙法上、選挙運動に対する報酬支払が、車上運動員に対してしか認められていなかったこと、ポスター、チラシ制作等が公費で賄われていたことなど、現行の公選法の枠組みを、SNS運用が重要な手段となったネット選挙に適合するように見直していく必要があるのではなかろうか。 「紙の選挙ポスター」は過去の遺物 第一に、ポスター掲示板に紙の選挙ポスターを貼るというのは、まさに「紙の時代」の選挙の遺物とも言える手法である。 しかも、選挙区が広く、有権者が多ければ多いほど、貼付のために膨大な労力を要し、そこに多額の機械的労務費も発生する。それが、選挙に金がかかる大きな要因になっていた。 さらに、最近では、表現の自由を逆手にとって、ポスター掲示板に、公序良俗に反するような画像のポスターを掲示するという問題も発生している。それを、可能な限りネットによる方法に改めていくことで、金のかからない選挙にしていくことを考えるべきではなかろうか。 具体的には、公費によるネット上での立候補者の紹介及び情報提供のための場を大幅に拡充し、動画なども含めて提供できるようにする。 ポスターの掲示板も、デジタルサイネージによる電子掲示板の街頭への設置に変更することを検討すべきである。それによって、ポスター制作についての公費負担を削減することもできる。 このようにして選挙に関する開示情報のネット公開が中心になれば、各候補者は、そのような基本情報に関連づけてSNS等による広報戦略を立案し、実行していくことになるが、それに関して候補者間の公平が図れるよう、具体的なルールを定める必要がある。 「SNS運用管理者」制度の導入を そして、ルールに従ったSNS運用を行っていくことについて、一定の範囲で「業務として選挙に関わること」に公的な位置づけを与え、候補者間の公平を図りつつ活用していくことが考えられる。 「公職選挙SNS運用管理者」などと称する制度を導入し、SNSを含む選挙戦略の企画立案・運用の方法や公選法の規定、ルール等について数日間の研修を義務づけ、それらを十分に理解していることが確認できた者にその資格を付与する。そして、候補者には、立候補の届出に当たって、同管理者の選任を義務づける。 この管理者には、候補者側が主体的に行うSNS運用全体を把握し、それがルールに則ったものであるかをチェックするとともに、候補者の周辺でのルール違反行為を認知した場合の当局への通報を義務づける。 そのように適正なネット選挙実現のための公的役割を担うだけに、車上運動員より高額の報酬の支払を認め、その一部を、公費負担の対象とする。 その費用は、ポスター掲示板をデジタルサイネージに変更し、印刷代の公費負担を廃止することによる節減を行えば十分に賄えるのではなかろうか。 【独自】石破10万円問題はこうしてリークされた…もらった議員、反石破議員が次々と明かした「石破おろし」全舞台裏