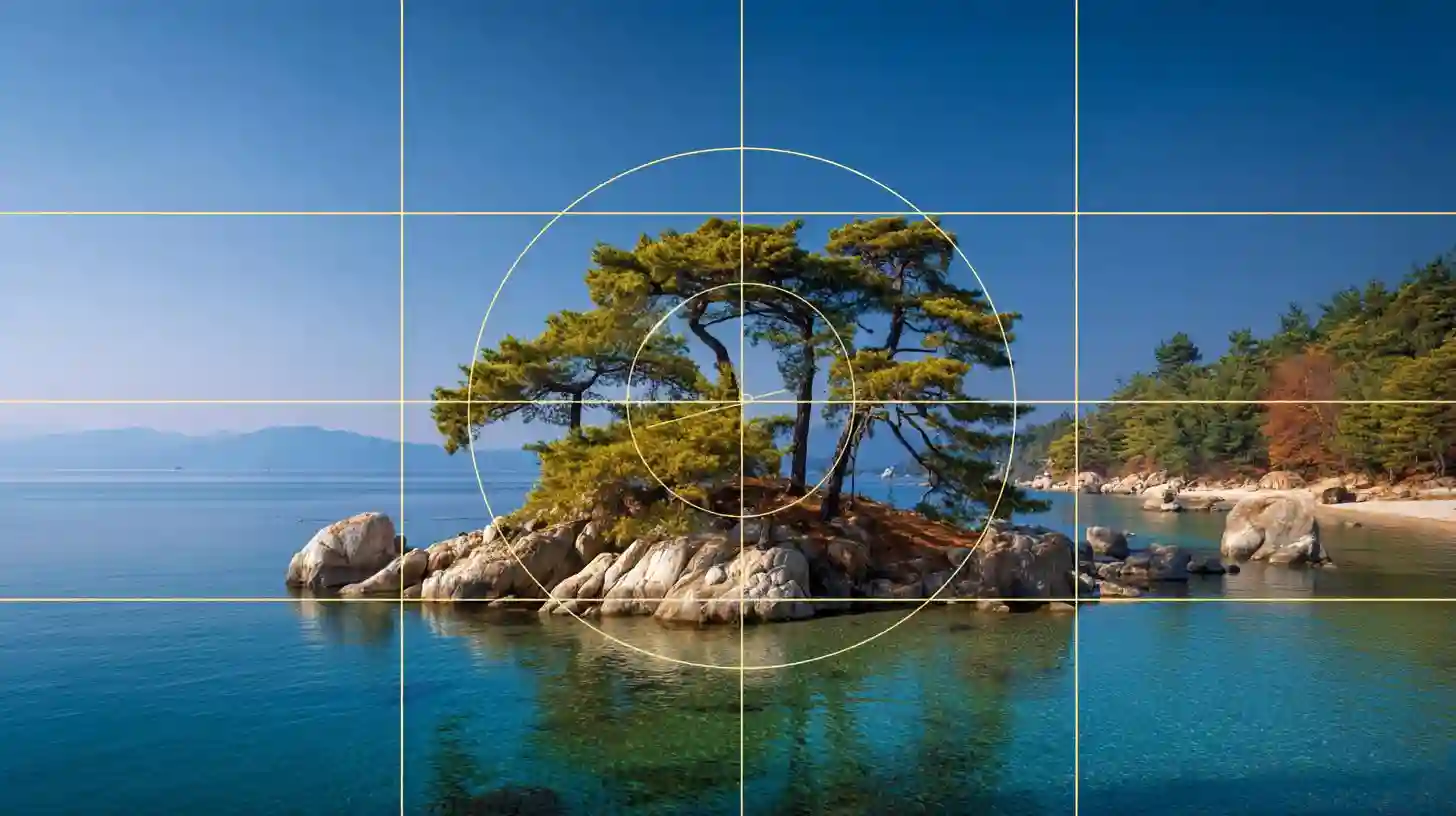夕暮れが山裾を染めるとき、遠い山々は黒緑の輪郭を深い藍色の空に映し出す。風は涼しく、耳の奥で木々のささやきを拾う。田畑の端には影が長く伸び、家の灯りがまだはっきりと浮かぶのを待つ。遠くの峰は雲の影と溶け合い、静かに夜の手前の祈りをつむぎ出す。私は歩みを緩め、足元の土と石の温度を指先で確かめる。雲間の月の光もまだ明るくはなく、代わりに空気の中に滲む紫と灰が、夕暮れの時間をやさしく閉じこめている。遠い山は高い仮面のように立ち、時折風に動くたびに微かな震えを見せる。その震えは、長い旅路の疲れを包み込み、同時に心の奥底に隠れていた何かをゆっくりと呼び戻す。
遠くの山並みはささやきのつぶやきで私を迎える。街道の向こう、川のほとりには小さな灯りが点々と灯る。灯りは川の水面を滑り、波のように揺れ、静かな歌を口ずさむ。鳥は帰路を探すように低く鳴くが、声は風の音と混ざって迷いを失い、私はその混ざり合いの中で自分自身を探す。山の端では夕暮れの金色が消え去り、代わりに深い紺と紫が夜の衣を着せる。遠い峰の影は次第に黒の塊となり、星が静かに現れ、眠らぬ空に天秤のように並ぶ。私は胸の奥で呼吸を整え、耳を澄ませると、遠い山々の呼吸が耳元に近づいてくる気がした。山が呼吸するたび、自分の胸の鼓動も小さく応える。そんな風景は、世界の喧騒を忘れさせ、私を過去の記憶の中へと引き戻す力を持っている。
夕暮れは終わりではなく、次の朝の前夜のように穏やかで、風景の輪郭を少しずつ変えていく。空の縁は薄く柔らかくなり、山影は輪郭をあいまいにし、雲は低く垂れ下がる。私はその変化を眺めながら、日々の営みの重さを肩の力で測ろうとする。遠い山々は大きな静かな鏡のようで、私の言葉を受け止めるとき、返事も喉の奥で温度を変える。川の流れは緩やかに音を落とし、草の匂いと木の香りが混ざって、夜の香りが街へとゆっくりと降りてくる。空気はひんやりし、手の甲をかすめる風は季節の変わり目を知らせるサインのようだ。私は指先を口元へ近づけ、かすかな息の温もりを確かめる。遠い山々は長い年月を越えて培われた沈黙を私に渡し、沈黙は言葉の代わりに心の中で語りかけてくる。私は言葉を急がず、ただ耳を澄ませてその語りに耳を傾ける。やがて夜は深まり、遠い山の輪郭が黒い紙のように静かに張りつく。星の光はまだやわらかく、遠い灯りと混ざり合い、夜の色を一層深くする。
夜はまだ続く。山の隙間から風が抜け、谷の向こうの小さな町の灯りが呼吸を合わせるようにきらめく。私はしゃがんで地面に手を置き、草の感触を確かめる。冷たい露が掌に落ち、指先を伝って血の温もりへと変わる。思い出は風とともに吹き抜け、古い道の風景が頭の中でつながっていく。見知らぬ土地で出会った知人の笑い声、遠い日の雨音、別れてしまった季節の香り。そのすべてが山の静寂と混ざり合い、私の胸の奥の窓を少しだけ開く。遠い山々は遠いという言葉を超え、静かなる存在として私の世界に居座り続ける。星が静かに灯り、風が山の谷を越えて私の心へとささやく。